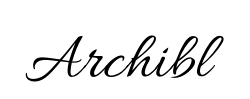わたしは、彼女とおためしという名目でつきあい始めてから一か月が経っているのに気がついた。これからが本番というふうに暑さも徐々に増していた。
今もわたしは一人で絵を描いている。前回描き終わった絵はもう既に提出済みで、課された分は終了していたからノルマというわけではなく、単純に自分が描きたいからという理由で筆をはしらせていた。
最初の告白では理解に時間がかかり、しかも押し切られるような形で交際を開始したが、それはそれで良かったのではないかと思い始めていた。結局、今のところわたしは女の子である彼女のことが好きなのかどうかわかっていないし、それは彼女もだろう。ただ、わたしにとっては学校で気兼ねなく話せる人間ができたことは貴重だと思えた。
「凜ちゃん」
この一か月で聞き慣れた声に振り替えれば、そこには彼女がいた。ショートカットを揺らして嬉しそうな顔をしていた。わたしも自分が笑顔になるのを感じた。
彼女との関係を言い表すのは難しいかもしれない。二人の間でのとりきめでは恋人で、はたから見ればただの仲が良い、いわば親友のような関係性。最初に言われた親友以上恋人以下という言葉は言いえて妙だということがわかった。
彼女は部活をしていないらしく、放課後は教室に残って参考書を片手に勉強している。そしてわたしは美術部から離れた場所で絵を描いている。キャンバスを片づけ終わったのを見計らったかのように彼女が現れて一緒に下校する。
クレープやアイスクリームなんかを買い食いして、時にはファミレスで長いこと話して、それでわたしと彼女は一か月とは思えないほどに仲良くなれた。
「いつも待たせてごめんね」
親友以上恋人以下の彼女に声をかけた。わたしはただの友人だろうと構わなかった。今が楽しいから、その関係性に甘え続けようと思っていた。恋だとか愛だとかわからなくても良い、ただの高校生だから。
わたしの言葉づかいもあの日から、初めて会った日から随分と変わったことは自覚していた。彼女に敬語を使わなくなったし、友人にするように砕けた調子で、ときおり冗談も交えながら話すようになっていた。
「いつも言ってるでしょ? 気にしなくて良いって。私だって直前までは参考書で勉強してるんだから」
わたしは教室の扇風機を止めると、外側の窓を閉めきり、廊下側の窓と扉にも鍵をかけた。
「凄いね。深月ちゃん、この前のテストでもかなり上位だったでしょ?」
わたしの言葉に得意げに、
「まあね。勉強してますから」
そう言い置いてから、
「でも、部活しながら上位に喰い込んでる凜ちゃんのほうが凄いと思うけれど?」
わたしは少し照れながら、
「それは深月ちゃんの教え方が良いからだよ」
そう告げた。彼女は頬をかきながら、
「それじゃあ、帰ろうか」
「そうだね」
二人で頷き合った。
わたしと彼女は仮の恋人で、友人で。わたしにとっては興味の対象で。彼女にとっては自分のことを知るための秤で。
はたから見ればきっとわたしたちは恋人でない。きっとそうだ。でも、だからこそこの関係は長いこと続けば良いなと思った。わたしが最初に言った、互いに好きな人ができれば別れることになったとしても、彼女とは仲良くありたいと思った。
「綺麗な髪だね」
手櫛でわたしの長い髪を整えるのは深月ちゃんだった。今日は学校帰りに寄ったアクセサリーショップで互いに似合うものを選び合うことにしていた。
彼女はイメージを固めるためにとわたしの髪をさらさらと何度もすいてわたしもされるままにしていた。アクセサリーは普段は着けない。面倒だし、鬱陶しい。どうしてもと彼女から言われて、じゃあ髪飾りをと告げると嬉々として髪をさわり始めた。
「深月ちゃんの髪も短いけれどちゃんとお手入れされていて綺麗だよ」
わたしは彼女のショートヘアに軽く触れながら言った。
「私は短いから楽なの。でも凜ちゃんは長いから大変でしょ? シャンプーもリンスもドライヤーも。時間かかってよく遅刻しないね、朝とか」
「わたしはあんまり寝ぐせできないから。できてても気にしないし」
近くの商品、ヘアピンにふれながら答えた。
「そんなのはよくないよ。凜ちゃんは可愛いんだから身だしなみをきちんと整えていればモテます」
「今は深月ちゃんの彼女なわけだけど?」
わたしの答えに、
「別に彼氏彼女がいようがいまいが、モテるってことは魅力的だってことなんだからいいじゃん?」
わたしは彼女の言葉になるほどと首肯を返しながら次の棚へと向かった。彼女はわたしの髪を持ったまま後ろからついて来た。
「いい加減離しませんかね、深月ちゃんや」
わたしはそろそろ疲れてきて後ろ手に彼女の手をつかんで引き寄せた。
「ほら、そろそろいいでしょ? 疲れてきちゃって。それにこれとか深月ちゃんに似合うと思うんだけれど?」
わたしは派手さはないけれど実用的な、赤いヘアピンを示した。
「それじゃあ着けてみるけど……」
近くの棚の鏡に向かう彼女は少し真剣な顔で着けようとしたが諦めて、
「やってよ」
わたしに目を向けた。
「このくらい自分でできなくてどうするの?」
そう言いながらわたしは彼女の髪の左側を留めた。
「ほらできた」
彼女を鏡のほうに向かせて後ろからのぞきこむと、照れたような目と鏡越しに目が合った。
「どうかな?」
わたしは、
「似合ってるよ」
答えてから離れた。
「じゃあ、凜ちゃんもおそろいにしない?」
わたしは少しためらいながらも、着けてみて、
「似合ってる?」
訊いてみた。彼女は元から大きな目をさらに大きくしてじっとわたしを見つめると、
「似合ってる!」
そう言った笑った。
「本当にそうかな?」
わたしは自分には少し似合っていない気がして鏡を覗き込む。黒髪ロングにしているとピンは使いにくい。そうだと思いついて私は髪をまとめてお団子にした。そして元々持っている簪を刺して前髪はピンで留める。
「これなら似合うかも」
彼女は激しく首肯して、
「滅茶苦茶可愛いからそれにしようよ」
わたしは彼女とそろいのピンを買うことにした。
アクセサリー店から出ると、わたしと彼女は近くに出ていた移動販売車でクレープを買うことにした。中高生が多くたむろしている。その中をクレープを買いに進んだ。
「わたしはチョコバナナのクレープが良いかな」
「じゃあ私は苺のクレープにするから……」
「あとで一口ちょうだい、でしょ? 交換してあげるからそうしようよ」
わたしの言葉に彼女はぱあっと表情を明るくしてわたしの腕を引きながら列に並んだ。
「クレープって原価安そうだよね」
彼女はわたしにそう話しかけてくる。わたしは何でもないことのように、
「原価率は三十パーセントくらいらしいよ」
わたしは店主と目が合った気がして思わず声をひそめた。
「確かにそれくらいでないともうからないだろうしね」
わたしと彼女はあらかじめ決めていたメニューを注文して受け取ると、近くにある椅子に並んで座って、それから、
「一口どうぞ」
わたしは彼女にクレープを差し出した。彼女は嬉しそうにかじりつくと心底美味しそうに相好を崩した。クレープって太りそうだとか、お肌に悪そうだとか野暮なことは言うものじゃないなと思いながらも、何キロカリーあるんだろうと考えて運動しなきゃなと脳裏に浮かぶ。
大抵の女子高生って毎日あれだけお菓子を食べていて太らないのだろうか。わたしはお菓子を沢山食べるほうではないので疑問だった。でも、
「美味しいからついつい食べ過ぎちゃうね」
わたしはお返しとばかりに差し出された苺のクレープを一口ぱくつくとそう言った。
「明日から運動しなきゃ」
彼女の言葉に周りの他の人もピクリとしていたから心は同じなんだろう。
「明日からと言うあたり、全然明日も運動しなそうだけどね」
わたしのとげはささりそこねて、
「私は勉強するのにかなりカロリー使ってるから少しで良いんですぅ」
わたしたちは互いに笑いあって、最後の一口を放り込んだ。