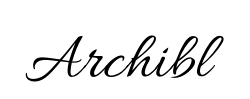わたしは奇異の視線にさらされていた。それも当然かもしれない。一般的に見れば女の子同士の恋愛なんて変かもしれない。ようやくそれも一般的になろうとしていてもまだ受け容れ難いというか自分とは異なる感覚を持つ少数を気にしないでいられるほどに普及していなかったのだ。
最初、わたしは彼が動画を拡散するのを止めたのではないかと思った。あの脅しから一週間が経ってもわたしと彼女の噂は広まっていなかったのだ。だから油断してしまった。
彼女とはあれから会っていない。もう会うこともないだろう。それかもし彼女が友人と認めてくれるのであれば、わたしは彼女に抱いた恋慕を押し殺してただの友人として接することもできる。そうであればどれだけ良かったか。救われたか。
動画を拡散した張本人は、わたしには視線を向けない。ただ見えるように笑みを浮かべている。何も言わないし何もしないがただ嗤っている。
クラスメイトがわたしを擁護することもない。当然だ。彼ら彼女らとわたしは親しくないしその上それを庇ったとなれば自分も仲間外れにされかねない。わたしは心の中でも責めることはなかった。
ただ彼だけを責めた。
彼の立場は、わたしに心惹かれてしまっていたが、告白する前にわたしが同姓とつき合っていることが判明し、フラれる前に変な人間とつき合わずに済んだ、一時的にでもわたしと話してしまった被害者。クラスメイトは彼の肩を持つ。彼はクラスの中でも人気者で、よく分からないわたしなんかとは違う良い奴だから。
この動画を拡散して、腹いせにしている屑だとは誰も気がついていない。本質を知らない。
わたしは前々から決めていたことを行動に移すことにした。わたしの好きな彼女が、無事に次の恋に行けるように、すべての元凶をわたしだと印象つけさせる。そのために、
「わたしとつき合わない?」
わたしはクラスメイトの前で言ったのだ。近くの机にいたクラスメイトを巻き込むようにして、わたしのほうをちらちらと見ていた名も知らぬクラスメイトに。
「何言ってるの?」
当然の反応にわたしは怯むことなく、
「あなた、可愛い顔してるから。好みだから。それでつき合わないかって訊いてるの」
教室の空気が凍りつき、気温が下がった気がした。
「嫌よ。気持ち悪い」
ごみを見るような目で彼女は吐き捨てる。
「弱みでも握ってれば好きにできるんだけどな」
わたしは精一杯演じて見せた。
「じゃあ、キスだけでも良いからしてくれない?」
「そんなの余計に嫌。好きでもない人に、ましてや女の子にキスだなんて」
「そっか。残念」
わたしは彼のほうをちらりと見る。彼は一瞬驚いた顔を見せたが、すぐにそれを隠してそっぽを向いた。これですべてはわたしのせいになるだろう。彼女は無理矢理、弱みを握られた哀れな人間ということになるだろう。
自分でも分かるくらいいやらしい笑みを浮かべてクラスの女子を見て、それから舌なめずりをした。彼女たちはブルりと身体を震わせた。
放課後になると既にすべての噂は置き換わり、わたしの被害者という立場になっていた深月ちゃんは息を切らしてわたしの元へとやってきた。いつものように空き教室の暑い中で、ただ筆は持たず、キャンバスもイーゼルも準備せず、外を眺めていた。
「どうして?」
彼女の言葉に、
「あなたが幸せになってくれれば良いから。わたしはわたしのために泥を被る。好きな子のために」
「わたしが先に迫ったのに……」
「でも本気じゃなかった」
「あの時は本気だった」
あの時はの言葉に胸が締めつけられた。
「わたしとはもう関わらないほうが良いから」
「でも、」
「わたしのことを無駄にするつもり? それだったら好きな子とつき合って、幸せになって、わたしに教えてよ。そのほうがよっぽど嬉しいから」
彼女はもう何も言わないで教室から出て行った。
しばらくして教室に入ってきたのは彼だった。わたしは彼に、
「部活に行きなよ。これで満足?」
力なく言った。
「自分ですべて被るなんて大したものだな」
「何の用?」
問いに答えながら教室を去って行った。
「壊れてるかなって思ったのに」