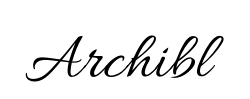第一節
遠野唯人は、目を刺すような強い光で目を覚ました。昨日の晩に、カーテンを閉め忘れたのかと思う。しかし、カーテンの隙間から漏れ出る光で、時計を見るとすでに七時を回っていて、登校完了時刻までは残り一時間しかない。唯人は憂鬱に思いながらも急いで身体を起こした。
壁には大量の英単語や歴史用語、数学の公式などが書きなぐられたノートの切れ端、ルーズリーフ、メモ帳が所狭しと画鋲、テープで張り付けられていた。
唯人は、部屋の中で唯一の安寧の地であるベッドの上掛け布団の中から這い出た。
部屋は十畳ほどで広い部類に入ることはわかっている。しかし、二メートル五十センチはある天井までそびえたっている、大量の本が詰まった書棚が一方の壁を占拠しているせいか圧迫感を感じる。ベッドから床に降りるとそこにも大量の紙やら参考書やらノートやら、時々シャープペンシルや消しゴムが落ちているから油断できない。机の上に置けば良いといつも思う。しかし、勉強のためのスペースを埋めるわけにはいかないとばかりに、机上は綺麗に保たれていた。慎重に足の踏み場を探しながら、地雷をよける兵士のように慎重に扉のほうへと歩いて行った。
部屋から廊下に出ると一階へと降りる階段が目の前に現れる。部屋の惨状とは裏腹に、自室以外の場所は綺麗だった。床は磨き上げられて廊下の窓から漏れる陽光に照らされてきらきらと反射していた。
ここまでの行動に十分掛かっていた。
唯人は、ようやくリビングルームにたどり着くと壁のハンガーにかかっている学生服を手に取り、手早く着替える。洗面所で顔を洗い、ついでに寝間着を洗濯かごに押し込んでから、帰ったら洗濯しておかないといけないと考えた。髪が短かったお陰で寝癖というほどのものはできていない。
その後で、朝食のパンを口に押し込み牛乳で流し込む。歯を磨いて、昨夜のうちに準備しておいた鞄を玄関の棚から取り出す。そして、唯人は父親が帰ってきたんだなと思った。鞄の上には今月も封筒が置いてある。中にはいつも通り十万円が入っている。
前回父親と話したのはいつだったろうか思い返す。父親とは話をしないようになっていた。
母さんが病気で死んで、それから七年が経つのか。一年で二回も顔を見ればよいほうだ。母さんが死んでから父親は人が変わったように仕事に打ち込むようになった。まだ十歳くらいの唯人をおいて海外出張などで家を空けることが多くなった。
唯人は客観的に自分の存在を俯瞰した。
母親を亡くし、父親は家を空け、金だけ与えられて生活するかわいそうな少年。これに気が付いたのは、母さんが死んでから半年も経たないうちだった。唯人は、それから自分は勉強を始めたんだ、と思う。相手にしてほしかった。自分を放っておかないでほしかった。父親にそれを言えていればもしかしたら自分は勉強をここまでしなかったかもしれない。
母さんが生きていれば、こんなことにはならなかったかもしれない。病気で死ななければ。
そこから医者になる夢を持ったのは、単純な子供としてはごく自然なことだろう。そこまで回想してから、封筒をリビングの金庫にしまう。登校完了までの残り時間は三十分程となっていた。学校までの距離を考えるとギリギリかもしれない。唯人は、運動靴を履くと玄関の鏡で自分を見つめた。自分の顔をたたいて自分に気合を入れ、玄関を開けた。
唯人は、いつもの退屈な道を駆けていた。学校の前の長大で急な、心臓破りの桜道と生徒に呼ばれている坂を駆け上がる。生徒はほとんどいない。生徒のほとんどは登校済みだろう。ギリギリに登校して万が一にでも間に合わなかったら体育教師に叱られるのは目に見えている。
この時間は車の通行が禁止されているから、道の真ん中を走ろうとも叱られることはない。校門まで後少し、山に渦巻くように走っている坂道は後少しでそこにたどり着く。
唯人はそう思って走るのを止め、歩き始めた。その時、桜の舞い散る坂道の途中、木の下に空を仰ぐ人影を見た。同じ高校の制服を着ていることはすぐに分かった。登校時間まではあと少しだというのに、分かしているのだろうか。唯人は、歩きながらその人影をもう少し詳しく見ようと思い、桜の木側を歩いた。人影に近づくとはっきりと見えた。
少女だった。長い白い髪、ほっそりとした体格、そして異常なほど白い陶器のような肌、整った顔立ち。思わず凝視していた。唯人はそれを見て、ただただ絵になると思った。
振り返る予感がして、慌てて校門へと走ったのだ。残り時間は三分。校門が閉められる前に何とか滑り込んだ。後ろを振り返っても、少女は駆けてはこなかった。
学校では見たことがない人間だった。あのような生徒がいれば噂の一つにでもなっているだろう。転校生だろうか。そう思いながらも意識は別のことに移っていた。教室までの距離はそう遠くないが始業時間までにはたどり着かねばならない。速足で移動を開始した。
第二節
家の中は静かなものだった。誰もいないのだからそれは当たり前だ。自分たち以外には誰もいないのだ。長谷川亮太はベッドで隣に眠る前田香織の方を見た。
自分の彼女の穏やかな寝顔と寝息を確認すると、服を着始めた。筋肉質の身体は健康的に日に焼けている。時計を見ると午後七時を回っていた。もうすぐ香織の両親も帰宅するだろう。公認の仲とは言え夜遅くまで二人でいるのは世間体が悪い。
長い黒髪をかき分けるようにして香織の頬を撫でた。
「起きろ、香織。俺はもう帰るぞ」
寝ぼけた眼で亮太を見つめた双眼はにへらと顔を綻ばせた。
「おはよ、亮太。明日学校だっていうのに遅くまでごめんね」
亮太は頬を撫でたまま無性に愛おしくなって首元に唇を落とした。
「全然いいんだ。俺にとって香織が全てなんだから」
「そっか、ありがと」
香織は身体を起こすと掛け布団が流れ落ちて大きな双丘が露になった。恥ずかしがる様子もなく立ち上がり下着を着けるとガウンを羽織った。髪をポニーテールに結ぶ。
「あのね、話があるの」
香織は切り出した。双眸には決意が燈っていた。
「何だ? 今度じゃ、駄目みたいだな」
「大事なことなの、私たちにとってはとっても」
「そっか」
どこか分かっていたかのような目で香織を見た亮太は先を促すようにベッドに腰を下ろし、深い溜息を吐いた。
「私たち、別れよっか」
香織の言葉には冷たい響きがあった。亮太が表情に驚きや焦りや怒りを出すことはなく、むしろ穏やかに笑みを浮かべていた。
「そっか」
短く言った。
「どうしてとか、嫌だよとか言わないのね」
「もちろんそう思ってる。でも、香織が意味もなくそんなことを言う人間じゃないことを俺は知ってるから、何かしら意味があって一緒にいないほうが良いと思ったんだろうから従うよ」
「私も別れたくなんてないよ。大好きだから。でも、だからこそ距離を取るべきだと思ったんだよ。しばらくして、もう一回復縁したいと思っているしその時亮太もそう思っていてくれたら嬉しいよ。でも今は一度きちんと距離を取って互いの存在が何なのかって考えるべきだと思う」
亮太は知っていたのだ。自分たちは互いに依存している、ただ愛し合っているだけではない気持ちの悪い関係だということを。それで、そのことを解消したいと互いに思っていたことを知っていたのだ。だから今回のことに賛成した。そして元恋人に訊ねた。
「別れたこときちんと公言した方が良いか?」
「した方が良いとは思うよ。その方がケジメになる。でも、私たちを結んでくれた唯人には知られたら心配されると思うし、浩志と春香も思うところはあると思うんだ。だから黙っていちゃ駄目かな。別れている間に誰かに盗られるのも言い寄られるのも嫌だから表面上は今まで通りにしたいの」
「別れようって言ったり、復縁しようって言ったり、公言しないでいつも通りって言ったり、色々言うんだな」
笑いながら亮太は言った。香織も笑い返しながら、
「だって、お互いに本当の意味で手放す気はないでしょ?」
「……別れた今でも俺の全ては香織のためのものだから」
言い淀んだ。今は彼氏彼女でもない別れた相手に重い言葉を吐いていると自覚していたからだ。亮太はそれからベッドの脇に立った。部屋の隅に置いてるごみ箱からティッシュがはみ出しているのが無性に目に付いた。窓を開けて籠った空気を入れ替えるようにしてから部屋の扉に手を掛けた。
「温かくして寝ろよ」
「うん、亮太もね」
もう振り返らずに家から出た。
第三節
「次の章なんだけど、どうする?」
「そうだねー。脚本が微妙に気に入らないんだけどー」
南浩志と安藤春香は、パソコンの画面を見ながら身を寄せ合っていた。画面には文字が綴られたメモが表示され、その続きに第五章の文字が躍っていた。浩志はプログラムを書いて春香はイラストを描く。これが五年間の二人の関係だった。脚本は外部に依頼しいて、それを基にノベルゲームを作成していた。今回もそうだった。
「前回の人は引き受けてくれなかったねー」
春香はすぐ隣にいる浩志を見もせずに言った。
「修正をお願いしすぎたからね。しかも、期限ぎりぎりまで。そりゃあ、嫌にもなるだろ? 自分で書ければ良いんだけれど、不評だったから」
「私は良いと思うけどなー。好きだったよー、あの話」
浩志はドキリとして隣を見た。好きだったのはゲームの脚本であって自分ではないんだろうなと思いながらも、春香は自分の気持ちに気が付いているのだろうかと思った。
自分たちは幼馴染で距離も近い。五人いる幼馴染のうち、亮太と香織は付き合っているし、唯人は興味がないだろう。そして自分と春香はどうだろうか。昔、春香は唯人のことが好きだと言っていた。自分では駄目だろうか。それとも八年も前のことだから変わっているのだろうか。その考えがぐるぐると頭を巡る。
「僕も……僕もはるちゃんの絵、好きだよ。あの時の不評だったけど」
「そっかー。ありがとー。でも、今だったら絵も上手く書けるようになったでしょー?」
「プロになってるんだから上手いって皆が認めてるんじゃないか? 実際、全然違うしさ、あの時と」
春香はむすっとした顔で隣の浩志の足を抓った。童顔の彼女は身体つきも相まって拗ねているととても子供っぽく見える。
「別に皆なんてどうでも良いのー。こう君が上手いって褒めてくれれば私は満足なんだからー。だって最初の絵を褒めてくれてなかったらプロになんてなれなかったし、ただの絵が趣味の高校生になってたよー」
「そうだな。本格的にプログラマとして活動し始めたのって、俺にとってははるちゃんが最初のしょうもないゲームを褒めてくれて自信がついたからだから、僕もはるちゃんさえ褒めてくれれば良い」
笑いかける浩志に春香は再びパソコンの画面に向かった。
「お揃いだねー」
ほんのりと頬を朱く染めていた気がした。画面には桜の絵が映っていた。それを見上げるようにしている白い天使が痛いほどの輝きと存在感を示していた。
どうでもいいか。春香がその気になってくれるまでは自分からは行かないと心に決めていた浩志は再び五章の構想へと意識を戻していた。
「そもそもこの脚本って、最初は良いんだけど後になるにつれて失速感が否めないよな」
「解るー。このシーンって必要ないじゃんとか、このシーン入れてよとか思っちゃうー」
「最後には勝手に改変して良いからとか言って逃げられたしさ。まあ、脚本自体は買い切りだから良いんだけどさ」
「ホームページで公開しても原作に名前書くだけにして後は知らん顔しとこうよー。ほとんど原作の部分残ってないけどさー」
「そうだな。それが良いかもしれない」
二人で笑いあって、一緒にいて、他の人よりも距離も時間も近くて、これからもこんな風にいられれば良いと思った。浩志はマウスとキーボードを操る。イラストの追加を春香に頼みながら流れを説明する。
春香はすぐさまペンタブレットで絵を描き始める。幸せな時間だった。いつまでも続けばこれはこれで幸せなのだろうなと思いながら。