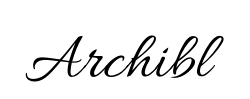第一節
「今日もぎりぎりだったな、唯人さんや」
教室に入ると唯人は声をかけられた。
「別に遅れてないんだからいいだろうが。今日もって言ったけどな、昨日は二十分前には着いてたけどな。そしてお前にとやかく言われることはないだろ?」
唯人は声をかけた幼馴染、長谷川亮太に軽口を返す。
「間に合ってるから別に責めてないけどな」
唯人はそれもそうだと思いながら自分の席に向かった。そして隣にいる亮太にだけ聞こえる声で、ぼそりと呟いた。
「今日もか」
面倒そうな声で言うしかなかった。
「今日もだよ。ずいぶんおモテになることじゃないですか。ちなみに俺が来た今から三十分前にはすでにいたよ」
唯人の机の周りではクラスメイトの女子たちが歓談に励んでいた。ホームルームももうすぐだというのに、自分の席に座りもしないで唯人が来てどいてほしいと話しかけるのを待っている。
唯人は自分の容姿がそれなりに優れていることに自覚はあった。そして成績優秀、スポーツもできる。その上彼女もいないときた。自分が演じている、優等生の遠野唯人が優良株だと分かっていた。八方美人で、そもそも深く人と関わらないからこそ映し出せる偶像。
幼馴染だから亮太の前では素の自分を隠していないが、それこそ亮太のほかに数人しか知らないことだった。そもそも引っ込み思案だった自分の友人といえるのは数人しかいないわけだが。体格もよく、顔も悪くない亮太もモテるらしいが、中学の時からの彼女がいるのであからさまに狙われはしない。自分には到底できないことだった。
「すみませんが、席に座りたいので空けてもらってもいいですか? もうすぐホームルームですし、席に戻ったほうが良いのではないですか?」
唯人はほれぼれするぐらいの柔らかい笑みを浮かべてクラスメイトに呼び掛けた。
「ごめんなさい。つい夢中になってしまって、時間を忘れてしまいました」
嘘だ、と唯人は思った。教室に入ってきた時から、今か今かと待っていたくせによくもぬけぬけと。チラチラ見ていたのは知ってるんだぞ、面倒だからやめろよとそう言いたくなるのを抑えて、完璧な笑顔で対応した。亮太は短い黒髪をかきあげながら素知らぬ顔ですでに席についていた。
「ところで遠野さん、少々お時間ありますか? 今日の放課後にみんなでカラオケに行く予定があるんですけど、よろしかったら一緒にどうですか?」
目が怖い。唯人は、面倒に思いながらもどう断ってやろうかと考える。結構な頻度であることだ。二度とかかわらないでくれというのが本心だが、そんなことを言っても聞かないだろうし、これまで積み上げてきた評価にかかわる。
三秒ほどで考えを巡らせると、いつも通り無難に断ることにする。
「大変申し訳ないのですけれど、今日も予定がありまして。残念ですがご一緒することはできないのですよ」
「そうですか、それは残念です。忙しいのが分かっているので、断られる前提でお誘いしてますけれど、やっぱり残念です。次にお暇ができたらぜひ私たちと交流を深めてくださると嬉しいです。ちなみに次の予定は……」
そこで担任教師の山下誠二が入ってくるのを唯人は見る。少しこわもての男性教師であるが根は優しい、生徒に人気の教師だった。
ようやく解放された。そう思いながら、クラスメイトを見やる。顔にうっすら忌々しげな表情が浮かんでいるのを見逃しはしなかった。しかし、一瞬ののちにはそれは掻き消える。見事な笑顔を浮かべてから、
「では、また機会がありましたら」
席に戻るのを見送った。唯人はようやく猛攻を退け、自分のカバンの中身を机にしまう。教科書は基本的に置いて帰らないし、辞書は電子辞書を使っている。ノートは最低限の冊数だし、体操服もきちんと持ち運んでいる。以前、置きっぱなしにしたほうが楽だと思ってそのままにしておいたら、中に手紙が挟まっていたり、もしくは自分のものから新品に変えられていたりすることもあった。
なんて面倒なのだろう、などと思いながらも唯人は筆箱からシャープペンシルを取り出してノートを準備する。担任の山下の話に耳を傾けると、春休みの課題から出題される、今季初めての試験の範囲が発表される。山下はクラスのブーイングには動じずに紙を張っていく。
国語は大丈夫そうだ。英語はやばいかも。などという会話も聞こえてくる。
唯人にとってはただの作業でしかなかった。どうせ今回も一位だ。中間試験や期末試験でさえも真剣に勉強している生徒は半数ほどだろう。この試験なんて言わずもがなだ。唯人は窓際に椅子を少し寄せて、外を見た。
しばらくするとわらわらと集団が校庭に吐き出されて行くのが見えた。一限目を知らせるチャイムが鳴った。どうでも良い授業が始まったと思った。
休み明けのテストが終わって、体力測定が終わった。テストの結果は二位だった。三点のミス。国語、英語、数学、理科、社会と五教科の総合で順位が決まる。理系と文系では理系が理科に科目、文系が社会に科目と受けたテストに差はあるが、どちらでも点数的にはトップになるはずだった。今までは少なくともそうだった。しかし、現実は違った。
満点が一人。一位の座をかすめ取って行ったのだ。努力が足りなかったか、と思う。一位でなければ意味がないのに。昼ご飯を食べ終わって、ぼうっとしていると唯人は亮太に話しかけられた。
「学年二位、おめでとうございます。唯人様」
「お前、嫌な奴だな。俺が一位じゃないのがそんなに嬉しいのか?」
目を細めながら訊いた。
「いや、別にどうでもいい。珍しいこともあったもんだなっと思っただけだ。俺はいつも通り十五位前後だったし、他人の点数なんかに興味ないし」
亮太は、おちょくりに来たのかどうなのか分からないようなことを言った。確かにこいつは他人の結果に興味を持つような奴じゃないなと思った。
「悔しいか?」
ふと真剣な表情になった亮太が問いかけた。
「悔しくないと言えば嘘になるな。そりゃあ、どうせ今回も一位だと慢心していた俺も悪かったさ。だって満点がいるなんて思わないじゃないか」
「自称進学校のうちは、この時期から勉強ガチ勢なんてほとんどいないからな」
亮太は訳知り顔でうなずく。その表情に無性に苛立った。
「誰が一位か知ってるか?」
亮太が唯人に問いかけた。
「名前を廊下に貼るなんて言う悪習慣を続ける学校だからな。そりゃあ誰が一位かなんてすぐにわかるだろう」
悪習慣だ。個人情報の保護が厳格化されている中で廊下に成績と名前を張り出すなんて。だが、他人に成績を見られるから恥ずかしくないようにそこそこの勉強はしておこうという風潮を作り出すことで進学率は悪くはない。そう考えるとそこまで悪いものではないのかもしれない。もっともそれは唯人が成績優秀者だから言えることで、あまり勉強に自信がない生徒にとってはただの災難でしかないのだが。
「刑部梨乃だって」
「一位の名前だろ?」
亮太の言葉に唯人は問う。見たことがない名前だ、少なくとも入学してから上位にそんな名前はなかったはずだ。もしかしたらものすごい努力で春休み明けのテストだけ頑張ったのかもしれない。そう結論付けようとした唯人に声がかけられた。
「ちなみに、転校生だそうだ。なんでも天才少女らしい。全国テストで常に一位だとか。
お前が全国テストで一位を取れないのは、どうやらあの少女がいるかららしいな」
「そんなことよく知ってたな」
「そりゃあ、学校中で噂になってるぜ、満点が現れたって。いくら課題から出るって言っても満点はなかなかいないじゃないか。しかも転校生で、春休みの課題は一切やっていないときたもんだ。どんな奴か気になるじゃないか」
確かに、と唯人は思う。そんなすごい奴なら噂になるのもうなずける。
「なるほどな」
そう答えながら、自分の敗因は天才じゃなくて凡才だったからなんだと悟る。いくら努力しても埋まらない差はあるもんだ、と。
「おまけにな、この間の体力測定の結果でも二年女子のすべての科目で一位だったらしいぞ。
勉強もできて運動もできる。すごいよな」
「そうだな」
「顔もいいらしいぞ、現世に降臨した女神だとか言ってたな、長い白髪に菫色の目、ほっそりとした体格。完全体なんだろうな」
「そう思うならお前が付き合えば言いじゃないか。告白してみろよ。案外成功するかも」
亮太は唯人にかぶりを振った。
「冗談でも言っちゃいけないぜ。俺には香織という人がいるんだからな。あいつほどの女はいないぜ。気立ても顔もいいし、俺に付き合ってくれた優しい子だぞ。まだまだあるんだがな……」
惚気始めた亮太の様子に、もう付き合っていられないとばかりに口をふさぐ。
「お前の香織ちゃんのいいところは、三百回は聞かされてる。その上に会うたびにそれに追加していろいろ言うだろ? もう魅力は聞きつくしたよ」
意外そうな顔をした亮太は、
「お前、聞き流してると思ったけどちゃんと聞いてたんだな。毎回本から顔も上げないから聞いてないと思って何回も話してたけど」
「マルチタスクには自信があるもんでな」
唯人は、鼻を鳴らした。別に話を聞くだけなら問題はないのだ。それに亮太は相槌を求めてこないから楽なもんだ。
「今度からは要点に絞って話すことにする」
亮太のいい笑顔にげんなりしつつも、返す。
「別に話してくれなくていいんだぞ。香織が可哀想じゃないか。本人の関与しないところでお前の評価に尾ひれがついて噂になるから大変そうだぞ。そして一つだけ言っておく、香織は俺と幼馴染でもあるし、お前との付き合うきっかけを与えたのは、まぎれもなくこの俺だ。悩んでたお前の背中を押したのは俺だ。別に教えてもらわなくても、若干付き合いの長い俺のほうがいろいろ知ってるし」
唯人は、少々嫌がらせの意味も込めてお前よりよく知ってるといった。実際付き合いは長いのだから嘘ではないが。
「そうだよな。唯人のおかげで付き合えたんだもんな。感謝はしているが、一つ気に入らないところがある」
藪蛇だったかと唯人は後悔する。余計なことを言っていなければ、さっきので終わっていたのにな、と。俺のほうが知っているなんどと口に出したばかりに……。
「お前の知らない香織を俺はたくさん知ってるんだぜ、唯人。エッチの時の顔とか知らないだろう。普段も可愛いがな、エッチの時の香織は最高だった! 長い黒髪が乱れて……」
話始める亮太の口をふさぐがもう時すでに遅し。この話はしばらくして香織の耳に入るだろう。そして問い詰められた挙句、一週間ほど口もきいてくれないだろうな。
そう思った唯人は、
「もうその辺にしとけ。これ以上その話をしたら殺されるぞ。初めてのエッチの話を次の日、俺に話しているのを聞かれて、香織にキレられたの覚えてないのか。物理的に記憶を消そうとするほどテンパって、俺にも災難が降り注いだのは忘れてないだろうな? あんな思いはもうこりごりだ。それに幼馴染同士とは言え他の人間にそんな話をするのは不誠実だろう」
亮太はようやく話をやめることにしたらしい。顔を青くして震えていた。
「やべえ、ジャーマンスープレックスされるかもしれね。どこで覚えたんだか知らねえけど、すごい上手く決めるんだ、あの技。殺されかけたらかくまってくれ」
「やだよ。かばったりなんかしたら俺がどうなるか分かったもんじゃない。前回はモンキーレンチ片手に、いい笑顔で『ゆいくーん』って迫られて死を覚悟したんだからな。あいつ、どんどん物理特化してきやがる。次は釘バットでも引きずってきそうだ」
ドン引きである。
「何はともあれ……」
亮太は話を強引に変えようとして、先にクラスメイトに、
「今の話は、俺の命のためにご内密に」
絶対無理だろうな。五分後にはバレてる。唯人は憐みの目で見ながらも、クラス全員の記憶を消そうとしませんように。そう祈るしかなかった。
「ともあれ、容姿端麗、成績優秀。そんな彼女には大きな欠点があるらしい」
唯人はふーんと相槌を返す。多分、以前に見かけた桜の下の子だろう。そう確信する。白くて長い髪は印象的だった。確かに美人さんだったなと思う。
「どんな欠点だ? カンニングなのかカンニングか?」
「どうしても悔しいらしいな。カンニングで満点取れるわけがなかろう? 全国模試なんてさらに厳しいだろうに」
唯人は舌打ちをした。どうせならそう言う欠点のほうがよかった、と思いながら。
「それで。結局どんな欠点なんだ? カンニングじゃないとして、体力測定はドーピングか?」
「どうしてお前は不正につなげたがる? 第一体力測定は男女別だろうに」
呆れた顔で亮太はため息をついた。それから、
「ものすごく、クールなんだとさ」
「クール?」
「ありていに言えば、不愛想だとよ。転校初日には、周りに女子も男子もたくさん集まったらしい。もちろんそれは、勉強とか運動とかする前だから容姿でだろうな。自分のグループに引き込んで、学校内の立場を向上させようという考えだろうな。大して自分はすごくないくせに、人の威を借りようとは低俗な人間じゃあないか。でも仕方ないのかもしれない。だって人間だもの」
わけの分からないボケなのか自説なのかわからないような意見を盛り込みながら話し続ける亮太に白い眼を向ける。
「誰にもなびかなかったそうだ。なびかないというよりは、完全に無視を決め込んでたらしい。話もしなかったそうだ。最後に口を開いて何を言うかと思えば、『うるさい。失せろ』だそうだ。それで次の日には誰も話しかけなくなったらしい」
「ふーん。まあ、人それぞれじゃない。特に人とのかかわりあいなんてないほうがいいと思う人間もいるだろうし。事実として俺は、亮太とか香織とか、他数人の幼馴染としかまともな会話しないだろう? 本音で話すのなんて五人くらいいれば十分だろ」
呆れた顔をしながらも亮太は言う。
「お前は良いじゃないか、唯人。無視はしないだろ、お前は。八方美人を演じてるだけあって人望も厚いじゃないか」
唯人は声を潜めた。
「まあ、そりゃそうだ。人望なんてあって困るものじゃない。しかも利用できるときたもんだ。大事にしないわけがなかろう?」
「お前の本性知ったらがっかりする人多いだろうな。俺たち幼馴染以外で知ってるのなんか、担任の山下くらいだろう。察してそうなだけで、知ってるかどうかと問われれば怪しいかもしれんが。他の先生は絶対騙されてるぜ。あとは保険医の亜美ちゃんくらいじゃない。新卒採用の人だけど、俺らが話してるところに通りかかってばれちゃったじゃないか。言いふらしてはなさそうだけど、時々話に混ざってくるじゃないか。お前のさぼり、もとい、しょうもない授業の時の自習のために保健室へ行ってきます作戦に知りながらも協力してくれるいい先生じゃないか」
唯人は、それはいい先生なのだろうかと疑問を呈しながらも、自分にとって都合のいい先生と解釈しておくことで納得する。
「幸い、亜美ちゃんのごまかしで俺は頭痛もちで、一時間寝れば治ることになってるし、まさか真面目な優等生がサボりと思うまい?」
「ほんと、ダメな奴だな。ダメというか悪いというか。そのうちバレるぞ、きっと。その時には亜美ちゃんも怒られるんだからバレるなよ。かわいそうだし、きっとお前を無理やり誘ってるとか、ろくな噂になりそうにもない」
「わかってるよ」
唯人は亮太に肩をすくめて見せた。
「話は戻るけどな、唯人。無愛想でも顔はいいから付き合いたいって男もたくさんいるわけ。照れ隠しだ、なんて言ってるやつもいたけどそんなことはないだろうな。実際、何人も振られてるしな。というか、告白をスルーされてるって感じか。手紙を出してもその場で捨てられるし、放課後校庭で待ってるとか言ってもそのまま帰っちゃうし」
「俺はちゃんと断ってるぞ。お前らに教えたメアド、二つあったろ。一つはちゃんと俺が読むやつで、片方の人に教えてもいいって言ったほうは、自動返信プログラムが動いてる。要約した内容が入って、選択肢を選んで返信する。まあ、まだ試作段階だから要約がめちゃくちゃな時もあるけどな。選択肢は、お断りとまともな、例えば委員会とクラスの仕事との時はメールボックスに転送とかだな。毎回人工知能にお断りの文面考えさせてるんだぜ。俺が作ったんじゃなくて浩志に作らせたんだがな。おやつ一か月分で」
「お前なあ。幼馴染とはいえ無茶苦茶な扱いしすぎだろう。どうせ十円そこらのお菓子三十個とかだろ? パソコンからデータ抜き取られても知らないぞ」
亮太は呆れた顔で、スマホを見る。
「今度腹立ったらそのことばらしてやる。それはともかくとしてだな、それで一番傑作なのはサッカー部の部長が振られた時だな。あの人、自分が振られるのを微塵も予想してなかったらしい。あの人も結構モテるだろ? それで自信過剰になってたってわけさ。他の人がことごとくフラれてるのに自分だけはそうじゃないって信じてたみたいだ」
笑いをこらえた様子の亮太は、さらに悪い顔をして、
「それまで付き合ってた彼女のことをフッたらしいんだよ。『俺は真実の愛を見つけた、だから君とはもう付き合えない』とかってさ。それで彼女も仕方ないって引き下がったらしいんだ。自分よりいい人を見つけたのならしょうがないってさ。いい子じゃないか。それで告白して、刑部は見もしなかったらしいけど、しつこく何度も告白したらしい。ついに振り向いたかと思うと、一日待って欲しいってさ。期待するよな、普通。ようやく振り向いたって、クラス中に自慢したらしいぜ。『あの美しい子は俺のもんだ』ってさ。それで次の日、学校から入ると建物まで通路があるだろ? あそこで待ち構えてたらしいんだ。それで、『いままでいた彼女さんはどうしたの』って聞いたらしい。そりゃあ、フラれた彼女のことは噂になってたよ、刑部のことを自分のだって言いふらしてたのとセットでさ。女子からは最低だとかなんだとか言われてたけど、男のほうはうらやましいって。『真実の愛のために分かれました。そもそもあいつは飾りですよ飾り。男にとって女は最高のアクセサリーなんですよ。それで返事は決まったってことですよね』もう、最高潮。自分の彼女になることを疑いもせず、期待に満ちた目で見ながら、返事を待ったんだってさ」
もう笑いをこらえられないといった風に表情を崩す。唯人は実にいい笑顔をしながら、
「それでフラれたわけだ?」
そう言った。
「ああ、良いところなのに結論だけ持ってくなよ。そこは俺がもっと低音で、イケメンボイスでささやくように、『フラれたそうだ』とか言う予定だったのに。まあ、そうだな。フラれたんだ。こっぴどくな。『そもそも興味もないし、迷惑だから二度と付きまとわれないように大勢の前で言わせてもらうけど、あなたに興味を持つくらいならプラナリアを一日観察したほうが興味深そうだ』ってさ。そりゃあ周りは笑いの渦に飲み込まれて、部長は顔真っ赤にして『別にお前なんか最初からタイプじゃなかった。俺には奈那子がいるからな』って反撃しようとしたらしい。奈那子っていうのは部長が真実の愛のためにフッた元カノのことな。そしたら奈那子さんは、最初から聞いてたらしい。千年の恋も冷めるってもんだ。『私はあなたのアクセサリーじゃない。この下種野郎が!』って、口汚く罵った。普段の奈那子さんは温厚でどっちかって言うとおっとり系の女子なわけだ。そのギャップがすごかった。前から別れよう思ってたらしいんだがな。その場で奈那子さんは、密かに逢瀬を重ねてたらしい、部長とは真逆の地味な男子に告白した。今まで隠れて浮気していたらしいんだ。それで成功して付き合うことになって最後に、『あなたと付き合ったのは人生最大の汚点だった』って言って去っていった。自分が所有していたと思ってた女に浮気されてて、その上フッたつもりがフラれたなんてことは、ギャグマンガの一コマかと思うほどの転落ぶりだったぜ。ありゃあ最高だった。周りからも白い目で見られてたし、もう再起不能だろうな。少なくともこの学校では」
唯人と亮太は顔を見合わせて笑った。声を潜めていたから内容は周りに聞かれていないだろうが、あまり声を上げない唯人が爆笑していることで教室内から注目を集めた。二人は慌てて咳払いをする。亮太は、それに続けて話始める。
「そこで終わりじゃないんだよな、この話。刑部はその話を機に、変人だって噂も広がることになるんだから」
「変人? 確かに、変人だろうけど広まるほどか? 確かに全然話しかけても無視とかは変人だけど、言うほどじゃないだろう?」
亮太は立てた人差し指を左右に振る
「そのあと問いかけたらしいんだ。なぜあなたは生きているのかってね。そして周りのギャラリーにもなぜ人間は生きているのかって問いかけて、誰も答えないと分かった途端、唖然とする人々を置いてすたすた歩き去っていった。次話しかけると、『なんで生きているのか結論が出たから話しかけてきたのか?』って問われるらしい。一瞬でその場にいた人の顔を覚えていたらしくて、その場にいなかった人が話しかけても無視。そして陰でこう呼ばれるようになった。『超弩級変人』ってさ。超弩級って戦艦かってな。ここまでの伝説、とてもじゃないけど転校してきてから一か月で築けるものじゃないだろ? すごいよな。興味持ったか?」
唯人が人にあまり興味がないことを亮太は知っていた。だからこそ何か面白い話題で興味を惹こうと思ったのだろう。唯人はそう結論づけた。
「面白かった。大変言い話を聞けた。けどな、ただの変人に対する興味はゼロだ。宇宙人とかミュータントならまだしも、人間じゃないか。人間はお前たちと話すだけで十分だ。わざわざそいつに話しかけに行きたくはないな」
亮太は少しがっかりしたような顔をして、
「お前、ぶれないな。人に興味なさすぎだろ」
そう言うと時計をちらりと見た。時計は昼休み終了一分前を指していた。
「授業始まるぞ。席に戻れよ。あと、面白いは話をありがとう」
亮太を見送ると、ちらりと教室を見回した。先ほどの爆笑で注目されていたらしい。いつもより多い視線に少し辟易した。
授業が全て終わり、放課後になると香織が教室に飛び込んできたのが見えた。唯人は自分がまきこまれないようにそっと机の下に隠れた。しかし、香織にはお見通しらしい。机のほ全てづいてくると、先に確保した亮太の腕を握りしめながら言った。
「ゆいくーん。今から時間あるかな。あるよね。ないわけないね」
ものすごくいい笑顔に恐れおののきながら唯人は、
「これからものすごく大事な用があるんだ。それはもう、ものすごく」
必死になって、涙目の亮太に巻き込まれないように言い訳をする。
「別にね、香織の話に付き合うのが嫌ってわけじゃないよ。でも、ね。用があるんだ。仕方ないよな。うん、仕方ない。それじゃあ、また」
足早に去ろうとする唯人の首根っこを使えると耳元で、
「じゃあ今日、泊めてもらいに行くね。亮太連れて。それで一晩中問い詰められたくなかったら今すぐ来なさい」
「分かりました。お供させていただきます」
唯人はこう答えるしかなかった。今でなければ後が怖そうだったからだ。きっと殺されるぞ。そう思いながら、余計なことを言った張本人は仲間ができたとばかりに若干嬉しそうに、そしてこれから所業を思って少しげんなりしてこちらを見ていた
唯人はこう言う時の香織には絶対に逆らわないと決めていた。周りでは香織のことを唯一、唯人がかなわない相手として認識されていた。優等生でも、モテていても、幼馴染の女の子にはかなわないことは認識されていた。周りもこの時の香織には、イケメン二人を連れてうらやましいとか、ずるいとか思うことはなかった。
これからの所業を考えると怖くて仕方なかったのだ。唯人はそう聞いた。以前、この状態の香織にうっかり触れてやけどした生徒がいるのだ。それはもう酷い火傷をしたらしい。どこからの情報か知らないが、裏での評判や悪事、彼女のほかに浮気相手が三人いる、どこ高校のだれだれだと、すべて大声でばらされたのだ。この状態のことを生徒たちは『触らぬ神に祟りなし』と結論付けていた。
ようやくお話、もとい尋問もしくは拷問が終わったころには、すでにあたりも暗くなりかけていた。学校内に生徒はほとんどおらず、すっかり閑散としていた。部活動も新入生と行うために少し時間が短縮されていた。奇妙な風潮だが、一年生の体力が受験期からの移行で戻りきっていないからという理由だそうだ。二年生と三年生は家で自主トレーニングに励むことになる。
唯人は、部活動には入っていなかったが同好会を勝手に名乗っていた。放課後に唯人にまとわりつく勧誘をシャットアウトするためだった。幼馴染五人で運よくこの高校に進学していたために唯人や亮太、香織、安藤春香、南浩志で結成したその名も『幼馴染同好会』。勝手に名乗っているだけだし、皆適当に名乗るだけで好き勝手しているし、活動内容や活動日は適当だった。入学当初からモテていた唯人と亮太のほかに、界隈では名の知れた元ピアニストの香織、天才的なプログラマーの浩志やイラストレーターの春香がいるからと参加したいという人間が続出した。しかしながら、参加の条件に十年以上全員と関わりのあるお泊り会もしたことがある幼馴染という無茶苦茶な基準でバッサリ切っていた。今ではこの活動は休みに遊びに行くくらいしかしていないからこの閑散とした学校が珍しかった。
亮太と香織は、二度と言わない、次似たことがあったらジャーマンスープレックス十回という条件のもと仲直りしていた。二人で帰るからと解放された唯人は、聞くだけでも止めなかったら同罪という謎の理由で、次はないと言われ釈放された。玄関に移動すると靴を履く。学校指定の通学靴は、革靴もどき、つまり革靴に見える運動靴だった。それならば普通の運動靴で登校を許可してくれれば楽なのに、と唯人は思いながら玄関を出る。
この高校に通う生徒並びに教師は毎朝登らねばならない坂にはうんざりしていた。どう考えてもきつすぎる傾斜を、自転車で登りきる運動部の生徒を見て感心している。教師は歩きか自動車のことが多いので移動はそこまで気にしていないだろうが、朝の挨拶週間などという謎の催し物のせいで月初めは等間隔に生徒会と風紀委員会、そして生徒指導部の教師は坂に並んで延々と挨拶させられる。参加したことがない唯人は、かわいそうにとしか思ったことがないが当事者にとってはたまったものではないだろう。その地獄の坂も下るのは楽勝だ。
帰り道の坂には何もないため生徒の歩みは早く、なんと平地の学校に比べて、登校時間は長いが下校時間は短いという結果が出ている。数年前に面白半分で登山部が調べた結果らしい。その調べ通り坂道には生徒はほとんどいない。
そう言えば、今日の話題に出た刑部らしき人を見かけたのはこの先のカーブを進んだ先だったと思い出す。あの時はただただ絵になると思っただけだったが、変人奇人の類だったと分かったとたん余計に関わりたくない。碌なことにならないだろう。しかし、唯人の願いとは裏腹にその先に、先日見たそのままの姿で上を見ていた。あの日は天気が良かったから空を見ていたのかと思っていたが、どうやら桜を見ているようだと思う。暗くなっても見られるようにという生徒会の伝統行事と暗くなっても道が明るくて見やすいという実益的な理由から、桜の周辺だけはうすぼんやりと光が当てられていた。
本当に意味はあるのかという声も上がる中、二十数年前からライトアップを行っているらしい。とにかく、刑部らしき人影には目もくれず横を通り過ぎようとしたその時だった。振り向かないままで刑部は、唯人に声を掛けてきた。
「なぜ人は生きるのだと思う?」
鈴の転がるような綺麗な声なだけあって、唯人の脳裏にその問いはこびりついた。通り過ぎようとしたがそれは不可能なことだった。美しい天才少女からの問いとして、哲学的な答えを望んでいるのかと思った。唯人が目を向けるとすでに少女は桜から目を離して、唯人の問いに耳を澄ませていた。ここで何も答えられなくても責められはしまい。突然の問いにまごつくに決まっている。しかし、少女の視線からは切実なものを感じた。生きている理由を知りたいといったような別に哲学的でない答えを探しているのかと思った。
「そんなこと……」
唯人は自分でも珍しくすんなり話しかけた。
「そんなこと知らないですよ。個人個人で生きる意味も目的も違うでしょうし、第一問うようなことでもないでしょう。ただ、個人的な見解を述べると……」
少女は促すように首肯する。
「個人的な意見を述べると、人間が生まれたからではないですかね。生を受けたうえで生を強制されている。なまじ理性があるがゆえに、人間は死への恐怖をもっています。それゆえ自刎しようとしてもたいていは怖くてできないでしょう。だから嫌々生きているのでしょうね。どんなに苦しくとも、例えば学校生活が苦痛であろうとも会社が嫌であろうともそこに通い続けて、日本人が真面目ゆえにそれらは社会的に強制されているようなものです。生きたくても生きられない人間がいるのだから命を大切になどと言われますけれど、結局その生きられなかっ真面目は自らの意思とは関係なくあらゆる感情から解放されたのでしょう。死にたくても死ねない人間は、嫌々感情に縛られ、社会に縛られ、生に縛られて嫌々生きているのです。個人的には、生かされているから生きるのだと答えておきましょう」
刑部は、すっと目を細めると、
「なるほど」
何度も反芻させるように、嫌々ね、とつぶやいた。
「面白い意見が聞けて良かった。私の名前は刑部梨乃、二年三組だ」
面倒だから答えたくないと思いつつも、不思議と人から言葉を引き出す魔法があるのか、刑部の声に答えていた。
「私は遠野唯人、二年一組です」
面白そうに刑部は笑うと、最後に一言残した。
「君の話し方は違和感がありすぎだ。演技はやめろ、気持ち悪くて仕方がない」
ドキリとした。唯人はどこでバレたのだろうか、なんて考えながら刑部を見やる。
「最初からだ」
不意打ちで、しかも見抜いたかのように言った。
「最初から違和感だらけだ。よくもまあそれだけ演技してられるものだ。どうせ人当たりが言いふりをしているだろう。私の前では結構だ。適当にしてくれ」
「バレてたんじゃ意味ないな。今まで見抜かれたことなんて初見ではないのに」
「私は人を見る目には少々自信があるし、知恵も回るつもりでいるから簡単に騙せると思わないことだ」
鼻を鳴らされた。刑部はそのまま歩き去って行った。謎の笑みを残して。
第二節
美しい旋律が耳に入る。幻想曲風ソナタ第十四番。月光ソナタとして親しまれているルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのピアノ曲である。これが聞こえてきていた。
生徒がいなくなった音楽室で香織が弾いていた。かつては世界的に神童とまで言われたピアノ奏者が一つのグランドピアノでアレンジを加えながら何度も弾いていた。
無心になりたい時に弾くのがこの月光ソナタだったなと香織は思った。何度も何度も弾くが正解が見えない。どの弾き方が今の私が求めているのものなのだろうか。短調なのか長調なのか楽譜に忠実なのかそれともおもいきり自由なのか。分からなくなっていた。
月光は校庭に漏れ出て、廊下に漏れ出て、当然隣の音楽準備室に漏れているのは分かっていた。音楽室の扉が開くと音楽教師が入ってきた。
「素晴らしいわ。独創的なものもあれば忠実なのもある。先生は良いと思うよ、解釈はいくつもあって」
「聞いていたんですね」
もちろん承知していた。
「隣の部屋にいれば聞こえてくるものよ。それに音楽室の使用許可を出したのは私なんだから聞こうと思えば聞けるものよ」
「そうでしょうね」
「でも、旋律に迷いが見える。心の中の悩みが現れるものね。いくら元天才ピアニストとはいえ全てを覆い隠しておくのは無理なのね」
香織は鍵盤から手を下すと立ち上がって伸びをした。もうすぐ消えかかる夕陽を眺めた。
「私、分からないんですよ。どの曲が一番聞きたいか、弾きたいか。自分の心にあった曲を演奏して落ち着こうと思ったんですけど、どれが一番か分からないんです。悩むときっと駄目になる。今まで積み重ねたものが」
「そうでもないんじゃない? 悩んでこそより昇華されるものだと思うわ。それにまだ若いから悩むのが仕事みたいなものよ」
香織は自分と亮太の関係性を悩みながらピアノを弾いていた。そしてどうしても結果が出ないでいた。一度自分から分かれて距離を置こうと思った。それは正しいことだろう。しかしながら、自分は耐えられたとしても亮太が耐えられるだろうか。
「私は駄目な人間ですよ」
呟くように零した。
「駄目じゃない人間なんていないんじゃない?」
「そうかもしれませんね」
亮太に依存されているのを分かってそれが気持ちよくて関係を続けて、自分自身は好きだとは思ってはいるけれど、それが亮太でなくてはいけないわけじゃない気がする。自分にとって亮太は大きい存在だけれど、同時にそれがどうして大きな存在なのか分からない。
付き合い始めてから互いに求めていた。亮太は香織に愛を、香織は亮太に性を。性欲をぶつけるためだけの相手という都合の良い位置に亮太を置いてはいないだろうか。かつてのピアニストとしての生活でたまったストレスをセックスという分かりやすい性的なもので上書きして晴らそうとして、その相手として見ているだけではないだろうか。
心配になったのだ。それで次復縁するまでの間に見詰め直して、それが亮太でなくても良いのか、例えば唯人や浩志やその他でも、お金を貰ってセックスするだけのおじさんでもいいのか。それを確かめたかった。
「先生は、真剣な恋ってしたことありますか?」
真剣な目で見た。
「五十のおばちゃん捕まえて何聞いてんのよ? でも、まあ、分からないでもないわ。私も高校のころに付き合っていた彼に恋をしていたのかって当時考えたこともあるもの。高校生での恋愛なんて深く考えるだけ無駄よ。どうせ皆青春を楽しみたいだけで、彼氏彼女って間柄を欲して、ただそれだけで自分は満たされているっていう感じなんだから」
「私は真剣に彼が好きなのか分からなかったんです。それで一度分かれてみたんです。でも彼が私を好きでいてくれたのは間違いなかった。それで私のわがままに付き合って一度分かれてみてくれたんです。それは間違いなんじゃないかって」
「別にいいんじゃない? 先生の友達で本当に愛してるって言いながら一か月で別れたカップルもいたし、もちろん別にめちゃくちゃ好きってわけでもなく波長が合うから付き合ってたら成人してから結婚まで行っていまだに仲良い夫婦もいるもの」
ピアノの屋根を持ち上げて突上棒を倒してゆっくりと閉じた。鍵盤蓋を閉めた。
「私がピアノをしていたのご存じでしょう?」
「もちろん知ってるわ」
「私はそれでストレスが溜まってそれでも何とか頑張ってやっていて、結果としてストレス発散の方法を間違った方に持っていたんです」
先生は何も言わずに香織の話に耳を傾けた。窓の外から見える桜並木はライトアップされていて仄かに薄暗く光っていた。
「先生に言うのが正しいのかどうかは分からないですし、否定されるかもしれません。でも……」
かぶりを振った。先生は目を逸らさずに真剣な表情をしていた。どうして他人にこんな話をしているのだろうか。ただの学校の先生に話していいのだろうか。
「私のストレス発散方法は自慰でした。まだ小学生高学年でしたから意味が分かってやっていたわけではないんです。でも、中学に上がって彼氏ができて、保険の授業で習った性交をするようになってそれを相手に強いているんじゃないか。自分がストレス発散でしていたことをピアノを止めたにもかかわらず続けていたんです。エスカレートして行って。でも彼は幼馴染で親友の一人でした。だから嫌でも嫌って言わないのかもしれないなって。週に何回も身体を重ねていました。それで間違っているんだろうなって思って一度別れました。正しかったんでしょうかね」
先生はからかうでもなく軽蔑するでもなくただ言った。
「学校の先生としては性交は止めなさいと言うべきなんでしょうね。でも別にそれが間違った行為かどうかなんて先生には分からないわ。今時の高校生カップルなんて毎日のようにしてるって聞いたわ。でも、自分で悩んで相手のことを考えてそれで一度離れてみようって考えて、それはやっぱり相手のこと大事に思っている証拠じゃない? だって大切じゃないなら気にもしないじゃない。女の子でも男の子でも相手を性欲処理の相手だとかストレス発散の相手だとか、それだけしか考えていないなら無理やりしておしまいじゃない。だからしてることは正しいかどうか分からないし私がとやかく言うつもりもない。でも相手を思いやっているのは伝わるからそこが正しいことだけは保証するわ」
意外だった。先生がここまできちんと話を聞いてくれて、それに否定をすることもないなんて、考えられないことだった。どうせ否定されると思っていた。
「先生、また来ます」
香織は笑って言った。その笑顔に驚いたように先生は笑うと言った。
「いつでもおいで」
とても暖かい笑みだった。
第三節
「そう言えば、今日は学校に出たの?」
メールの着信を見た。春香は浩志からのメールを震えた携帯を拾い上げて読んだのだった。この時間にメールが来ることは珍しくなかった。春香にとって浩志は一番信頼していて話しやすい相手だった。
「今日はちゃんと出たよ。授業を聞かないと大変だから」
すぐさま返信すると次の答えを期待するように待っていた。
部屋は一面ファンシーな色合いで染められていた。ベッドの枕元にはぬいぐるみが置かれていて、可愛らしいいかにも女の子の部屋といった感じだった。しかし机の下には大きなフルタワーのパソコンが置かれていて、机の上にはキーボードとマウス、三つのディスプレイとペンタブレットが置かれていた。それだけは部屋に似つかわしくなかった。夜だというのに目がさえていて、健康的ではないなと春香は自身を客観視した。昼夜逆転しているのが良いことではないということは自覚していた。
学校には最低限しか行かない。単位をとれて卒業さえ出来れば良いと考えていた。春香は自分自身で既に金を稼いでいて言わば手に職付けた状態だからそこまで困ることはないだろうと思っていたのだ。既に生取れは困らない程度は稼げていた。それで嫌な思いをしてまで学校に行く必要はないだろう。
「授業に出たのなら良かった。春から全然出てなかったら後々困るからちゃんと早いうちに出席日数だけ稼いでおいた方が自分のためだよ」
笑みが零れた。去年、浩志は出席日数がギリギリで焦っていたことを思い出したのだ。それで警告してくれているのだろうなと思った。
「了解。とりあえず去年のこう君みたいにはならないようにする」
そう返信して携帯を閉じた。これから作業する気にはなんとなくなれずパソコンの電源を落とした。
ベッドの上に寝転ぶと、以前に二人でゲームの脚本について話していた時のことを思い出した。自分の絵が好きと褒められて嬉しかった。多分、自分は浩志に褒められたから余計に嬉しかったんだろう。自分の気持ちに浩志は気が付いているだろうか。浩志が自分をまだ好いていてくれているだろうか。
自分が不甲斐ないせいで待たせてしまっている。かなり昔に照れて唯人のことが好きだと言った時のことをいつまでも後悔している別に唯人のことは恋愛対象としてみたことはない。いわば兄弟扱いだ。だというのに真剣な気持ちを伝えた浩志に嘘を吐いてしまった。
自分のことを好きでいてくれていることには気が付いていた。仕草が分かりやすいから長い間一緒にいれば分かるようになるのだ。それでも自分は気が付かないふりをして焦らして、それでも見てくれる浩志に甘え切っていたのだろうな。だから高校の間に自分から気持ちを伝えようと決心していた。
きっかけがあればいつでも準備はできているつもりだった。亮太と香織が付き合っていることは知っているし、自分も憧れたりする。でも怖いのだ。自分からこの関係を変えて修復不可能なまでに壊してしまうのが。
自分が男性への恐怖を抱いていることを浩志も他の幼馴染たちも知っている。それでも浩志と唯人と亮太は幾分かましなのだ。実質会話して楽しいのは三人と父くらいなものだ。両親はそれを知っているから学校に無理には行かせないし、父は自分からできるだけ距離を保とうとしている。娘にもっと構いたいだろうに。唯人も亮太も幼いころに比べれば少しだけ距離を取っている。いや、自分から取っているのだろう。しかし、浩志に対しては少しの恐怖心はあるものの距離を取ろうと思うほどのものではない。
気が付いているのだ。自分の恋心には。だからメール越しでも直接でも楽しい。そして返事を待ち望んでしまう。あわよくばこのままいたいと思ってしまっている。
電話は恐怖だ。女性との電話は大丈夫だ。しかし、男性とは怖い。あの日のことが甦るから怖い。脳裏にちらつく声を覚えているのだ。何が何でも忘れられない小学生のあの日の恐怖がいくらでも思い浮かぶ。目隠しをされてもう少しで犯され掛けた。
思えばあの時助けてくれたのも浩志だったかもしれないと思い出した。少しでも遅れていたら汚されていただろう。だから感謝もしている。
「ところであの脚本のことなんだけど、天使が気持ちを伝えるタイミングはいつにする? いくらノベルゲームとは言っても最後が見えてないと調整しにくいからさ。僕的にはタイミングははるちゃんに決めて欲しいんだ。五章だけどあと何章で完結するかなって」
メールが来た。そう言えばタイミングを決めて欲しいと言われていた。恋愛要素入りのノベルゲームにしようと言ったのは自分だった。一年以上前から計画して、脚本自体は完成していてそれに手を加えたくなって、それで止まっているのは完結を勝手に引き延ばしている春香のせいだと自覚していた。
自分と天界から落ちてきて地上の人間の男の子に恋をした天使の女の子を重ねていたのかもしれない。それでゲームで告白イベントが出来上がったらちゃんと気持ちを伝えたいと思っていたのかもしれない。
「もう少し待って、今固めてるところだから。とりあえずイラストは添付します。あと、完結は第八章くらいを予定してる。」
メールの本文に追加シーンのイラストをつけて送った。踏ん切りがつかない。
「私自身が八章にたどり着くまでにどれだけ掛かるかな? できるだけ早く……」
春香はきゅっと手を握った。枕に顔を埋めて足をパタパタと上下させた。それからとりあえず両親のいるリビングへと足を向けた。
「お父さんお帰りー」
自分でもぎこちないと思いながらも春香は告げた。距離は三メートルもあるように感じる。
「春香、ただいま」
それでも笑顔で、嬉しそうに答えてくれる父を見てやはり良い父親だと思う。
「春香、運ぶの手伝ってくれない? サラダの皿とお茶碗」
母に言われてキッチンに入る。
「これとこれだねー」
「よろしく」
机の上にはすでに生姜焼きが並べられていた。
自分に対して優しすぎる世界だ。友人はいるしお金もある。両親は良い人だし、ただ男性が怖いだけなのだ。
「私ね、ちゃんと克服したい」
春香はそう言って父にそっと触れた。
「無理しなくて良いんだぞ」
心配げに言った父に笑顔を見せる。
「大丈夫。お父さんはもう怖くないから。あとは触れて長いこといても大丈夫になるだけだから」
「動かないから好きにして良いよ」
「ありがと」
春香は自分に恐る恐る触れられたらどうだろうと思う。恐怖ながらに触られるのなんて本当は気分が悪いはずだ。それでも娘に嫌な顔一つ見せない父を尊敬していた。
「あら、今日は仲良しね」
母の言葉に笑いかけると、
「もうご飯にしよっかー」
父から手を放して食卓に着く。
「いただきますー」 生姜焼きを頬張った。