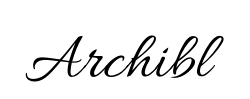第一節
「終わった。何もかもが終わった」
先々週の金曜日までテストだった。唯人は香織の家でうめいていた。例の約束のことはすでに亮太も香織も、春香も浩志も知っていた。今時の学校らしくメールで自分の結果の速報だけは届くようになっていた。学校の掲示板に張られるのは決定した点数と順位である。土曜日の今日は、メールに添付されているスキャンされた自分の解答用紙と模範解答を見比べて、日曜日の十五時までに結果が間違っていないか、間違っているならばどこかを送信しなければならない。
テストの結果が送信されてくる土曜日の朝十時に香織の家で結果を見ようということになったのである。先ほどまでタブレットで絵をかいていた春香も、ノートパソコンでプログラムを書いていた浩志も興味津々とばかりにこの時は画面を凝視していた。
採点科目は、文理で異なる。国語は現代文と古文と漢文の平均点、英語はリスニングとリーディングの平均点、数学は1Aと2Bの平均点、社会と理科はそれぞれとっている科目二教科の平均点という感じで全五教科として五百点満点で算出される。結果として、唯人は社会で一点落として四百九十九点だったのだ。要求をのまねばならぬという憂鬱感が押し寄せてくる。
「すごいじゃないか。ほぼ満点とはあっぱれだよ」
浩志の言葉に、
「満点でないと駄目だったんだ」
「いや、相手も人間だからさ」
「いや、絶対満点だ。約束の時に私と並ぶか私が負けるかと、わざわざ並んで満点の時の条件も付けてきやがったんだ。満点でないわけがない」
「わたしは四百点くらいだったよー」
呑気な春香の声で、余計にがっくりとくる。唯人はもう救いの手がないことを悟って、諦観の境地にいた。
「まあまあ、そんなに落ち込まないで。ほら、クッキー焼いたの。ささ、おひとつどうぞ」
「お、香織の手作りか。最高だぜ!」
唯人に差し出されたクッキーの載った皿から亮太はチョコレートクッキーを奪い去る。
「あ、こら! 亮太のはこっちにあるでしょ!」
その皿からはすでにクッキーなど初めから存在しなかったかのように消滅していた。そして浩志の口の中がいっぱいになっていた。香織は、もうやってられないとばかりにテーブルに皿を載せると、紅茶の準備をしていた。
「春香、溢さないでね」
「大丈夫―、かおちゃんが拭いてくれるからー」
「いや、私は拭くけど下に溢されたらカーペットびちゃびちゃになるじゃない」
「大丈夫―、すぐに乾くからー」
不毛なやり取りをしていた。香織も浩志も四百五十点前後で、亮太は四百六十点前後だった。気楽な四人を見て唯人は、
「あーあー」
思わず声を出していた。
「この一大事に誰も気遣ってくれない。よよよ」
「うるさい。それにゆい君は誰かと付き合っておくべきだと思うの。虫除けになるよ、きっと。そしたら楽になるじゃない。知らないかもしれないけど、ゆい君への取り次ぎを断る理由ができたら楽なんてもんじゃないよ。一日に一人は頼まれるんだから」
「それは申し訳ないけど、あんな変人とフリでも恋人だなんて。面倒臭いじゃあないか」
「それは彼女の周りの人間が聞いたら殺されるわよ。相手にもしてもらえないのに」
亮太はそれを聞いていたのか、
「新聞部とかにいろいろ書かれそうだな」
ぼそっと呟いた。いつの間にか始めていたゲームからは目を離さずに。
「それはないと思うよ。先生の検閲も入るし」
浩志の言葉に、
「もし、検閲まで回されたらバレるじゃないか、先生にも」
「それは時間の問題だと思うけど」
優等生を演じている唯人は、教師たちからの信頼も勝ち取っているがために注目もされやすい。
「まあ、あきらめるしかないってことだねー」
うなだれた唯人を気にする者は誰もいなかった。すでにおやつを食べ終えた春香と浩志は自分の作業に戻り、亮太は相変わらずゲーム、香織は皿の片づけに回っていた。唯人はあきらめて片づけを手伝うことにして、香織を追いかけた。
香織の部屋は二階に位置している。両親との三人暮らしだが部屋数は多い。一階には和室が一室、洋室が二室あり、二階には洋室が二室と残りは物置や書庫になっている。この書庫には唯人も世話になることが多い。専門書から児童書までおいてあり、参考書を借りて行くこともあるのだ。
一階に降りるとキッチンに入る。一般家庭では珍しくキッチンは独立している。ここは香織の母親きっての願いらしく、揚げ物などをした際にリビングダイニングキッチンとは違ってカーテンやソファににおいが付かないようにしたらしい。
「そこに置いておいて」
香織は流し台を示した。唯人は指示通りの場所に運び込んだ紅茶セットを置く。
それから、
「さっきの話だけど」
切り出していた。
「何? 刑部梨乃さんと付き合う話のこと?」
「そう、その話のことだけどさ、どうしたらいいと思う? ほら、知っての通り付き合った経験ないんですけど」
「それは知ってる」
うんうん、とうなずきながら手を動かす。クッキーの下に敷いていたキッチンペーパーをゴミ箱に入れると、
「何をどうしたらいいのか、どういう意図かきちんと言ってもらわないと困るな」
「何をどうしたらって、そもそも何をするために付き合うのか、とか」
うーん、と悩むそぶりをみせると、
「人それぞれだけど、相手と一緒にいるためじゃないかな。好きな人と一緒にいるためで、最終的な高校生の答えとしてはエッチするためじゃないかなと思うけど? だって、高校生で結婚とか考えて交際してたら重いでしょ? 私は重い女だから、そこまで考えちゃってるけどね。それに多分亮太もそうかも」
「なるほどな。愛し合う二人としてはそれが一つの正解なわけか」
唯人は首肯する。それから、
「でも、俺と刑部は愛し合ってないけど?」
「そうかもしれないけど、そこはほら、きっと彼女に考えがあるんだよ。お互い虫除けくらいに思っておけばいいんじゃないのかな、きっと。あの子もいろいろ転校してから言われて、面倒臭くなったんじゃない。それで絶好の相手を見つけたわけだよ。別に好きあってないんだったら、何かされる恐れもないし、たまに一緒に出掛ければ噂もたって勝手に減るとか思ってるんじゃない?」
「なるほどね。互いに恋愛感情がなければいいわけか」
皿を洗い始めた香織が言う。
「本当に好きになって誰か見つけてくれたら、私としてはうれしいんだけど?」
唯人は食器棚を開けて、皿を入れる準備をする。洗われた食器の水気を付近で丁寧にふき取り、片づけ始めた。
「それは……」
今のところその予定はない、と思いながらも唯人は言葉を切って、言おうとしたことを変えた。
「それが現実になったらいいかもしれないな。好きな人なんてできるのか? とりあえず大学に上がってからだな」
そう、と香織は答えた。
「そう言えば、香織は亮太とどうなんだ?」
「そうねぇ、中学の時から付き合ってるから新たな発展なんてなかなかないし、デートしてキスしてエッチするだけかな。最近は……何でもない」
何でもないような顔で言う。
「いくら幼馴染とは言え、俺にそんなに赤裸々に言うのか」
「ゆい君がくっつけたんじゃない。そして、ちゃんと全部ばれてるだろうし。中学一年の夏休みに一週間くらい家族がいないことがあって、そこで二人とも初体験したんだけどその翌日に赤飯もって三人が遊びに来たことは忘れてないよ。もう恥ずかしいなんて思わなくなったし。この前の教室での発言は学校の人に知られたからあんな風にしたんだし」
あんな風に、のあんな風があれほど怖いことはなかなかないと思いながら唯人は話題を変えることもできないでいると、
「でもね、真剣に考えてるけど刑部さんが満点じゃない可能性もあるわけじゃない? そっちをとりあえず願ったら?」
香織が話題を変えた。
「ないとは思うけど、そう願うことにする」
「そうだ、今日のお昼はカレーだから深めの皿出しておいてね」
「了解」
食器棚の中からカレー用に使っている皿を出す。唯人は、スプーンも一緒に出しながら香織のカレーは甘口なんだよな、と思う。昔、暇なときにスパイスの混合から試したとき、小学生の自分たちには途轍もない辛さになって、いまだに甘口のカレーしか食べないことを思い出した。
「カレーはいまだに中辛でも食べないのか?」
「あの時のカレーが忘れられなくて」
「あれは、唐辛子マーク五つ分はあったな」
「何を基準に五つか知らないけど、今なら多分大丈夫なんだろうなとは思ってるの。だってお父さんもお母さんもおいしく食べてたじゃない?」
「今度試すか?」
「遠慮しとく」
しばらくして、野菜のカットが終わり、カレーのルーを投入し終えたところで、香織に皿を運んでみんなを呼んできて、と頼まれる。呼んでも三十分は来ないことを重々承知しているらしい。唯人は、ついでに三十分くらいぼうっとしていてもいいとの許可をもらいに階へと足を運んだ。
「ご飯だってさ」
唯人が声をかけると予想通りうめき声だけが聞こえた。
「ちゃんと返事しろよ。うめくだけだったら飯は当たらんぞ!」
言葉に反応したのは亮太だけだった。
「了解であります」
やっていたゲームが宇宙軍のパイロットとなって敵を打ち落とすものだったためか、若干の違和感ある返事ながらもそれは気にしないことにした。
「今日のお昼はカレーかなー?」
匂いに目ざとく反応したらしい春香は、先ほどとは打って変わってタブレットから顔を上げた。
「よく匂いが分かったな」
「そりゃあ、カレーの匂いがしたからねー」
「答えになってないじゃないか」
カレーに気を取られている春香を見て、こいつは絵と食い物しか興味がないのかと思う。
「浩志は返事なしか?」
わざわざ話しかけたが、返事はない。高速で流れる文字列の映る画面を凝視したままピクリともしなかった。亮太はすでにゲームに戻って、三十分で五ステージとつぶやいていた。春香は、三十分で背景を進めると言う。唯人は、本当にこいつら高校生かよ、とぼやきながら、香織の予想通り三十分かかることが分かり、よく分かってらっしゃる、と苦笑した。
カレーをすっかり胃袋に収めた一同は解散することにする。
「じゃあ、とりあえず今後の展開分かったら連絡よろしくー」
春香の答えはなんとなく予想がついていた。亮太は残ると言っていたので、午後はお楽しみなのだろうか。浩志は充電が切れると走り去った。唯人は、香織の家の隣にある自宅へと帰ることにした。
第二節
「亮太、何で残るって言ったの?」
香織は責めるような目線を向けた。
「だって別れていることは隠しておこうって言ってたじゃないか。それに別に恋人でなくても仲の良い友人同士は二人でテレビくらい見るだろうさ」
部屋ではなくリビングのソファにどっかりと座り込んだ亮太を見て呆れたように溜息を漏らした。別に嫌なわけじゃないし、隠し通すなら確かにこの方が自然だろう。だからこそ部屋には行かないのだろう。リビングでテレビという答えは、今日はセックスをするつもりはないという態度を明確に表していた。両親ももうすぐ帰ってくる。
「まあ、良いけどさ。親には何も言ってないから別れてるなんて思いもしないだろうしね」
「そっか、誰にも言ってないんだな」
「そりゃあ、黙っておこうって言ったの私だし。自分で作った約束を破るような人間ではないと自分では思ってるよ」
「俺は唯人にバレているのかと思ったけど?」
「そんな素振りあったの?」
「いや、なんとなくあいつは感づいていそうだなと思っただけだ」
香織は何でもないように振舞ったが確かに感づかれている可能性があるかもしれないと思った。先ほど言い淀んだ時の違和感を感じられていたらどうしよか、などと考えるがいまさら何を言っても無駄か、と思う。
「それで、本当にテレビを見るだけなの?」
香織はそわそわしながら聞いた。自分から言い出しておきながら、もしかしたら亮太とできるかもしれないと思って期待していたのだ。
「そうだ。恋人でも何でもないんだろ? 今の俺たちは。だから不純なことをすることはできない。それに今は自分を見つめなおしている、というか考えているから残念だけどそういうことはしないって決めてここに来たんだ」
「そうだよね。私たち仮にも分かれてるんだもんね。そういうことはしないよね」
テレビのチャンネルを回す。昼間はたいして面白い番組などしていない。だからテレビを見るだけだなんて退屈に決まっている。それでも一緒にいたいと思ってくれたのかもしれない。
香織は家にあるブルーレイディスクを持ち出して再生機にセットした。
「これを見るほうが面白いと思うの。退屈なニュースじゃなくて映画でも見ましょ?」
亮太は何も言わずに笑って首肯した。
第三節
月曜日の朝の時点で廊下に張り出されていた結果順位は、予想と完全に一致するものだったがために、特に驚きはなかった。掲示板は右上が一番で左下が最下位、三段になって掲示されていた。いつもは唯人の名前があった場所には刑部梨乃と書いてあり、五百の表示。次いで二位に、遠野唯人とあり四百九十九の表示があった。
昼休みが始まった今、朝の掲示板を思い起こしながらも購買で買った総菜パンを咀嚼していた。亮太は向かいに座って弁当を食べていた。この間は特別だったらしく、今日の弁当は香織の手作りではない。弁当屋の人の愛情たっぷり、から揚げ弁当であった。
「おいしいよ、おいしいけどさ……」
悲しそうに言う、
「手作り弁当がよかった」
「それは弁当屋さんの手作りだろ? 間違いはないじゃないか。美味しく食べてもらえるように愛情込めてると思うぞ」
「確かに手作りだ、家のものとは違う、べちゃっとしないから揚げだけどな」
落差に驚いているらしい。べちゃっとしないいつでも美味しいものの方が良いじゃないか。そう思う唯人だったが、何も言わなかった。
「土曜は珍しく映画、それもホラーをお楽しみでしたね。怖かった?」
唯人が一言告げると、
「あいつから見せておいたくせに怖がってしがみつきやがったんだ。手の跡が残るかと思った。というか何で知っている?」
「なんとなく? 残ったってことはそうなのかなって思ったけど、嬌声じゃなくて怨嗟の声が聞こえたもので。もう少しボリューム落としてほしいな、とか思ったり。悲鳴も映像も」
「聞こえてるのかよ!」
「そりゃあ、真昼間だったし聞こえない人のほうが多かったんじゃないか? うちではテレビなんかつけてないし、勉強してたし」
「お前には聞こえてるのかよ。 どんな気分だった?」
「腹が立ったな。人が勉強しているのに映画なんて見やがって。気を遣って帰ったら映画見やがって。俺も誘えよ」
声を潜める。その時間がいつも暇ならと誘いをかけられかねないとクラスの人間には聞こえないくらいの小声になった。
「毎週エッチばかりじゃないのは良いことだ。毎週嬌声を聞かされる身にもなってほしい。というか珍しいな。やらなかったなんて」
「もう黙ってくださいお願いします。これ以上その時に怯えてたなんて話をしたら後で怖い目に合いそうだ。私は怖がりではないが学校で通ってるんだから。それに殺されるのは道連れなんだぞ。無差別攻撃なんだぞ」
この一言に唯人も黙らざるを得なかった。どうしようもないようなじゃれあいの最中に、教室がざわつくのを感じた。唯人は総菜パンの最後のひとかけらを口に押し込むと、ペットボトルの水で流し込んだ。
梨乃が教室入り口に立っているのが見えた。その瞬間脱兎のごとく逃げ出そうとしたが先ほどのお返しとばかりに亮太ががっちりと裾をつかんでいた。放せと小声で言うがその時にはもう遅かった。放したぞというとほとんど同時に、梨乃は唯人を見つけるとつかつかと歩み寄った。
「ごきげんよう、刑部さん。いったい何の用ですか?」
今時お嬢様学校でもごきげんようなんて言うのだろうか。疑問を自分に投げかけながらにっこり笑み向けた。すると梨乃は無表情だった顔を少し歪めて、
「少し立ってくれる?」
一瞬とはいえ企み顔を見てしまった唯人は、警戒しながらも立ち上がった。それに表情が少し出たことにも驚きがあった。
「立ちましたけど、これでいいですか?」
と、いきなり梨乃が唯人に抱き着いた。ふわりとする花香りを髪から感じて立ちすくんでいると、教室中が黄色い悲鳴に包まれ、もしくは嫉妬の視線が突き刺さった。
「何を……」
耳元で梨乃は、
「約束は守ってもらうよ」
それはもう邪悪な声色だった。唯人にしか聞こえないその声は真っ黒だった。唯人は内心で、やばいぞこれはと絶叫しながら、梨乃を身体から引きはがした。そして手を取って一目散に教室から駆け出した。廊下ですれ違うたびに見られながらも、正門から出て庭園エリアの木の密集地でようやく立ち止まった。
「どういうつもりだよ!」
唯人は梨乃にかみつく。しばらく頭を抱えて悩んだ末の声がそれである。
「だから、約束は守ってもらうと言ったじゃないか。それに約束を破られたら『優等生の遠野君が美少女転校生に乱暴か?』というタイトルが躍る新聞部の号外が出ることになっただろうね」
「約束を守ることは仕方ない。だが、あんな場所であんな風にしなくて良かっただろうが。というか脅しが怖い。俺の人生が終わるやつじゃないか」
唯人に対して不思議そうに、
「あんなふうじゃなきゃダメじゃない。虫除けといったんだから、周囲にみられる中での抱擁とかキスが一番効果的だろうに、何を不思議なことを言ってるんだ? キスではなかっただろう?そんなに怒ることはないだろう」
確かに、キスよりはマシだなと思うしかし、付き合うことを秘匿できなくなったではないかなどと焦る。唯人はこの変人が突飛なことをしでかす前に、何とかしなければと再び頭を抱えた。
「何はともあれ、負けは負けだ。言うことは聞こう」
「潔いのだな。というか他の男に声を掛けたらきっと舞い上がってただろうね。それに抱擁のおまけつきだ」
「そう思うなら、声かけてやれよ」
「あなたはどう考えても相思相愛になる気がしないから選ばれたんだから、そのほかじゃあ意味ないじゃないか」
「なんかひどいことを言われてる気がするが、まあいい。条件を付けさせろ。学校でなるべく接触するな」
目を見つめながら、
「それじゃあ意味がないじゃないか」
唯人の言葉に梨乃は反駁した。
「そもそも虫除けと言ってるんだから役割は果たしなさい。これは命令だから」
「百歩譲って昼食を食べるくらいはいいだろう。それ以上は学校で余計なことをするなよ」
「時々出かけるのに付き合ってくれるならそれで構わないが」
こいつ何を言っているんだ。唯人は、これじゃあ恋人じゃないか、というと、だから最初の時から恋人になれって言ったじゃないか、と返される。
「別にキスしろというつもりもないしするつもりもないが、荷物持ちくらいはしろ、という意味だが。きっとあなたのもとには集まるだろうな、いつデート行くんだとか、そういう噂好きの連中が。そして、私にもな。定期的に出かける予定を行っておけば追い払えるから言いじゃないか」
それもそうか、と唯人は自分を無理やり納得させる。
「まあ、いい。今回のことは俺にもメリットが一ミクロンほどあるから、そういうことにしておく」
「そう言えば、一点は何を落としたんだ?」
興味もないだろうに梨乃が訊ねた。
「テストか? あの時の自分を殴ってやりたいのを我慢するのが大変だが、答えよう。世界史をとってるんだが、それの論述問題で漢字を間違えた。あの一点がなかったら今頃話してもいないだろうに」
「私としては、ラッキーに思ってるよ」
「なんで俺なんだ? 他にもいるだろうに」
梨乃は少し考えると、
「前も言ったように似た者同士で互いにそんなに恋愛に興味がないからだ。後は、問いに答えたからだな。私の問いに答える人は少なかったんだ。周りで話したそうにしているから聞いてやったらすぐに逃げるし、おまけに変人扱いするんだ。失礼なのか、答えられなさそうだと耳が遠くなる病気なのか、それは知らんが聞かれたら自分の考えを述べればいいだろうにな」
唯人は呆れ顔で、
「いや、あの質問は変人だぞ。別に答えようが答えまいが多分変人だと思っているだろうな。俺も変だと思うぞ」
「あなたも変人扱いするのか? 失礼だな」
そう言ってから、
「それはそうと、これからよろしく頼むよ、彼氏君」
「あのな、それは笑顔とかいたずらっぽい顔で言うからそれっぽいのであって、ほとんど抑揚のない声で、無表情で言われても怖いだけだ」
「なんだかエロゲのバッドエンドみたいだと言いたいのだな? ヤンデレヒロインの最後とか」
「年齢制限を守っていないでエロゲをしていることには突っ込まないでおいてあげよう。でもちょっと怖いから改めて笑顔でやってみよう」
梨乃は目が笑っていないアルカイックスマイルを浮かべた。
「これからよろしく頼むよ、彼氏君。それと」
「余計に怖いわ。アルカイックスマイルって、あんたは仏像かなんかか? 笑うなら笑え、ただし目元も。笑わないなら笑うな」
「じゃあ、笑わないでおこう。無表情こそが私らしいかもしれないからな」
「努力しろよ、きっと損してるぞ。顔は悪くないだけに損してるだろうな。縁日だったら金魚すくいで取れなくても三匹おまけしてくれるレベルだぞ」
「その基準はなんだか知らんが、私は笑うのが上手くないんだ。笑うことなんてほとんどなかったからな」
仄かに暗い表情を浮かべたように見える。実際には表情などほとんど変わっていないのに。これはこれからなんとなくでも分かるようになったほうが快適そうだ。唯人は、何とか表情を読み取れるようにしようと考えた。
「そろそろ次の授業が始まるから戻るとしよう」
梨乃はやはり抑揚のない、表情の読み取りにくい声で言った。
「さぼりたいところだが、そう言うわけにもいかないからなぁ。優等生はつらいぜ」
「ならやめれば言いじゃないか。何不自由なくなるぞ」
唯人はかぶりを振る。
「推薦狙ってるからそう言うわけにもいかないのな」
「別に受ければ受かるだろう? あなた、頭はいいんだろうから」
「嫌味か! それにそれじゃあ意味がないんだ。他人の受験期真っただ中にすでに受かって遊びまわれるのがいいんじゃないか。おすすめだぞ、推薦受験」
「推薦受験したら、大学生活も母校に筒抜けらしいじゃないか。そんなのはごめんだね」
「大丈夫、大学までは真面目キャラで行くから」
「キャラって……」
「お前はさしずめクールキャラってところか?」
「残念ながら私はキャラではなく本性だ。がっかりしたか? 別に好きでなくとも彼女にするんだ、普段はクールを装いながらも二人きりの時は……とか期待したのか? エロゲじゃないんだぞ?」
「いいや、求めてない」
校舎内に入ると、下足箱で別れる。とその前に、
「そうそう」
梨乃はメモを取り出した。
「これが私のアドレスだ。ばらすなよ?」
「あとで空メール送っとく」
唯人はメモを胸ポケットにしまった。妙なことになってしまったな、などと思いながら教室に戻るのが憂鬱だった。
教室に戻ると唯人は亮太に引っ張られて教室の隅に移動させられた。小学生が秘密の話をするときのようにカーテンの陰に入ると、
「で、どうなった?」
単刀直入に聞いた。
「付き合うことになった。約束通りのことだがな」
「そもそもなんでそんなに約束したんだ? 断ればよかったのに」
唯人はため息交じりで言葉を紡いだ。
「脅されたんだよ。あいつに、『私、遠野君に乱暴されました』って、新聞部に話すぞってな」
「そりゃあ、また結構な性格をしてるな」
「しょうがない、慣れるさ」
人間の適応能力の高さを信じて唯人はカーテンから出る。
自分の席に戻ると、
「遠野さんって刑部さんと付き合ってるんですか?」
人って知りたがりだな、と面倒なのはおくびにも出さず、
「お付き合いしていますよ」
笑顔で答えた。
「そうなんですね」
教室では悲鳴があがったが、唯人は完全にスルーして教科書を机の上に出した。
「人の噂も七十五日っていうけど、七十五日って長いよなぁ」
ぼそりとつぶやいた。
第四節
それは突然の出来事だった。急に電話が掛かって来たのだ。春香は自分が電話をするのが苦手だと知っている浩志から電話があったことに驚きながらも普段は絶対にしない行為に何かあったのではないかとどきりとした。
「もしもしー。春香だけど?」
「はるちゃん、電話してごめんね……」
電話の向こう側からは酷く動揺した声が聞こえて来た。何かあったに違いない。というか何もなければ電話なんてして来ないだろう。それに夜だ。だからこそメールではできないほど切羽詰まっているのだろう。
「それよりどうしたの? すごく震えてるよ、声」
「実は……」
息を吸う声のが聞こえた。震えながら落ち着かせるかのような息遣いが耳に入る。
「ゆっくりで良いから」
春香はパソコンの電源を落として、バッグの用意をした。財布と飴玉を入れてすぐに出られるようにした。
「じいちゃんとばあちゃんが、事故で死んだ」
固く冷たい声だった。春香は全身を衝撃が突き抜けるような気がした。浩志が唯一信じていた大人、彼らが死んだというのだ。動揺もするだろうし信じられないだろう。春香はすぐさま聞き返した。
「それは誰から聞いたの? 本当のことなの?」
「それが、警察からなんだ。バッグに入っていた財布から免許証が出てきて一緒にあったメモの電話番号に電話してるんだって言われて、道路を横断中に撥ねられたって……」
泣き出しそうな声に春香は立ち上がった。
「今どこにいるの?」
「家にいる…………」
「すぐ行くから」
春香はすぐにバッグをつかんで玄関へ向かった。廊下で母に手短に浩志が大変かもしれないから行くと告げて家を飛び出した。普段は運動しない自分を呪った。今この時、きっと浩志が連絡したのは自分だけだ。そう思ったのだ。自分が何とか早くたどり着かないといけない。
浩志の家はそう遠く離れてはいなかった。家から見えるマンションの一室に住んでいることは何度か部屋を訪ねたので知っている。
マンションに飛び込むと部屋を目指した。マンションに入るには鍵とパスワードが必要だったが、マンションから出てくる住人と上手く時間が合い滑り込んだ。エレベーターで階を上り部屋の前にたどり着くとインターフォンを鳴らした。
「浩志!」
ドアが開くと真っ青な顔をした浩志がよろよろと出てきた。
「はるちゃん、僕、どうしたら……」
とても冷静に見えない、酷い顔の浩志に、
「警察はなんて言ったの?」
「本人か確認して欲しいから警察署に来てほしいって……」
「分かった。私も行くから。着替えと荷物準備して。あとこれ」
飴玉を取り出して口に押し込んだ。
「とりあえず落ち着いて」
春香はいつものふわりとした話し方とは違い、はっきりと言った。
「……」
押し込まれたままに浩志は飴玉を舐めながら荷物を準備し始めた。
春香はタクシーを呼んでそれから唯人に助けを求めた。
浩志が祖父母を亡くしたかもしれない。今から警察に一緒に行くからとりあえず私の家に行って着替えを受け取って浩志の家に来て。
メールを送るとすぐに浩志のよろよろとした身体を支えるように腕を持った。
「じゃあ、行こう」
部屋の扉をバタンと閉めた。
タクシーに乗り込むと警察署へと急いだ。隣の崩れ落ちそうな浩志に声をかけた。
「しっかりして。今は確認が先。シャキッとしなさい」
浩志は相変わらず心ここにあらずといった様子でふらふらとしていた。
「警察署についたら出せるように学生証をポケットに入れておいて」
多分本人確認がされるだろうと思いせっつく。のろのろと財布から取り出した学生証をポケットに押し込むさまを見ながら、これから浩志は大丈夫だろうかと心配した。本人が祖父母以外の親類から距離を置いているのも理由も聞いている。だからこそ、この弱ったときに付け入られないだろうか。自分が守らなくちゃいけない。あの時ぎりぎりで守ってもらったのだからその時のことを返さなければならない。
そんな義務感と、親友で幼馴染で、好きな人のことは守らなくちゃいけないという感情が沸き上がり、そっと頬を撫でた。
タクシーが到着すると料金を支払い浩志を連れて受付へ向かう。そして説明を受けた。亡くなったのは一週間ほど前で家族には連絡が行っていて検視も済んでいたこと。今日引き取るから電話をしてほしい相手がいるといって、自分たちは着信拒否されているかもしれないからかけてほしいと頼まれて浩志への連絡を依頼されたこと。
浩志が遺体安置所に足を運ぶとすでに浩志の父と母がいた。春香は庇うように浩志の隣に立った。
「浩志。電話には出ろ」
「あなたに連絡するのは大変だったわ」
両親はそう言った。浩志はそちらを見ることもなく顔の方へと移動し白い布を捲った。
「ああ」
声に出ていた。歪んだ声が鼓膜を震わせた。
「あああああああああああああああああああああああ」
浩志は壁に背中を預けるとへたり込んだ。ちょうど葬儀屋がやってきた。すでに浩志の両親は葬儀屋と話して搬出の話をしていた。
震えていた。声が腕が指先が身体が。春香は横に付き添った。
「浩志。葬儀の準備があるから明日は家に来なさい」
冷たい目だった。声も硬かった。踵を返すと部屋から出て行った。
「こうちゃん……」
春香は力なく座る浩志を立たせると遺体安置所から出てロビーへと向かった。
「私がいるから。今日は私が泊まるから」
声のかけ方が分からなかった。しかし、一人にしたくなかった。
ロビーへと向かい椅子に座ると浩志はすすり泣いた。春香はそっと肩を抱いた。
「ただいま」
春香は浩志を連れて戻った。マンションの前では唯人と亮太、香織がいた。
「お帰り。着替えはこれ」
唯人に手渡された荷物を持ってマンションの部屋に向かった。後ろから続く唯人たちに目配せした。
「こうちゃん、とりあえず風呂に入って。ゆい君とりょう君よろしく」
任せてすぐに風呂に入れた後、香織に、
「こうちゃんは今晩心配だから泊ってく。皆もできたらいて欲しい」
春香の言葉に、
「人はあまりいないほうがいいんじゃない? いくら私たちが親しいからって一人の時間が欲しいんじゃ……」
「今日は絶対一人にしちゃ駄目な気がするの。取返しがつかないことになる予感がして」
「そっか。私たちはリビングにいるから春香は寝室に浩志といて。後でご飯運ぶから」
香織に礼を言うと荷物の中にあったジャージに着替える。今まで来ていたものをしまうと香織が作り始めた料理の様子をぼうっと眺めた。
私には今、何もできない。だから、傍にいるしかないのだ。何とかしなければならない。
「春香、出たぞ。唯人が服着せてるからあとよろしく」
「うん、ありがとね。こんな夜なのに」
葬儀屋が来るのが夜というのはいささか変ではないかと思ったり、どうしてもっと早く知らせなかったんだと思ったり。それから昼は忙しいから引き取りが夜しかなかったのか、よく承知したななどと考えながら寝室へと向かった。
浩志をベッドに座らせて食事を採らせて、寝かせた。隣で手を握る。一緒のベッドで寝るなんて初めてかもしれない、もしくは幼稚園の時以来だなと思う。
「浩志、起きてる?」
返事がないことに安心しながら続けた。
「寝てるから言うけど、私、浩志のこと好きだよ。でもまだ少し怖いの。男の人が。それと、私はどこにも行かないから。私のことを今も好きでいてくれるなら。浩志より先にどこかに行くことなんてないから。だから……」
寝息が聞こえてきた。だからこそ言えたのだ。
自分の思いをこんな時に言ってしまうなんてどうしようもない人間だと春香は自分を責めたが、同時にこんな時でもないと卑怯でないと言えないかもしれないと思った。
次第に瞼が重たくなってきた。寝てしまう。そう意識する暇もなく、自然と眠りに落ちた。
「寝たね」
唯人が言った。その声に二人は首肯で応えた。
「浩志大丈夫かな」
「どうだろ。でも春香がいるから今は大丈夫じゃない?」
「あの子、ふわふわしているようで芯は強いし、意外としっかりしてるから」
亮太の問いに唯人と香織が答えた。
「これから先どうするかだな。あいつの家族関係は複雑だから……」
「あいつが信用してた大人って唯一、じいさんばあさんだったからな。今このタイミングはきついかもしれないな」
「これからきっと親族に会うともっと辛い思いするぞ」
「でも葬式に出ない訳にはいかないだろうし、じいさんたちとかかわりがあったって言っても家族葬だったら付いて行って守るわけにもいかないし」
「頑張って、って言うしかないね。春香がどこまでできるかにもかかってるかもしれないね」
「俺たちが土足で入れないほどに二人は特殊で特別な関係だと思うから」
三人は交代で眠ることにして唯人は最初の起きる当番を引き受けた。