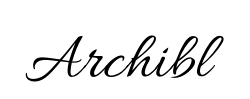わたしは、ひとりで絵を描いていた。暑いと思いながらも教室のエアコンがついていないので扇風機で我慢するしかない。しかし、絵を描いているのだから扇風機の風量を『強』にするわけにもいかず、頬を流れる汗をときおりハンカチでぬぐいながら筆をはしらせていた。
教室は生徒用の机も椅子も撤去された状態で、だからこそ広さを感じることができていた。使用されていない空き教室。それがわたしの今いる場所だった。
部屋には壁掛け時計と温度計が設置されており、それに目をやると室温が二十五度を超えているのが目にとまった。日本の猛暑は特有のもので、この蒸し暑さがわたしは嫌いだった。
日本よりも暑い地域、赤道付近の国々や乾燥した砂漠地帯の多いアフリカ大陸の人々はこれを超える温度の中で生活しているのかと尊敬の念を覚えるが、それでもその地域は蒸し暑いのではなく、ただただ乾燥して暑いだけで、肌にまとわりつくような暑さではないのだから、実は幾分かマシなのではないかと疑っている。
わたしが所属するのは美術部だ。美術部の部室では現在、夏休みに入ってもいないのに夏休み明けの文化祭の展示に向けて絵の制作が進めている。わたしはせわしない部室から外に出されているのだった。顧問いわく、年々絵の製作開始時期は早まっており、それに比例してか絵のクオリティも向上しているらしい。
わたしは、製作時間が長ければクオリティも向上するに違いないと当然のように思った。元々美術部が早くから制作に取り組むのは、過去に文化祭当日に間に合わなかった例があるからで、それを避けるために早めの完成を目指していることには否定の言葉を投げかける考えはなかった。
それで、わたしは文化祭用の部員との合作、それの担当分を終えており、手持ち無沙汰になって部屋から外に出されている。わたしは自分が文化祭に展示する用の絵を完成させるべく、誰もいない空き教室で、イーゼルを立ててキャンバスに向かっているのだ。
キャンバスは今やわたしの筆跡で埋め尽くされていた。わたしは校舎三階の空き教室の窓から見える風景をそこに展開していた。
淡い空色の透き通るような空に、うっすらとところどころに重なる白い綿がある。その空の真ん中には貫くように一筋の飛行機雲と、胡麻粒のように小さくなった航空機が描かれている。その下には小さく瓦葺の屋根が軒をつらね、そして電柱や道路標識、車道を示す白線、その線の間には制限速度表示が見える。
もちろんそのまま描けば手前の校庭や駐車場、校門など雑多なものが混じってしまう。だから描きにくいものや描きたくないものは削って、少し、もしくはかなり美化された街並みを描いていた。
わたしは細部に少し手を加えた後、細筆を水入りのバケツに浸けてため息を吐いた。
もう少し空のグラデーションを細かくしたい。雲を減らしたい。そして明るすぎる街並みをもう少し落ち着かせたい。自分の絵を見るうちに修正箇所ばかりに目が向いてしまい嫌になる。バシャバシャとバケツで筆から色を落とすと、太めの筆に持ち替えて、パレットにある絵具から色を取り上げキャンバスにのせた。
それからパレットに追加で藍色の絵具をチューブから押し出すと、残りわずかであると明らかにわかる音を立てて最後の数グラムを差し出した。
わたしは追加で絵具を買わなくちゃならないと思いながらも、藍色と白や青やそれから水色と混ぜ合わせて独特の色合いを作るとひとりで満足してもう一度キャンバスに筆をはしらせ、雲の一部を覆い隠した。
「綺麗だね、その絵」
わたしは突然の声に驚いてあやうく筆を取り落としそうになった。それから鈴の転がるような軽快で元気の良い声の主を視界に入れるために、かたわらにあった棚にパレットをのせて筆をバケツに突っ込み、それからようやく振り返った。
声にぴったりな気がする黒髪のショートカットを揺らして笑顔でこちらを見る少女に、見覚えがなくわたしはただただ困惑しながらも、ほめてもらえた絵の礼を述べた。
「ありがとうございます」
わたしよりも身長は数センチ低いだろうか。柔らかそうな頬は暑さのせいか上気していた。学校指定のセーラー服の袖はまくられ細く、それでいて健康的な色に焼けた腕が惜しげもなく見せつけられていた。リボンは緩められていて豊満な胸が下から突き上げるように布を持ち上げているのがわかる。スカートはもはや脱ぎ捨てられ、体操服の半ズボンが太ももを覆い、これまたほっそりとしたしなやかな足首までのラインはどこかカモシカを想起させた。
誰だろうか。じっくりと観察した後に出てきた感想がそれである。わたしの記憶にはやはりない。同じクラスになったことはないだろう。そう結論づけた。
「私は中野深月。深月って呼んでね」
わたしが彼女のことを誰か分かっていないのを見透かすように彼女は自分の名前をあっさりと明かした。名乗られたらきちんと返すのが礼儀だというのはわかりきった話だからとわたしは自分の名前を示そうとするがそれを先に手でさえぎり彼女に言い当てられた。
「前田凜ちゃんでしょ? 美術部の天才だとか、不愛想な美人さんだとか、色々噂は聞いてるよ。でも多分不愛想なのは今みたいに話しかける隙を与えないでマシンガントークをする人ばかりで反応する暇もなかったからそう言われているだけじゃないかなって思うんだけど、どうかな? 美人さんと天才は事実だとしても」
彼女の言葉にわたしはこくりと頷くしかなく、まっすぐに彼女の目を見つめた。
「わたしはあなたの言う通り前田凜です。天才とか美人とかは知らないですけれど、わたしは別に不愛想にしているつもりはないですよ」
ようやく言葉をつむぐと彼女は納得したかのように満足気な表情を見せた。
わたしは、天才だとか美人だとか言われるのには慣れていなかったので少し照れてしまったが、それと同時に、この人は絵をほめてくれているんだけれどこの絵については面白いと思ってくれるのだろうかと疑問を心に浮かべた。
「綺麗って言って貰えて嬉しいです。でも、退屈な絵でしょう? 何の変哲もない美化された街並みなんて見ても。色々な人が綺麗だけれど退屈な絵っていう風に評価しますし」
自嘲してわたしは彼女に告げる。自分の退屈な絵は見る価値もないものだと。
「私は絵に面白さなんて求めないから気にはならないけど? 第一、面白い絵って漫画だけじゃないの?」
わたしは思わず笑ってしまっていた。それはそうだ。ストーリーもないのに面白いはずもない。ストーリーを見出すのは鑑賞者自身のセンスだろう。
「結局、面白くはないってことですよね?」
「そりゃあ、漫画じゃないからね」
彼女ははっきりと答えた。わたしにはその答えが面白くて笑ってしまった。
「凜ちゃんって、絵画コンクールで何回か金賞獲ってたよね?」
その質問にわたしは、
「一応は獲ってますけど、評価は綺麗なだけで退屈な絵ですけどね」
「私にとって綺麗な絵っていうのは大切なことだと思うの。それにチョビ髭生やした偉そうな美術界の大御所の意見なんてどうでも良いじゃない? ただ綺麗なだけで凄いんだから」
わたしはこの言葉に少し救われた気がした。
「ちなみに、深月さんは何をしにこの教室にいらしたんですか?」
話題を変えるべく質問を返すと、深月さんはころころと笑いながら、
「私は別にこの教室には用はないの。単純に廊下から絵が見えたから来ただけ」
暑いから開け放しておいた廊下側の扉と窓からは確かにわたしの絵は見える。完成前の作品を見られた気がして少し恥ずかしいなんて思いもあったけれど、ほめてもらえて嬉しかった。部活の仲間からは孤立していて、評価なんてしてもらえないから関わり合いがない相手からほめてもらえるのは励みになった。
「ただの偶然でも深月さんに綺麗な絵だって言ってもらえて嬉しいです。本当に。他にそんな単純にほめてくれる人はいませんから」
「私のことを単純だって馬鹿にした?」
「いいえ、純粋だってほめました」
「そっか」
しばらく互いに笑いあった後に、わたしは彼女のことをあまり気にとめないことにして、むしろ制作過程を見られてもいいような気がしてパレットに出した絵の具が乾かないうちにもう一度色を重ねた。
「あのね、それで落ち着いて聞いて欲しいんだけど……」
突然切り出した彼女に、わたしはパレットを再び棚に置いて絵筆をバケツに突っ込んで顔を見た。何かを言い出しかねているのだろうが、解らない。
彼女はどこか不安げで、しかし芯の強さを感じさせる表情になって、それからやっぱり悩んだ表情で。わたしはじっと彼女を見守った。
「突然だけど、凜ちゃん。私とつきあってくれませんか?」
わたしは困惑した。そして言葉を反すうした。『私につきあってくれませんか?』ではなく、間違いなく『私とつきあってくれませんか?』で聞き間違いではなかった。
どうしてわたしとつきあいたいのか。会ったばかりで何を言い出すのか。幾らでも言葉は口をついて出るだろう。それでもわたしは最初に言った。
「わたしは恋だとか愛だとかわからないですよ?」
彼女は少し笑って、
「それでも構わないの。私もわからないから」
確かに彼女はわたしに好きだからつきあって欲しいなんて一言も言っていない。ただつきあって欲しいと言っただけなのだ。
「それにわたしたち女の子同士だけど……」
わたしの言葉に彼女は、
「知ってる。だからこそ女の子に言ってるの」
そう答えた。純真な目で、ただ興味本位でそう言っていることが分かった。そして、
「私も女の子が好きかなんてわからないし、それに男の子でもいまだに誰が好きかなんてわからないから、おためしでいいからさ。お互いにおためしで」
「それってどういう状態なの?」
「親友以上恋人以下の関係になって欲しいっていうことかな」
彼女の言葉にわたしは少し考えてから、
「じゃあ、お互いに別に好きな人が出来たら別れるということでよければつきあいましょうか」
そう告げた。彼女は嬉しそうに、
「それじゃあ、よろしくです。凜ちゃん」
人懐っこい笑みを浮かべた。 わたしはわからないなりにも彼女のことを精一杯知って、好きになれるように努力して、それからその先のことは考えようと決意した。とりあえずは親友以上というポジションを理解するために互いに話をしなければならないと思いながら。