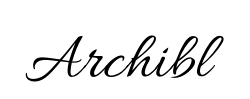教室のこもるような空気と反射した斜陽ではなく、炎天の下にさらされて立っていた。わたしたちが立っている場所には日陰もなく、ただ帽子の陰に入って凌いでいるだけだった。
わたしは、深月ちゃんと共に頼まれた絵を描くためにサッカー場に来ていた。わたしと彼女は互いの陰に入ろうとたわむれるうちに、元気もなくなりあっという間に疲れ果ててしまっていた。
そう、わたしは今回の頼みを聞き入れたことを早くも後悔していたのだ。
「ごめんね、つき合わせちゃって」
わたしが深月ちゃんにそう伝えると、彼女は気にしたそぶりもなくタオルで額の汗をぬぐいながら答えた。
「私、夏休みに入ってからクーラーの効いた部屋から出てなくて、生活リズムも狂ってて、それでお母さんからたまには健康的な若者らしく外に出なさいって口うるさく言われていたの。だから今回の約束は渡りに船って言うか、丁度良いきっかけだったって言うか。だから全然気にしてないよ。そう、全然気にしてなんか……ないよ」
「すごく気にしてそうな言い方だけど?」
わたしは思わず吹き出してしまった。
「それにしても暑いね。これだから外は大変なんだよ。汗をかいても涼しくならないし、喉はすぐに渇くしさ」
彼女は健康的な肢体を惜しげもなくさらすように薄手の白いTシャツに黒い短パンをはいていた。靴は運動靴で、はたから見ればどう見ても運動部のエース級の生徒で、彼女が帰宅部だということがにわかには信じられなかった。
わたしは彼女と反対の格好だがそれは日焼けが嫌だからで、薄手ではあるが長袖、それに下は薄いジャージの長ズボン、靴はスニーカーと、運動部に連れ出される文化部のような格好になってしまっていた。
「日焼け止めちゃんと塗った?」
わたしが彼女に訊ねると、
「一応べったり塗ったけど既に汗で流れてそうだよね。それにしても凜ちゃんは暑くないのかい? 私なら耐えられないだろうけど」
「しょうがないじゃない? だってわたし、肌が弱くて直ぐに皮がはがれたり、真っ赤になったりするんだもの」
わたしはさりげなく彼女を見やると、薄手だからかいつもより目立つ胸部が、Tシャツの布を下から突き上げるように持ち上げていて、それから自分のを見ると絶壁とまでは言わないが彼女と比べて、女性の膨らみが慎ましやかで少しうらやましい気がした。
「さっきから胸ばかり見てるの、気づいてるよ」
彼女はいたずらっ子のように無邪気な笑みの奥に、少し妖艶さを滲ませてわたしの耳元に口を寄せると、
「凜ちゃんのエッチ」
耳にかかった吐息に思わず悲鳴を上げると、彼女はキャッキャと笑った。
「わたしより大きくてうらやましかったんだもん」
素直な気持ちを口にすると、
「そっか、そっか。うらやましいんだね」
そう言ってから、
「でもね、重くて肩はこるし、夏場は胸の間とか下とかに汗をかくから面倒だよ? それに男の子からエッチな視線を向けられるし」
「でも、それは持つ者の意見で、わたしみたいな持たざる者の意見ではないからね。うらやましいものですよ。ナイスバディーになりたい」
わたしは彼女の胸をぺしぺしと叩くと、
「凜ちゃんもきっと大きくなるよ」
そう言って笑った。
サッカー場とは言っても、本来の用途は陸上競技場で、真ん中の芝生の部分にゴールと線が引かれて使用される。県営の総合運動公園にあって、学校からは自転車で三十分程度、バスだと十五分程度の時間で着く。わたしの家は学校からはそう遠くはないし彼女の家は少し遠かったがわたしの家と同じ方角で、学校近くのバス停で待ち合わせをしようという話になって、それでバスでここまで来たのだった。
「バスも暑かったね」
わたしの言葉に、
「クーラー故障してたのかな」
「それにしても本当に暑いね」
「酷暑ってこのことだね」
「ね」
「教室も暑かったけど、ここは直射日光だから余計ね」
「ね」
「水分補給しないと倒れそうだね」
「ね」
「ちょっと。ね、だけで済ませないでよ」
「だって話すだけで体力が削られそうなんだもの?」
「そうだよね」
会話の後に、わたしと彼女は水筒からこくこくと水を喉に流し込んだ。つうと汗が額から流れ落ちる。彼女の頬を伝って首を通って鎖骨のあたりまで一筋に流れるキラキラした汗は凄く蠱惑的に感じた。
「それにしてもこんな暑いのにサッカーってやるんだね」
「そりゃあ、雷でも落ちない限り大抵のスポーツはするでしょ?」
わたしはその答えにぞっとした。土砂降りの中サッカーをする人たちを想像するだけで、風邪をひきそうだった。
「そろそろ始まるかな?」
彼女の問いに、
「そうだね、あと十五分くらいかも?」
そう答えて観客席に向かった。
わたしは観客席に着くと、なるべく日陰を選ぶかのようにグラウンドからは遠い場所を選んだ。背中のリュックサックから双眼鏡と、スケッチ用の紙とペン、それからカメラを取り出して座った。
「色々持って来たんだね」
彼女は興味深そうにわたしの荷物を眺めると、双眼鏡でグラウンドの様子を仔細に観察し始めた。すぐに選手が入場してきて、グラウンドの中央に並ぶと挨拶して、試合開始のホイッスルが鳴り響いた。
わたしは彼女から双眼鏡を受け取ってポジションと背番号を聞くと、覗き込んで彼を観察した。ユニフォームを着ているが既に汗まみれに見えて、どうしてスポーツなんてしてるんだろうと思った。
足の筋肉は瑞々しくしなやかで、足運びはスムーズ。一度ボールを持つと吸いつくようなドリブルで前半でハットトリックを決めてしまった。わたしは彼が上手なのかそれとも相手が下手なのか判別がつかなかったが、下手ということはないだろうと彼の動きを切り取るように写真に写して、それからスケッチに移った。
結果として彼のチームはこの試合を勝ち残った。しかしながら、この大会は規模が大きい上に総当たり戦という謎の決まりで、一週間にわたって続くらしく、明日も明後日も明々後日も大会かと思うと、ベンチの人も出れていいのかななんて思いと、大変そうだという思いが交錯した。
わたしは今日の試合は午後に後一度だと聞いていたので、せっかくなら最後まで観ようと思って来たが、もう既に限界だった。
わたしがサッカー部のテントに向かう途中で、彼に会って勝利を祝う言葉をかけると、期待して待っていると言われたので、期待しないで待っていて欲しいと告げた。
昼食を食べるのに程よい時間になって、わたしと彼女は競技場から少し離れた遊具のある公園のエリアに足を運んで、影にあるテーブルセットに座る。多少なりとも涼しさを感じられたので直射日光に当たるだけであれだけ暑いのかと体感した。
「ご飯、食べようか」
わたしが彼女に告げて弁当箱を広げると、彼女も呼応して彼女のリュックサックから弁当箱を取り出してテーブルに広げた。わたしの弁当は卵焼きや唐揚げで、彼女の弁当には肉巻きや一口ハンバーグが入っていた。
「凜ちゃん」
わたしが弁当のほうを見ているところで彼女にそう呼びかけられて顔を上げると、彼女との顔の距離が近くて一瞬驚いて停止した隙に唇に瑞々しいものが触れた。
接触部分からは熱が伝わって来て、触れるようなキスだったにも拘らず、どうしてか熱を帯びて来て、ふわふわとした気持ちになった。わたしのファーストキスは突然に奪われた。唇がそっと離れようとする中でわたしはまだ触れていたという欲求と、離れたら消えてしまいそうな胸の高鳴りを残しておきたいという欲求とで支配され、一瞬離れた唇に今度は自ら触れるために顔を寄せた。
わたしはテーブル越しのキスから移動して彼女の隣に腰を下ろすと、腰を引き寄せて口吸いをした。最初はちろちろと舌で彼女の唇をなぞり、唇にできた少しの隙間からゆっくりと舌を侵入させ彼女の口腔内を蹂躙した。舌を絡めて唾液を交換する。彼女は嫌がる素振りを見せることもなくただ無抵抗にされるがままになっていた。彼女は積極的に舌を絡めることはなかったけれどわたしはそれでも良いと思った。
名残惜しくも互いの熱が離れて行くと互いの唇から艶っぽい唾液がつうと伸びて、直後には彼女が顔を真っ赤に染めるさまが目に見えた。抱き着いた時の柔らかい感触も唇の瑞々しさも少し甘い唾液も真っ赤に染まる頬もすべてにわたしは恋をしているのだと気がついた。
わたしの心は決まったのだろうと自覚した。そして彼女からの接吻には驚きながらも歓喜の気持ちが生じていた。
真っ赤になって動かない、ぼおっとした彼女に代わって手を打つと微笑んでから、
「じゃあ、食べようか」
ぎこちない言い方になってしまった。わたしは唇を下でなぞって最後まで彼女を感じてその甘さを麦茶で流し込み、唐揚げをほおばった。