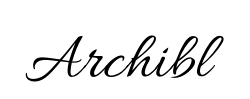後から聞いた話だが、あの時彼女がわたしにキスをしたのは、彼女がわたしのことを好きなのかというごく初期からの疑問を確かめるためと、サッカー部員が笠原さんがわたしのことを好きらしいと話しているのを聞いて嫉妬心を覚えたためらしい。
わたしは彼女の行動に思わず胸が締めつけられるように愛おしくなって、その時のキスで自覚した彼女への恋慕を煮えたぎるように胸に秘めていた。結局キスの後は恥ずかしくなってその時は解散してしまったが、しばらくして会ってからはその時のぎこちなさは消失していた。
女の子の部屋だ。甘い香りのする十畳はあるかもしれない広めの部屋を見回して、わたしは感想を抱いた。窓近くの天井にはエアコンが取りつけられ、部屋を冷却するために唸りを上げていた。壁には参考書や漫画、小説がごちゃ混ぜになった本棚や、その上にちょこんと載せられたぬいぐるみ類、空色のカーテン、淡いピンクの絨毯とその上の机、白いシーツのベッドにはピンク色のタオルケットと枕元にサメのぬいぐるみ。クローゼットは覗くわけにはいかないが、とにかくわたしの部屋とは似ても似つかないものだった。
「お待たせ、凜ちゃん」
彼女は片手でお盆をもってその上にお菓子とグラス、反対の手ではジュースのペットボトルを持ち上げていた。わたしは彼女からペットボトルを受け取ると、部屋の中央にある小さな机に載せると、彼女は伏せていたグラスの口を上に向けてジュースを注いでと言うようにこちらに差し出してきた。ジュースをとくとくと注ぐと二人で一気に飲み下し、お代わりを注いだ。
わたしはこの家に遊びに来るのは初めてではないが、今日は少し緊張していた。『私の家、今度誰もいない日があるんだけど泊まりに来ない?』と聞かれてお泊りの誘いに乗ったわけだが恋人からの誘いで、そういうことがあるのではないかと密かに期待したわたしは、何度かデートに行くうちに彼女はそういうことを考えなしに言い出すことが分かり、やはりわたしだけが期待しているのだろうかと少し落ち込んだ。
「部屋、綺麗にしてるんだね」
「イメージと違った?」
小悪魔的な笑みにどきりとすると、
「本当はもっと滅茶苦茶なんだけど、凜ちゃんがお泊りに来るから片つけたの。流石に足の踏み場もないっていうのは避けなきゃって。でも片つけてるうちにどんどん楽しくなっちゃったから、女の子っぽい部屋に模様替えしてみたの。どう、ドキドキした?」
「ドキドキしたし、今もしてる」
「またまた、同性の部屋なんてどれでも一緒でしょ? 凜ちゃんの部屋も似たようなものではないのかい?」
「わたしの部屋は絵具の臭いがして壁一面に絵が飾ってある。ベッド以外は下に段ボールを敷いて汚れないようにしてるかな」
「美術室みたい」
わたしは絵を描くのが好きだからそうなっているのだが、やっぱり深月ちゃんの今の部屋みたいにするのもありかな、なんて思い始めた。
わたしは彼女と話をするうちに、段々と彼女を好きな気持ちが抑えきれなくなった。初めの頃は女の子同士なんて変だと思ったりしたが、あの時のキス以来、彼女のことが脳裏にこびりついて離れない。
クーラーは点いているはずなのに熱に浮かされた感覚が収まらない。隣に座る彼女と触れている箇所が熱い。
わたしはついに我慢できなくなってしまった。
「深月ちゃん……」
近くにあったベッドに彼女をゆっくりと押し倒した。久しぶりのキスだ。彼女の上に馬乗りになってそれから上体を倒し、重なるような体勢になる。顔を両手で挟んで逃がさないようにしてから唇に触れた。抱きしめると彼女は全身を強張らせていたのを緩めた。
彼女の唇を舐めるとこじ開けてあの時のように舌を侵入させた。ぬるりとした唾液の感触にわたしはぞくぞくとした快感を覚えた。舌を絡めて互いの吐息を感じ、幸せな気分になっていた。口腔内のあらゆる場所を感じようと、わたしは彼女の頬を内側から舐めたり、歯を舌先で感じたりした。
一度唇を離すとわたしも彼女も少し息が荒いことに気がついて、
「深月ちゃん、わたし、もう」
伝えると呼応するように彼女は微笑んだ。
わたしは彼女との愛の表現を終えると、シャワーに向かった。彼女の頬はいまだに紅潮し、乱れた息はようやく整ってきたところだった。彼女は終始無抵抗で、わたしは少し調子に乗ってしまったかもしれないと反省をした。
シャワー後にすっかりぬるいオレンジジュースを飲むとぱたりとベッドに倒れこんだ。わたしたちは猛烈な睡魔に襲われて、まだ話していたいという思いが聞き届けられることなく、夕食も取らぬままに泥濘へと沈んで行った。