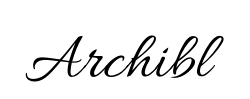「この間はありがとね。暑かったでしょ?」
学校が始まるのはもう少し先だ。しかし文化祭が夏休み明けにはあるからと大抵の生徒は準備のために学校に来ていた。暑いのは変わらない。わたしは先程までクラスの出し物のために絵を書いていた。休憩時間に頼まれていた絵を見せるために彼をあの空き教室へと連れ込んだのだ。
「時間がかかっちゃいました。人を描くのは意外と難しくて」
わたしは教室の壁に立てかけてあるキャンバスを縦向きにイーゼルに載せて見せた。
「これでどうでしょう」
まさしく瞬間を切り取った絵だった。濃い青色の空には薄い雲が寄り添うように存在しているが太陽を隠してくれはしない。対称的な位置には芝生が生えていて、その空と地の狭間には彼の姿があった。吸いつくようなドリブルが印象的だった。添えられたボールは自ら彼につき従うように見えた。瑞々しい筋肉はわたしの実力不足で完全には表現できなかったが、満足は行く出来映えだった。
彼は引き込まれるように絵を見ると、
「ありがとう。凄い、凄いよ」
感動したようにわたしに頷きかけると、
「キャンバス代と絵具代、いくらだった? 後は、アイスも奢るからこの絵、貰っちゃ駄目かな?」
わたしはただ練習になったし、何より最初から彼にあげるつもりだったから、
「ジュース奢ってくれたらそれで良いよ」
そう告げた。
彼は何度も嬉しそうに絵を見つめると、
「何がいい? スポーツ飲料か? 野菜ジュースか?」
「そうですね。スポーツ飲料で」
「じゃあ、自販機行って来る」
彼はあっという間に教室から出て行ってしまった。これで彼も後腐れないだろうなと思いながら、暑いからスポーツ飲料がぴったりだなんて思ったり、実は野菜ジュースのほうが高かったんじゃないかと若干の後悔をしてみたり。そんなこんな考えるうちに彼は戻って来た。
「お待たせしました」
「ありがとうございます」
わたしは差し出されたスポーツ飲料が冷えていることを喜びながら封を切って一口飲んだ。以外と喉が渇いていたことに気がついてごくごくと半分も飲んでしまった。
「もう一本買ってこようか?」
彼の問いかけに、
「大丈夫です。ありがとうございます」
ペットボトルを棚に載せるとビニール袋に絵を入れて差し出した。
「こうやって持って帰れば多分大丈夫です」
「ありがと」
彼は絵を受け取って、少し悩んだ末に壁に立てかけたように見えた。
「それで、他にも話があるんだけど……」
歯切れの悪い言葉に、わたしは言いたいことが分かったような気がした。もごもごと口の中で呟く彼に、わたしはイーゼルを畳みながら待った。それで、
「俺は前田凜さん。あなたのことが好きです。つき合ってくれませんか?」
ストレートな告白を受けた。深月ちゃんからのものよりも余程歯切れの良い告白だった。サッカー部の爽やかな彼らしい告白だと思った。それでもわたしは彼女のことを愛してしまっていた。だからその想いには応えられない。でも彼は分かってくれるだろう。別に好きな人がいるならと。だからわたしは、
「ごめんなさい」
わたしは続けた。
「別に好きな人がいるんです」
誰とは言っていないし秘密にしているから分からないだろう。だから男の子と勘違いしてくれるだろう。
彼は意外なほど冷静に、
「そっか」
残念そうに笑った。それからスマートフォンを取り出した。
「好きな人って、彼女?」
わたしの目の前に示された画像は深月ちゃんのものだった。
「どうしてって、顔してるね。一緒に応援来てくれたでしょ? その時、どうしても君と話したくて追いかけて行って弁当食べるのかなって思ったら君と彼女がキスしてるとこ見ちゃったんだ」
「見られちゃったんだ」
わたしは観念して認めた。
「どうして彼女なんだ? 女同士だなんて……」
「それでもわたしを好きなの?」
「こうして告白してるんだからそうだろうね」
彼はスマートフォンを操作してさらに次のものを見せた。
「これは……」
わたしが驚いていると、
「君が彼女にディープキスをしている動画だよ」
動画だった。わたしが彼女に口づけをしている、そのシーンが収められていた。
「どうして撮ったの?」
わたしが訊くと、
「その時は勢いで撮っただけだけどこれは使えるかなって」
耳を疑った。
「使えるって?」
「だからさ」
彼は嗜虐的に嗤った。
「君は俺とつき合うしかないんだよ。この動画が拡散されるかもしれなからね」
「卑怯者」
わたしは彼の印象ががらりと変わったのが分かった。彼は爽やかなんかじゃない。ただの圧倒的な屑だ。
「そんな脅しにわたしが屈すると思いますか?」
「思うね。だって、この動画が拡散されたら君の好きな彼女にも迷惑かかっちゃうでしょ? 君のせいで」
「いいえ、あなたのせいです。だって拡散しなければ彼女にも迷惑をかけることなんてないんですから。わたしがどうこうしないせいだなんて責任逃れをするような言い方は止めて下さいよ。わたしはあなたの脅しには屈しませんし、つき合いもしません。すべてはあなたのせいです。何が起ころうとも」
わたしは彼を睨みつけると彼は少したじろいだ。
「分かった」
彼は一歩下がると、先程までの温和で爽やかな彼の面影なんて微塵も残さずに冷酷に嗤ってから、眼光を冷たく突き刺してきた。
「そっか。そういう態度とるんだ?」
彼はスマートフォンをポケットに仕舞うと、深く溜息を吐いた。
「じゃあ、さようならだね。きっと君と彼女の噂は全校に知れ渡るよ」
「卑怯者」
今度は小さく呟くことしかできなかった。
「卑怯者だって? これは恋の駆け引きだよ」
「こんなの恋の駆け引きでも何でもないですよ。ただの卑怯者がフラれてわるあがきしただけのことでしょうね」
「お前くらいの女なんて他にもいるんだよ。俺とつき合いたい女もな。コケにされたお礼はそのうちさせて貰うからな」
呻るように低く言い放つ。
「可哀想な人」
わたしの言葉に彼はついに怒りに支配されたように、わたしが描いた絵を踏み躙った。
「こんなもの!」
上から踏みつけられて靴の裏の汚れがつ着して、彼のことを描いた絵は汚されていったのを見つめるしかなかった。彼に時間を割いた自分が馬鹿だった。そして人などそう簡単に信用してはいけない生き物だと、再認識した。
「覚えていろ」
彼はそれから出て行った。恐怖を感じる。明日から、クラスでも奇異視線に耐えなければならない。それどころか、彼女までその視線にさらされてしまう。
わたしは彼とつき合って彼女を守ることができればよかったのかもしれない、自分の気持ちに蓋をして我慢すれば彼女が守られたかもしれない。
それでもわたしは彼に屈することはしなかった。彼女のことを想う度に罪悪感にさいなまれるだろう。彼とつき合っても、つき合わなくてもきっと。
わたしは教室に戻る気分にはなれず、だからと言ってこの教室にいる気分にもなれず、どうしようもないままに屋上へと向かった。普段は施錠されていて出られないが、文化祭の準備期間は垂れ幕の準備や天文部の夜間星観察のために常時開け放されていて、誰もいない屋上というわけにはいかなかったがフェンスの横で外を眺めた。
誰もわたしを気にしない。
わたしも誰も気にしない。
それだけで良かった。
「はぁ」
わたしは溜息を吐いた。深い溜息だった。体の中のもやもやをすべて吐き出してしまいたかった。しばらくそうしていると先生が近づいてくるのが見えて逃げ出すように屋上を出た。
このまま時が止まれば良いのにと思った。
彼女に話さないわけにもいかず、わたしは彼女に空き教室ではないどこかで会おうと告げていた。それならばと言われたのは、あまり生徒が通らない体育館と校舎の間のスペース。急いでいる移動教室では使う人もいるが、この時間には誰も通らないだろう。
「ごめんね。こんなことになって」
わたしは出会い頭にそう言った。
「気にしないで。私からしたんだし」
彼女は気にしない素振りで言った。しかし、隠しきれていない後悔が遠くを見る目からはうかがい知れた。わたしは確信していた。この間のお泊りの日にしたときから彼女はわたしではない誰かを想っているのではないかと。
だからこそ噂が広まるのが怖いのだろう。わたしではない誰かに知られるのが。しかしわたしには嫉妬の炎も怨嗟の言葉も出なかった。彼女に最初に、好きな人ができたら別れようといったのは私なのだから。
「彼に絵を描いて欲しいって頼まれたとき、断ればよかった」
後悔が口を衝いて出た。
「私も彼がそんな人だなんて思いもよらなかったから……」
彼女の言葉はどこか上の空だった。わたしは続けて言った。
「深月ちゃん、好きな人ができたでしょ?」
彼女はビクンと肩を震わせた。ただそれから何も言わない。わたしは言葉を紡ぐ。
「良いよ。分かってるから。わたしと深月ちゃんは恋人関係。でも、最初に深月ちゃんが女の子が好きなのか分からないって言って、わたしも恋とか分からないって言って、それで仮の恋人になって、他に好きな人ができたら別れようって話だったんだから。今、別に好きな人がいるのならわたしとのことは青春時代のひと夏の思い出ってことにしてくれても良いんだから」
わたしはなかったことにだけはされたくなかった。わたしの初恋を。だから思い出という言葉にすべてを乗せて、封じ込めて、それでも心のどこかには残して欲しかった。
「大丈夫。何かあったらわたしが何とかするから」
わたしはその姿を胸に刻みつけた。たとえわかれることになっても、それでも彼女とのことは忘れたくなかった。
「あの男の子でしょ? 最近目で追ってることが多い、仲良くなってる男の子」
彼女はもう反応もしなかったがわたしには分かった。
最初からわたしだけが想っていたのかもしれない。デートをしてキスをして身体を重ねて。どこまで本気だったんだろう。彼女はいつからわたしに心惹かれていなかったことに気がついてしまっていたのだろう。
わたしは彼女に背を向けると下足箱に向かった。