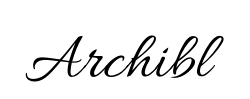わたしの元に届いたのは一件のメールだった。わたしのメールアドレスを知っている人なんて限られている。すぐに彼女からだと分かった。
タイトルは『ごめん』。わたしはメールを破棄しようとしたがちらりと中を見てから考えようと思い直した。
本文には『私のことまで全部凜ちゃんに押しつけてごめん。どうしても伝えたくて、凜ちゃんが傷つくのかもしれないのも全部分かってて、酷いことを言うよ』そうあった。
わたしはスクロールして続きを読んだ、
『私が好きになったのは、前に凜ちゃんが言ったあの男の子。私はあの時凜ちゃんに、それなら好きな人と幸せになってよって言われたから思い切って彼に告白したの。それで彼も私のこと好きだったらしくてつき合えることになったの。彼は私が凜ちゃんに脅されていたって信じてるの。そんなことないのにね。卑怯な私は彼に本当のことを言えない。許してなんて言わない。だけどちゃんと幸せだから』
どうでも良かった。わたしのことなんてどうでも良かった。わたしの好きな彼女が幸せならばそれでどうでも良かった。
『お幸せに』
乾いた唇の隙間から漏らすようにつぶやいた。そして文面にした。メールの題名には『さようなら』とつけて送った。
頬を流れる涙が妙に多かった。ひとりしかいない教室に嗚咽を漏らしながら、初めて失恋したことを実感した。
目の前にあるのは真っ白なキャンバス。イーゼルにいつものように立てかけるとパレットに絵具を絞り出していた。混ぜることもなく、絞り出したそのまま色だった。今回はそれに多めに水分を含ませていた。
わたしと彼女が分かれてから時間が経ち秋に差し掛かろうとしていた。既に教室は快適な温度になっており、今度は寒くなるのだろうと確信した。
今まではずっとひとりだった。そこから時々、二人や一人になって、それからひとりに戻った。元々誰とも親しくなかったのだ。平気だ。
言い聞かせるが、彼女のいた短い時間は濃密で、そこには埋めることができない喪失感が横たわっていた。
わたしには氷柱の視線が刺さることはなくなったが、もはや誰もわたしに関わろうとはしなかった。聞こえていないと思ってか、それとも聞こえているのを分かってか知らないが、わたしのことをひどくこきおろしていた。
わたしの前にはキャンバスがあり、手元には絵筆と絵具がある。これは間違いないことだ。
わたしは風景画を描く気分になれないで、あれから感情のままに筆をはしらせることが多くなった。
水気の多い絵具を叩きつけるようにキャンバスにぶつける。白の上に赤や青や黄色や緑や紫や橙色やとにかく無茶苦茶に、絵と呼べるのかも分からないが空白を埋めるように重ねて、まき散らしていた。
わたしは彼女が好きだ。その気持ちは今も変わらないどころか、以前よりもより強く深くなっている。自分の心には嘘を吐けなかった。
だからこそ彼女の幸せを願うのだ。
斜陽が教室に射した。
黒いショートカットが揺れる。鈴の転がるような朗らかな声で笑う。柔らかな手が触れる。美しい唇がある。大きな目が笑う。
彼女は既にわたしのものではないし、今だって外を見るとつき合い始めた彼と手を繋いで親しげに談笑して、校門から出るのが見える。
彼女はわたしだけのものだった。
でももう二度と会わない。わたしの大好きな人。
筆に想いが乗る。気持ちが乗る。感情の渦が乗る。
この恋に終わりを与えたい。忘れたい。本当は最初からなかったことにしたい。そうすれば誰も愛おしまずに済んだ。ここから離れて、いつかまた恋をして、愛を芽生えさせて、喧嘩して仲直りして、それから自分を再発見して。
想い想われたい。
絵具を散らす。
「ぐちゃぐちゃになっちゃった」
ひとりで笑うともう手を加えないために絵にタイトルをつける。たくさんの色の雫が散らされたその絵。
この絵にタイトルをつけるなら。滅茶苦茶な感情に終止符を打つのなら……。
「アネモネ」
わたしは初恋を終わらせた。