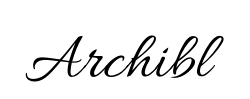第一節
「白日の下にさらされたよ、この俺の演技が見破られてな!」
梨乃と出会った翌日、晴れでも雨でもない、曇り空と同じような顔をしながら、唯人は亮太に耳打ちしていた。最後の『な!』に力が入って声量が上がり、頭をはたかれたの致し方ないことだと唯人は納得した。
昼休みである。教室にはクラスメイト他にもその友人や部活仲間が集まり、がやがやとやかましかった。他のクラスに人が少ないということもないが、この混雑は唯人と話す機会をうかがう女生徒が一割以上いることを察して、唯人はもちろん、亮太もげんなりしていた。
亮太の前には食事がない。昨日の仲直りの印に、香織が弁当を製作してきてくれると言って喜んでいた。馬鹿力もでるが繊細な力加減も元ピアニストらしく使いこなしている。彼女が料理上手なのは唯人も認めるところだ。もっと言えば、教えたのも唯人である。
「誰にバレたんだよ、本性というか雑な人間性というか」
「それが、昨日初めて会った人間なんだよ」
亮太は目を瞠る。
「初見さんに見破られたの? あの演技。いやあ、あれって結構高度なもんだと思っていたんだが、そうでもなかったらしいな。ところで誰に見抜かれたんだ?」
「俺も結構高度だと思う。ただ相手が悪かっただけかもしれない。刑部梨乃だよ。昨日ちょっと話しただけでバレた」
ますます驚きを隠せない様子で、
「そもそもお前が彼女と話したのが驚きなんだが?」
「そうよね、驚きだわ」
ぎょっとする唯人と亮太にかまわず、いつの間にか横にいた香織は続けた。
「面白そうだから別の場所で話しましょうよ。いいでしょ?」
「まあ構わないけど。先に購買にパン買いに行くぞ」
唯人は財布とスマホをポケットに押し込んで立ち上がった。
「ゆい君の分もあるわよ、お弁当。自分で作ったほうが上手だろうけど、どうせないだろうと思ってついでに作ってきてあげたのよ」
「そりゃ悪いな」
「香織、俺だけに手作り弁当を頼むよ。後で唯人に見せびらかそうと思ってたのに」
「じゃあ、亮太の分はないわね。そもそも私に料理教えたのゆい君だし。師匠として味見を頼んだだけなのに狭量ね」
そう言われて亮太はすぐに掌を返した。
「唯人と一緒にお弁当なんて嬉しいな。だからわたくしめにもどうかお恵みください」
見事なもんだと思いながら、亮太を見やる。たかが弁当一つでここまで態度が違うとは。
唯人は、
「じゃあ、場所を移そうか」
香織について教室を後にした。
弁当を食べるためによくここまでしたもんだ。そう思いながら空き教室を見る。 何か理由をつけて空き教室のカギを拝借してきた香織には尊敬の念が堪えない。何かというと教師をこき使い、さらには施設のカギまで借りられるなんてどれだけ神経が図太いのだろうか。
「何か失礼なこと考えてない?」
エスパー並みに鋭い第六感が鋭い香織にびくつきながらもテーブルクロスを敷いて弁当を並べるのを手伝った。
「いや、香織は準備がいいなと思っただけだ」
「どうだか?」
亮太はそのやり取りの間に椅子を並べていた。
「あ、そうそう、浩志と春香も来るって言ってたよ」
香織の言葉に、
「あいつら、学校に来てたのか」
結構失礼なことを亮太が口にした。あいつらとて生徒。もちろん出席日数不足で留年なんて言う不名誉なことは避けたいだろうに。最低限は出ているに決まっている。
唯人は二人に久しぶりに会う気がしていた。しかしそれほど久しぶりというわけでもない。春休みには結構頻繁に会っていたのだから。
「初めのほうに日数稼ぎだってさ。去年も後半来てないこと多かったよね」
香織の言葉に二人で同意する。
「二人とも兼ね稼いでるからなぁ。春休みも結構働いてたし。ちなみに唯人も学校来なくても十分勉強してると思うけどな」
亮太の言葉に、
「俺は内申点稼ぎだ。大学の推薦で良いとこ行きたいし。そしたら他の奴が必死に勉強してるときに遊んでいられるだろ?」
「うわぁ」
げんなりした顔で見られて、唯人は心外だと思う。楽してよい学校を出てこそだ、などと思う。どうせ昔から目指していた医者にでもなるのだろうと心の底ではうっすらと考えていた。もう勉強する意味なんてほとんど考えていないのに、医者の夢は別にかなえたくもないのにそこに縛り付けられたままだ。父親は大学の費用は出してくれるだろう。そう考えていた。
扉の開く音がした。それから浩志と春香が首を出した。
「到着!」
浩志はジャンプして入ってきた。無邪気な笑顔だ。お前はドリブル中のバスケットボールかとでも問いたくなるような変なはね方で近づいてきた。飛び跳ねるたびに髪が浮き上がる。髪を切りに行けと言って行ったためしなんかない。唯人はあきらめていた。
「来たよー」
春香はけだるそうにこれまた長い髪を寝ぐせだらけで入ってきた。
「寝癖くらい直してから来なさいよ」
香織が叱るが、
「かおちゃんが直してくれるからいいよ。昨日から一時間しか寝てないし、髪直す時間あったら寝たいー」
身だしなみに人並み以上に興味がない彼女は、童顔で可愛らしい顔立ちだが、どうも浩志と付き合っているとみられているのと、そもそも授業以外は寝ている、授業中も寝ているので誰も恋人にするための話すチャンスがそもそもないらしい。
二人が席に着くと弁当箱を開けた。そもそも全員分あるらしい。唯人は道理でさっき並べたときにやけに弁当箱が大きい、というかタッパーだったわけだと納得する。最初から場所を変えるつもりだったんだなと、だから鍵なんて持ってたんだなと。
「おいしそうなサンドウィッチだねー」
眠そうにしていた春香は食欲の前には目を覚まさざるを得ないらしく、一番に昼食にかぶりついた。続いて一同は一斉に食べ始めた。ベーコンの味とからしマヨネーズ、レタスがよく合う。口の中を心地よい風味が走り抜けて行く。すきっ腹には十分な威力を発揮した。
「さっきの話の続きは?」
「さっきの話?」
浩志が香織の問いに食いついた。
「そう、さっき唯人と亮太がクラスで話してたの。唯人と刑部さんが話したって」
「へぇー、あの刑部と唯人がねぇ。あ、まさかテストで負けた腹いせになんか言ったの? あの人、そもそも人と話してない印象なんだけど」
「お前も人と話してないだろが。というか学校にも来てないだろうが」
亮太が呆れると、
「失敬な。今年はまだ全部来てるよ!」
浩志の言葉に今度は全員が驚いた。唯人は、
「来てるか来てないか論争は今度にして、とにかく、俺からじゃなくて刑部から話しかけられたんだよ。それから腹いせで話しかけねぇよ。するなら無視だ」
「それのほうがひどいな」
浩志は、されたことのある人がいるのか、という風に同情の表情を見せていた。唯人は容赦なく切り捨てる、いくら外聞が良くても気に入らない時はバッサリと。それを知る人間だからこそ同情したのだ。そこまでになるにはよほどのことをしなければならない。
唯人が過去にバレンタインのチョコレートを受け取った時に爪が入っていて、その犯人がされたくらいしか思い当たらない。それが原因で二度と知らない人間やクラスメイトからのチョコレートを受け取らなくなったことは、浩志の記憶に残っている。
「そんなことより、話の内容は何だったのー? まさか、愛の告白とかー。いやー、それだったら面白すぎますなー」
春香はいつの間に口に押し込んだサンドウィッチを咀嚼しつくしていたらしく話に割って入ってきた。
「いや、そんなわけないだろ。さっき刑部は人に話しかけること自体ほとんどないのに、初対面の相手に告白とか、ありえないだろ。多分」
浩志の言葉に唯人は、
「多分ってなんだよ。ないよ、そんなこと。亮太が話してた通り変人奇人の類だったんだよ。
何とも形容しがたい人間だった。なぜ生きるのか、って問われたよ。そもそもなぜ生きるかなんか知るはずないだろう。というか問い自体が哲学臭いし、中二病のやつが問いかけてきそうな内容じゃないか。眼帯して、なんかわけのわからん杖とかもって、あとは包帯ぐるぐる巻きの腕と足、極めつけはカラーコンタクト入れて言いそうじゃないか」
ここまで一息で話してから唯人は、
「でも、なんか茶化せない雰囲気っていうか、話させられる雰囲気っていうか、だから問いと問い方のギャップにちょっとばかりびっくりしてさ」
春香は、興味津々の様子で目を見開いた。なんとなくイラストの役に立ちそうだとおもったのか、紙とペンを用意している。これは絶対後で、どこでどんな風にとか、あとは事実を捻じ曲げてそれっぽく話せとか言われるんだろうなと、唯人はため息をついた。
そして春香は、
「そこでこう答えたわけだねー。それは、君とこの場で出会うためさ。バサッ、キリッ。みたいな感じでー。そして二人は晴れて前世からの因縁の再開を果たしたわけなんだねー」
「やかましいわ。そんなことしてない。ただ、人は生かされて生きてる、死ねないから生きてるって答えたんだよ。なんか今思えばスルーして帰ればよかったと後悔してる、恥ずかしい答えだし」
春香はにやにやしながら、
「中二病っぽい返し、ありがとうございますー。きっと、この後世界は滅びて二人だけになって、ノアの箱舟とか、最後の審判を生き残ったとか、そういう展開が待ってるわけだねー」
「いや、お前らも死んでるじゃないか」
「いいのだよー。題材になりそうだしー。ホームページに載せとくねー、それっぽいのー」
「それで」
亮太が話した。
「それでその答えに満足したのか? 彼女は」
「満足したのかは知らないけど、自己紹介されて、面白いとか言って去っていったよ。これから絡まれそうな予感がすごいんだけど」
香織は、憐れむような眼で見ると、
「そしたらゆい君はこれから、例の変人さんと噂になるわけだね。これは面白い予感が……」
「フラグ立てるのやめい。そんなことになったら全員巻き込んでやる」
その言葉に浩志は、
「多分、仮に巻き込もうとしても、彼女はお前以外をいない者扱いするだろうな。いや、もしくは余計に絡まれるか。どっちにしろ、そんなことになろうものなら僕は休むからいいよ」
唯人はもう疲れてしまっていた。変人奇人はこいつらも同じだった。そして全員知らん顔しそうだな、巻き込まれるまでは、と考えながら唯人は時計を見た。昼の休憩時間はあと十分だ。
いつの間にか食事は終わり、片付ける。
「では、散開!」
「どこの軍だよ」
くだらない会話のうちに解散する。唯人は亮太と教室に戻ることにした。
教室に戻ると、いつも以上に囁き合う声が聞こえた。何か面白い出来事でもあったのか、と思いながら、唯人は亮太と顔を見合わせた。すでに猫の皮をかぶった唯人は入り口付近にいたクラスメイトに声をかけた。
「何かありましたか?」
彼女はハッとすると、
「いや、遠野さんに会いに来た方がいらっしゃいまして……」
何とも歯切れの悪い答えに違和感を覚えながらも、彼女の目線の先にある自分の席に目をやった。話題の刑部だった。亮太とぎょっとした顔を合わせると仕方なく自分の席に歩みを進めた。
「やっと来たか」
待ちくたびれたとばかりに、唯人の席から立ちあがる。伏せていたまつ毛は持ち上げられ、瞳は唯人をとらえていた。逃げられない草食動物の気持ちに陥りながらも、なんとか返事をする。
「私に何か御用ですか?」
昨日の会話で話し方についてひと悶着あったことを思い出して、どうか突っ込んでくれるなよ、と祈りながら目をやると、幸いにしてなんの言及もなかった。
「これを」
メモ用紙だった。ノートの切れ端には何か文字が書いてあるが、閉じられていて中は読めない。
「これは?」
「とりあえず受け取れ。そしてちゃんと中を見ろ。私の用は以上だ。では、またな」
メモを渡すと長い髪を吹雪のようになびかせながら去っていった。唖然とする教室の中、唯人は何事もなかったかのように席に着いた。
「どういうことだよ!」
亮太は耳元で囁きかけた。
「そんなこと知るかよ。見るように釘刺されたし、見ないわけにもいかないんだろうな。さっきフラグ立てた香織にはあとで仕返ししてやろう。筆箱にゴキブリ人形仕込んでやる」
「またしょうもないこと考えて。あとでキャメルクラッチ食らっても知らねぇぞ」
「あいつ、元プロレスラーじゃなくてピアニストだよな。なんでそんなに技使えるんだよ?」
「バックドロップも使えるらしい」
二人は投げやりな会話をしつつも、メモの内容が気になっていた。周囲は素知らぬフリをしつつも内心では興味津々といった感じで視線を投げかけていた。ここで読まないのも何とも気持ち悪いし、捨てて拾われるのもダメだろうな、とあきらめて中を見ることにした。
マスキングテープで二つ折りの真ん中を止められたメモ用紙の中にはただ一言、暗号のようなものが書かれていた。
『78515458 15851 53566046 7966』
唯人は亮太に数字の羅列を見せる。
「なんだこれ? 字の羅列となると何か意味はありそうだけどなぁ」
「全然分からん」
二人は顔を突き合わせて悩んだが、結論が出るはずもなくあきらめた。
亮太は無責任にも、
「数字書いてあるし、とりあえず浩志に送ったら教えてくれるんじゃない?」
「無責任だな、おい」
唯人はこんなことで悩んでも一切意味がないだろうと思い、言われたとおりに浩志に数字を送った。
「とりあえず放課後までに何とかしてくれるだろう、寝てなければ」
「そうだな」
二人は授業の開始時間になると席に戻った。
ようやく午後の授業も終了して、放課後の談笑が聞こえるようになる。スマートフォンの通知を見た唯人は、浩志からの返信があったことを見つけた。とりあえず中を見ると、端的な本文が表示された。
「JIS半角。ほうかこ 1こう おくしょ まつ」
解読に成功したらしい本文に驚いた。そして浩志に送って正解だと唯人は思った。
亮太が近づいてきて、
「解読は?」
「功したみたいだ。誰が文字コードなんて知ってるんだよ」
そういいながら画面を見せる。
「万が一拾われてもいいように、楽に解読できないようにしたわけだ」
「いや、これは俺も解読できてないから。こんなのは事前に言っておいてもらわないと困るだろ」
「お前は分かると信じてたんじゃないか?」
「事実として解読は依頼したがな」
興味を失ったような亮太が、再び目を輝かせる。
「おい、これって……」
声を潜めて、
「これって『放課後に一号館の屋上で待つ』ってことか? やっぱり噂になるようなことが起きるんじゃ」
「面倒だよな。読めなかったフリして行かないでおこうかな」
「絶対後で面倒なことになる予感しかないけど、唯人がそれでいいなら別にいいんじゃないか?」
「いやだね。後での面倒なんて。そして、行っても面倒の予感しかない絶望」
唯人の曇った表情を見て亮太は、
「とりあえず注目されてるから普通に帰るフリに付き合うから行ってみれば?」
「他人事だな、おい」
「他人事だからな」
唯人は観念して、行くことに決める。ただでさえ注目の的が、人を呼び出したとなったらどうなることか考え頭痛がした。
「誰にもバレてないのね」
「誰にもではないし、その相手には俺がバラした」
刑部は意外そうな顔をした。
「学校でモテモテという噂のあなたがバラしたの? 誰も来ていないところを見ると、信頼してる相手なのか」
「ついでに言うと、暗号解読者でもあったりする」
唯人は亮太のことは黙っておいたが、別に他意はないと考える。
「そもそもあんなの、普段使わない人間が読めるわけないだろうに」
「基本教養じゃないのか。今度からポケベル方式で呼び出そうかしらね」
唯人は、『ポケベル方式も知らんわ!』と怒鳴りそうになりながらも、そこは耐えきり理由を聞くことにした。春香と似たような空気を感じたのだ。何か言っても話を聞かず自分の言いたいことだけ言いそうな気がした。
「そもそも何の用だ? 使用禁止の張り紙を見てびくびくしながら来たんだぞ。鍵壊れてる屋上なんて早く修理してしまえ!」
そんな叫びは無視するかのように、唯人をちょいちょいと手招きすると屋上の縁のフェンスから校庭と庭園を見下ろす。
「人間って愚かだよ」
ぞんざいな口調で話す。
「人間って本当に愚かだよ。愛なんて曖昧なものに取りつかれて、さ。不確かで形のないものなんて信じていいはずがない」
視線の先を見やると、ちょうど木の陰でキスを交わすカップルがいた。学校でのキスは、確かに隠れてすることが多いと聞くが、家に帰ってからしろ、と唯人は思った。他人に実害がないため何とも言えないし、校則で男女交際の禁止がされているわけでもない。
唯人は、刑部の言葉に一部の同意をした。愛のような曖昧模糊としたものに縋りつくのは確かに愚かだと思った。
「形のないものを信じられないっていうのは同意するけど、何か関係が?」
刑部は振り返る。白の髪に陽光を浴びながら、
「学校では優等生を演じているあなたを、ここに呼び出すのは心苦しいばかりだったのけれど……」
懇願に似た空気を感じた。
「……私の恋人になって」
衝撃だった。恋人を否定していた刑部の告白が。
「どう考えてもおかしいでしょ。今の流れからするとどう考えても告白に結びつかないだろうが?」
「結びつかないだろうね」
「じゃあ、なんで?」
刑部は少し考える。自分の矛盾には最初から気が付いていたその上で、告白なのだろう。告白というか懇願かもしれない。
「似た者同士だから、だろうね」
「どういう意味?」
唯人は戸惑った。
「人を信用していない。もちろん数人は信頼できても交友関係は広げるつもりがない。曖昧な感情を許していない。似ているじゃないか」
「それと恋人とはどうつながる? 全く関係ないし、今の考えからしたら俺が誰とも付き合うつもりないのも分かってるだろうに」
「そうだろうね。だから、提案する。次のテストで私が勝ったら恋人になってほしい。
その代わり、同点か負けたら二度と関わり合いを持たないことにする。別にあなたのことは面白いとは思うけど、好きとかそう言うのではなくてただの虫除けって感じだし。良いじゃないか、お互い鬱陶しいだろう? 何の生産性もない人間に取り巻かれて」
「それじゃあ、お前に有利すぎないか? 俺は全国一位じゃあないぞ」
「負けを認めてもいいんだよ、最初から」
「受けないという可能性は考えないのか?」
「受けなかったら勝手に付き合ってることにして周りの羽虫に言いふらすから。あとは新聞部に乱暴されたうえで捨てられたって」
唯人はもうどうとでもなれという感じで、あきらめた。
「分かったから言いふらすな。嘘も吐くな。約束は守れよ」
唯人は次のテストまでにきちんと勉強しておかないと満点で並べない、と思った。もうすでに満点で並ぶ以外に方法がないことを悟り、ため息をついた。
第二節
暗い部屋で一人の男が腕立て伏せをしていた。亮太は全身に汗を纏っていた。ひたすらに、無心になるために行っていた行為だった。
身体を鍛えるのは趣味だった。いつからだったろうか筋トレにはまったのは。自分を落ち着かせるには独りの時間は何かしていなければ落ち着かなかった。
「はぁ、はぁ……」
息が上がっているのは自覚していた。ここ最近は独りになる時間は少なかった。いつでも香織が傍にいた。夜寝る時と朝起きた時くらいなものだった。孤独がこんなにも重苦しいものだったなんて、知らなかった。というよりはすっかり忘れてしまっていた。
「いつもなら、香織と愛し合っていた時間か……」
つい先日のことなのにベッドでセックスをしたのがだいぶ昔な気がした。別に亮太はセックスがしたくて香織と一緒にいるわけではない。自分たちを満足させて落ち着かせて、それから愛を感じられるのがセックスだったというだけなのだ。
しかし、先日別れようと言われて、別れてからも学校の距離は変わらなくて、それで弁当もごちそうしてくれて、それでも放課後一緒にいられない。このことに亮太は胸を締め付けられるような思いをしていた。
自分では十分愛していた。そして香織もそうだったのだと思う。たまに不安になる時があった。そもそも自分たちはきちんとした恋人なのだろうか。互いの欲求を満たすだけの関係だったのではないか。
香織が本当は自分でなくてもいいのかもしれないことは知っていた。別に唯人でも浩志でもそこらにいるおじさんでもなんでも誰でもセックスさえできればいいのかもしれない。
求められるたびにそんな気がしていた。自分でなくても良い、一方的に自分が彼女に愛を求めていて、それに気まぐれで答えていてくれたのではないか。そう考えるとなおのこと辛い。
自分には香織しかいなくても香織はそう思っていないのかもしれない。
「はぁ、はぁ……」
苛立ちと戸惑いと、後悔と憤怒と嫉妬と寂寥と。様々な感情がごちゃ混ぜになっている。
自分がどれだけ彼女に、香織に依存していたのか。よく分かった。
「だからこそ、別れようって、一回別れようって言ったのだろうな」
知っていた。依存していることを。だからこそその提案に乗ったのだ。もちろん断ればきっと今回のことはなかっただろう。そしてこのまま自分たちが分からないままずるずると最後まで、きっと結婚までしたのかもしれない。
「何が愛していた、だよ」
自分から提案すべきだった。自分のことをどう思っているのか、自分がどう思っているのかを確認するために。本当に彼女を好きなのならば。
「ただの高校生が何で愛なんて言葉を使ったんだろうな。薄っぺらい、中身のない、どうしようもない、崩れ落ちそうな、愛って言葉を」
腕立てを終えると懸垂を始めることにした。アニメのキャラクターで左手一本で懸垂するような人もいるが、あくまでもフィクションだと分かっている。過去に似たことをしようとして肩がちぎれそうになったことを思い出した。
部屋にある懸垂器具に両手で摑まり、身体を引き上げていく。
「いちっ」
どんどんと自分が無心になって行くのが分かる。
「にっ」
自分は結局何かして気を紛らわせて、そうでもなければどうかなってしまうほどの弱い人間だったのだ。愛を感じたい、愛されたい。気持ちに嘘はない。だが、それは誰でも良いのではないか。別に彼女でなくとも……。
ぐるぐる回る思考を押さえつけるようにして懸垂を続けた。
「さんっ」
冷水のシャワーを浴びると汗が流れるのを感じた。亮太は自分の思考が身体とともに冷えて行くのが感じられた。
「まだまだ、だな」
唯人と違って完璧に演じられていない。自分は冷静ではない人間を、言わばクラスに一人はいるようなムードメーカーと言うか愉快な人間と言うか、それを演じていた。自分には愛が足りない。だからこそ本性は冷酷なものだと思っていた。
タオルで水滴を全てふき取り下着を付けた。独りしかいない部屋。両親はいない。自分には初めから両親などいなかった。そう思っていた。両親は離婚している。自分が小学生に上がる前から別居していた。そこには愛なんてなくて、与えられるはずの愛なんて子供には回ってこない。
会うたびにいらないもの、余計なモノ扱いを視線でされて、自分がそういう存在なんだと思っていた。だからこそ、初めて与えられた香織からの愛が心地よくて、依存して、どろどろに執着して、気持ち悪い。
「はぁ……」
溜息を吐いて、冷蔵庫から出したプロテインを飲み干した。
第三節
無表情に、無感情に、効率的に、延々と指を動かして行く。自分にはこれくらいしかないから。できることはこれだけだから。浩志は感情のない目で画面を凝視していた。
黒い画面に色とりどりのコードが電飾のように輝く。コードを書いていた。自分の思うとおりになるコンピュータは良い。信頼できるし、何より見ていて気持ちが良い。感情に左右されることなんてない。
リファクタリングをすれば限界まで効率を上げて美しい文字が連ねられる。そして他人が読みやすいコードが作られる。初期のオペレーティングシステムカーネルは約一万行で実装されていたらしい。それが分かれば全てが制御できていた。現在では二千万行を軽く超えているためその限りではないが、それでも読めれば全てが分かる。
人間は読めない。思考が脳の電気信号の類であるとしても、人間の基本的なカーネル的なものはない。だからこそ何も分からない。
プログラムの依頼が来るのは、自分がある程度コード実装や言語に詳しいからだと分かっている。そして年に一千万円近く稼いでいる。
簡単なことだ。誰もができることだ。月に三十万の依頼を三つもこなせば良い。一週間に一つの依頼で事足りる。しかし、そうしている人間は少ない。そして、できる人間から毟り取ろうとする。
人間なんか信用ならない。親も親戚も誰も彼もが自分から、小学生の頃から毟り取ろうとしてきた。唯一母方の祖父母だけが自分をただの孫として見てくれていた。だからこそ人を完全に信用しないまでには至っていない。そして春香も唯人も亮太も香織もただの幼馴染としてみてくれる。
人の金に関心がないどころか、自分でプロとして金を稼いでいる。だからこそ、自分を純粋に自分としてみてくれるような気がしていた。それでも、彼女が男性が怖いという事情は知っている。自分がその窮地に接したのだから。だからこそ、自分が思っている通りに距離を詰められない。
仕方のないことだろうが、どうしても彼女のペースを待つ必要がある。彼女に思いを告げることはできない。彼女がもし自分のことを好きになってくれたならばどれだけ嬉しいことだろうか。浩志は思った。
「今回の依頼も面白みがないものばかりだ」
一週間前からの依頼は一応の完成を見た。自分で作ればすぐにできるが依頼すれば三十万も取られるというものだ。できる人間は儲け、できない人間は搾取される。これが現実だ。
クラウド上にバックアップを上げるとパソコンの電源を落とした。
「少し前の唯人に頼まれたメールAIのほうがよっぽど面白かった」
一人で呟いた。今は一人暮らしだ。家にいると金を盗られる。だから、祖父母に頼んでマンションを借りてもらって一人で暮らしている。
金はこうも人を狂わせるのか。
分からないな。プログラムのように簡潔だったら良いのに。何度思ったことか。
そう思いながらスマートフォンを見てメールを送った。
「これからそっちに行っても良いか? 続きの話をしたいから」
すぐに返信が来る。
「いいよ。お菓子よろしく」
はいはい、と心中で返事を返しながら部屋を出た。外はすっかり暗くなっていて、近くのコンビニの明かりが煌々と見えた。
「お邪魔します」
玄関から入ると春香が出迎えてくれた。
「いらっしゃいー。お菓子―」
「ほらよ」
ポテトチップスを差し出すと、靴を脱いで遥かの部屋へと向かった。
「お邪魔しますね、おばさん」
途中で会った春香の母親に挨拶をするといらっしゃいと言われる。いつものことで、浩志が遅くに来ることに慣れているのだ。そしてある程度信頼しているのだろう。
春香が恐怖心が少ない男性の友人だから、少しでも娘の克服というか治療というか、それに協力してくれたら良いという思いだろう。
不思議と、彼女は男性に一定以上近づくのも触られるのも駄目なはずなのに浩志へ一方的に触るのは大丈夫なのだ。だからこそ部屋にも入れるし、近くにもいられる。
「続きの話ってゲームだよねー。まだ構想が決まってないからさー」
「だろうと思ったよ。でも僕も早く完成させて発表させたいから協力できたらな、なんて思ってさ。どこが気に入らないとか、どこの展開をどうするとか。一人より二人の方がアイデアも出るかもしれないし」
いつの間にか準備されていた紙皿にポテトチップスを出して割り箸でつまんで口に入れる春香を横目に浩志はジュースをコップに注いだ。
「そうだねー。結論としては最終章では告白させたいよねー。天使側からかプレイヤー側からかは分からないけどー。それで告白シーンの先は描かないで想像にお任せってするか、ダウンロードしてくれた人にホームページで続きの展開についてアンケートを取ってそれを後から追加コンテンツとして増やしておくとかー。そんな感じでさー」
「確かにそれは良いかもしれないね。これは商用コンテンツじゃないから適当でも文句を言われる筋合いはないしね。完成版を追加グラフィック付きで販売に出すとかができれば良いかもしれない」
「そーだねー」
浩志は春香と話しているのが楽しいと感じていた。そして春香も楽しそうにしているのを見て思わず笑ってしまう。
「何さー?」
肩をゆすられて不満そうな春香の顔を見つめた。
「いや、楽しいなって思ってさ」
「そっかー……。そうだねー……。これからも楽しいままだと良いねー。みんなでさー」
「そうだな」
浩志はみんなでという言葉にちくりとした棘を感じながらも笑った。