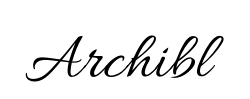第一節
「それで、付き合い始めてしばらく経つけどどうよ?」
土曜日のおやつ時、唯人は香織の家で亮太に問いかけられていた。唯人にはこれと言って趣味はないが、あえていうなれば勉強くらい。しかし、高校二年生なのだからわざわざ土日の日中に勉強はしないでおこうという心の中の取り決めにより、特にすることがない日は友人との時間を楽しむことにしていた。休日とは言っても父親が帰ってくる気配はなく、予定共有アプリ上では海外出張となっていたが、どこまで本当なのかなどはどうでもよい話だった。
「どうってなんだよ?」
答えにくい質問に対して聞き返していた。恋のABCなどという古い言い方で聞かれれば、まだどれも経験していないと答えられるのだが、抽象的すぎる質問は逆に答えにくいということを亮太は考えるべきだ。唯人の困り具合を見て亮太は質問を変えた。
「キスとかはしたのかって聞いてるんだが」
「してないよ。知ってるだろ? 別に俺たちは好きあって付き合ってるわけじゃないし、互いに利用できるものとしか見てないことくらい。大体、そこまで進むほどに見えるか?」
「俺の場合は一か月そこらで最終段階まで行ったからなぁ」
「中学生で早すぎるだろ。ちゃんと保健体育受けてからにしろよって当時のお前らに言いたい。大体、お前らは好き同士だったろ?」
「まあ、確かにな。くっつけてもらったけど、最初から互いの気持ちには気づいてたみたいなところはある」
唯人はこれ以上突っついてもいいことがないと観念した。
「ちなみに今日のおやつはホットケーキらしい」
ちょうど皿とカップを持ってきた香織を見て亮太がつぶやいた。
「ホイップクリームほしい?」
香織の問いかけに、何か悪意を感じて唯人は、
「あればほしい」
曖昧な答え方をした。それに対して亮太は、
「欲しい! 甘党にとっては必須のアイテムですよ!」
食い気味に答えた。
「じゃあ、ホイップクリーム作るの手伝ってね。
一つだけ言っておくと、いま電動の混ぜるやつ壊れてるから手動ね」
絶望的な表情で凍り付いた。手動でやるなんて正気の沙汰じゃないなどと考えているのだろうか、道連れを作ろうとしているのか亮太は、
「おいしい、おいしい、ホイップクリームはいらんかね? 今なら混ぜるだけで食べられるよ」
「どこの屋台販売の車だよ。別に俺は蜂蜜バターでいいし。大体、電動泡だて器なしって正気じゃないな。心の底から甘党を尊敬するよ」
恨めしそうな顔で、
「じゃあ、やっぱりやめようかなー、なんて」
香織がそれを許さなかった。
「私も食べたいから、よろしく。拒否権はないよ。してもいいけどおやつは当たらないよ」
「卑怯者ぉー」
語尾が弱かった。おやつが食べられないのは我慢ならないらしい。それともすでに唯人がホットケーキを食べているからなのか、一階のキッチンルームへと走る音がした。香織はホイップクリームの権は亮太に一任するらしく、手元のファッション雑誌を眺めながら、仕事とは終わったとばかりに知らん顔していた。そして切り出す。
「そう言えば、ゆい君って今度デートするんだってね」
何気ない一言に口に含んだ紅茶を吹き出しそうになり、唯人はむせた。
「何の話だ?」
心底記憶にないことを告げられて戸惑っていたのだ。それに浩志のことがあって今は落ち着いているとはいえそんなことをするような気分ではなかった。今は安定していると聞いたが、しばらくは春香が通って様子を見るらしい。そしてしばらくは来ないで欲しいと言われ、直接様子を見ることができないでいる。
「え?知らないの? 最近刑部さんの周りで話を聞いた、もとい絡んでた人がしつこく聞いたらめんどくさそうに今度遊園地にデートに行くって答えたらしいよ」
「そんな話聞いてないし、メールも来てないんだが」
「メールなんてしてたんだ。それより聞いてみなよ。俺たちデートすることになってるのかってさ」
唯人は慌ててスマートフォンを取りだしメールを書いた。
「俺に黙ってそんなこと言いふらすなんて、協定違反だろ」
「何よ、協定って。きっと刑部さんがデートしたかっただけじゃないの? もしくは面倒になって適当に答えたとか。でも、答えたからには行かないと面倒よ。証拠が出てくるまで延々とさえずることになるわ」
「なんて面倒な真似を……」
「それでキスくらいはしたの? 手をつなぐくらいはするわよね?」
「だから、さっき亮太にも聞かれたけどそんなことしてないって。別にそういうことがしたいわけじゃないんだから。ちなみにお前らの初体験の時期はさっき亮太から聞いたぞ」
俺が止める時間もなかった。大変遺憾だ。ぴしりと空気が凍った。
「そう、お仕置きが必要かもね。ゆい君は、今日は見逃してあげる。別にクラスメイトに聞かれたとかじゃないから、そこはいいし。ただ、軽々しくそんなことを言った亮太にはお仕置きが必要かもね」
これからの亮太の運命に合掌した。ホイップクリームを作って帰ってきたときには鬼がいる。唯人は知らないふりをしよう、自分は早めに帰宅して施錠しよう。そう心に決めた。
「そうそう」
先ほどの冷たい空気を霧散させて、ページの端がゆがんだファッション誌を机の上においてから香織は言った。
「遊園地に行くんだったら無料券あるよ。親戚が株主で友達とどうぞって十枚くらいくれたんだけど、あんま使い道なくてさ。良かったらこれで行ってきなよ」
「刑部に問合わせ中だが、行く可能性があるからありがたくもらっておく。ありがとう」
「どういたしまして。その代わり刑部さんってどんな人か教えてね。後は楽しみなさい。別にただの友達と言ってる感覚で行けば言いじゃない。さもないと無料券が泣くわ」
「了解です」
香織は棚から券を取り出し唯人に手渡してから、再びファッション誌に目を落とした。唯人は急いで残りのホットケーキを胃に押し込むと、紅茶を飲み干し、
「それじゃあ、また今度」
説教に巻き込まれる前に退散することにした。入れ替わりに入ってきた亮太の肩を優しくたたくと、不思議そうな顔をしてから部屋に入った。鋭い悲鳴が聞こえた気がしたが、唯人は急いで帰宅した。
返信があったのは夜の八時過ぎだった。メールにはそっけない文章と電話番号が表示されていた。
「面倒になってきたから餌をまいた」
ため息をつきながら読み上げた。確かに無用な妄想を噂として広められるよりは話題提供のほうがダメージははるかに少ない気がすると唯人は結論付けた。電話番号をスマートフォンに登録してから思った。メールに電話番号を添付して流出したらどうするつもりだったのか、不用心だな。五コール目で電話はつながった。
「もしもし、どちらさまですか?」
やけに丁寧な話し方だ、と思った。
「俺だよ、遠野だ」
「なんだ、あなたか。丁寧な応答して損した」
「やかましいわ」
何とも失礼な言い草に思わず言ってしまった。
「それで、何の用かなんて知っているが、あえて問おう。何の用だ」
「もう少し楽し気に、ノリノリのテンションで言われたら何とも普通のセリフだが、楽しくもなさそうに感情のない声で聞かれると普通に怖い」
「ヤンデレエンドのエロゲのヒロインとの電話みたいだって?」
「その例え何とかならないのか? 清楚系クール系を演出してるのに下ネタ好きって」
「 学校では優等生キャラのくせにたとえは下ネタってギャップあるでしょ? あなたもそうしてみたら?」
「俺は、エロゲはあんまりしないけど、なんとなく自分でも分かるわ。主人公が逃げてる途中みたい」
「あんまりしない、なんだな。全くしないではないと」
「今どきの高校生も嗜む程度はするだろうな」
「それもそうね、きっと」
唯人は、これ以上は不毛な話になりそうだと切り上げて本題に入る。
「それで、学校で遊園地デートに行くなんて言ったそうじゃないか?」
「したさ、今度行くから」
「だれが決めたんだ?」
「もちろん私だ。それ以外の何者でもない」
「相談もなく?」
「勝者の言うことは絶対だ。試験で負けたことを忘れたのか?」
「あれは付き合う付き合わないの話だろ?」
ここで折れてはいけない、これからいろいろ勝手に決められそうだなどと考える。しかし、なんだか屁理屈を言われる気がした。
「聞け。古代から勝者が敗者を支配するということは、暗黙の了解として決まっている。奴隷でもアイバクのように皇帝になった人物もいる。つまりあなたは私に勝利しない限り、ずっと奴隷のままなんだよ」
無茶苦茶な世界史理論を述べる梨乃に、次のテストで絶対勝ってやると誓いながらもこれ以上の抵抗は無意味だろうとあきらめる。唯人は自分を客観的に見て、ここの所二か月くらいでずいぶん振り回されていると評価し、しかも勝てないのではないかと最初から弱腰なことを自覚する。
「俺はあんまり乗り気じゃないんだ。親友が祖父母を亡くして落ち込んでいるんでね」
「それとあなたの行動の何が関係するの? 大体、それで気を使ってるつもり? きっと普通にしていてくれたほうがいい思うに決まている」
「それもそうかもしれないな」
唯人はかつて母を亡くした時にそうだったことを思い出した。
「まあ、それはいいとしよう。なんでショッピングとかじゃないんだ?」
「それはほら、ネット通販とかあるし。服とか下着とかって、男性はついてきにくいでしょ?」
「確かに、服はついて行っても暇だし、下着もなんだか変態みたいだし」
「もっとも、今時は彼女の下着選びについていく男性なんて珍しくもないけれど。選んだ下着着てほしいなら、着てあげるよ。オープンブラとかオープンショーツとか、エロゲではつけてる人多いし」
「なんでもエロゲ基準にするなよ。防御力ゼロじゃないか」
「いや、防御力の問題じゃないけどね。まあ、そこで個人的にも行ったことのない遊園地に行ってみたいわけよ」
「さいですか」
唯人は、梨乃が変人なのは考え方もだけれど、いろいろオープンに話すとこもじゃないかと勝手に思っていた。
「それで、いつにするんだ? 友人から無料券を譲り受けているけど」
「へえぇ、意外と乗り気?」
「そんなことはないが、たまたま今回お前が勝手に言いふらしたことを耳にしたらしくてな、それで使わないから要るかと聞かれたわけだ」
「その人、信用できるの? 見返りは?」
「俺の幼馴染だから大丈夫だろう。そして、見返りはお前がどんな人間か知りたいだそうだ」
「そうか、そんなくらいなら適当に話しておけばいいよ」
「了解」
唯人は梨乃に返事をした。
「今度の土曜日にしようじゃないか。どうせ予定なんてないだろ?」
「つくづくお前は失礼な奴だな。優等生の俺には予定があるかもしれないだろ?」
「ないだろうな。どうせ友人とか言うのも表面の付き合いで校外ではクラスメイトと遊びもしないだろう? 幼馴染なんていつでも大丈夫だろうから、結論として予定はないわけだ」
「結構な推理力だことで」
「朝の八時に駅前集合でいいな? 地元の遊園地とはいえ土日は混むからな。それでは」
電話がぷつりと切れた。勝手に話すだけ話しやがって、と唯人は心の中で毒づくがもうあきらめていた。
「というか、あいつエロゲ好きだな」
非常に残念なことに記憶に残ったことを言語化してからため息をついた。仕方なくカレンダーの約束の日に丸を付けた。傍から見れば彼女とのデートを楽しみにする彼氏そのものだったが、結局本人は気が付いていないようだった。唯人はベッドに倒れこんだ。
第二節
土曜日が来た。目が覚めたのは目覚ましが鳴ってからだった。普段の休日ならば、九時まで惰眠をむさぼっているというのに、朝八時集合という学校の登校時間かと突っ込みたくなる時間を指定されて、唯人は六時半には目を覚まさざるを得なかった。
父親は昨日帰っていたらしいと唯人は確信する。ソファにはカバンとスーツが乱雑に置かれていた。朝ごはんにはパンというこだわりがある唯人は、オーブントースターで食パンを焼きつつ目玉焼きとヨーグルトの準備をした。昨晩の残りのカレーを温め、ちょうど焼きあがったパンを浸して食べることにする。
食事を終えて食器を洗い終わると洗面所で手早く身支度を整えて、動いやすい服装になる。遊園地の面積はそこそこに広く、歩き回るのには適した格好がある。水筒を入れたリュックサックを背負い、財布とスマートフォンを持つと、運動靴を履いて家から出る。
隣の家の二階、つまり香織の部屋にはまだカーテンが引かれていた。休日の朝の七時三十分という時間を考えれば、自然なことだろう。徒歩で駅前へ向かう途中で出会うのは犬の散歩をする人とウォーキングをする年寄りばかりだ。犬にとって休日は関係ないし、老人は早起きなものだ。
早起きで三文の徳を得た人はどれくらいいるのか、実際に尋ねてみたい気もする。今時、落ちているお金を猫糞すれば、拾得物横領で叱られることになるだろうが。そんなこんなを考えているうちに唯人は待ち合わせの場所に到着する。
時刻は待ち合わせの五分前。休日だけあって人通りは少ない。鉄道会社は人の乗らない時間帯も電車を動かして採算がとれるのだろうか、などと無用の心配をする。ベンチに腰を下ろすと、チケットが財布に収められていることを確認する。
「待ったか?」
時間ちょうどになると梨乃は現れた。白い透き通る肌に白髪、白いワンピース。日傘をさしていた。
「白ずくめの女」
「なんだそれは。どこかの漫画の正反対を行く人間じゃないか」
「待った、五分ほど」
重ねて言葉を紡ぐと、
「普通は、『待った?』『今来たところ』とか言うのではないか。そして五分など今来たところの部類に入るだろうに」
唯人は、
「そんなやり取りは少女漫画の中だけで十分だ。そして、別に遅れていないのだから責めてはいない。待ったかと聞くから待ったと答えただけだ」
それに答えた梨乃は、
「何とか笑顔で言ってみたのに酷いな」
「いや、笑顔じゃなかっただろ。どう考えても口元をゆがめた復讐者だろ。どこのサスペンスだよ。遊園地殺人事件かよ」
「うるさいやつだな、本当に。とりあえず電車に乗るぞ、あと十分で来るから駅舎内に入ろう。日傘が重い」
肌ばかりでなく髪も白い梨乃は、日焼け対策が大変そうだと思う。唯人は、きっとこの人はアルビノなのだろうなと特徴を見てから再確認する。誰も口にはしないが、浮世離れした美しさはアルビノと遺伝の両方が作用した結果なのだろうと思っている。色素が薄いと少しの紫外線も肌に悪影響を与えると聞いたことがある。
そんなことを考えながら唯人は梨乃に続いて駅舎に入ることにした。
駅舎は新しい。最近建て替えられたばかりで、窓ガラスにクモの巣が付着することもなく、自動券売機が設置され、自動改札まで設置されている。どちらも改築前よりも増設されており、駅員は休日と朝の通勤通学ラッシュの時、もしくは地元の夏祭りの期間だけしかいない。
券売機で切符を買うことなくスマートフォンをタッチすると、通行する。切符を使う人は最近減少しており、紙を使わないエコなアプリ使用者が増えている。梨乃もアプリで入場していた。唯人は、スマートフォンをしまうと話しかけた。
「電子機器に弱いかと思ったが、そんなことはないのだな」
「もともとは弱かったが、自分で何とかするしかなくなって以来調べて使えるようになった。携帯ショップの店員と話すのは面倒だったから、シムフリーのスマホネットで買って、格安シムを挿している。最初はシムが何か分からなかったがな」
「格安シムだと楽なことも多いな。ショップからの広告も来ないだろうし」
「メールは来るがな。とりあえず無視しておけばよい」
「確かにな」
唯人は、梨乃の言葉に相槌を打つ。
「最近はパソコンにもはまっていて、分かると意外と面白いものだな。プロトコルとか部品とか。高スペックのパソコンだと重たいゲームでもヌルヌル動く」
「それでエロゲをするわけだ」
「そうそう、ヌルヌルと動くからサクサク遊べる」
「いや、突っ込めよ」
「スペックの無駄遣いだな。FPSゲームをするならまだしも、最新のCPUとGPUを搭載しているのにな」
「そこじゃないけどまあいい。お前のペースに乗せられるときりがない。それに最初のプロトコル云々は聞かなかったことにする。一般人が意識することはほとんどないからな」
「そうか。そう言えば、あなたってメールアドレスいろんな人に教えてるのだな。いちいち返さないといけないとか面倒じゃないのか?」
「それはほら、幼馴染にプログラミング得意なやつがいるから、おやつ一か月分でAI開発してもらった。名付けて返信AIのBOTちゃんだ」
「ほぼそのままのネーミングに、ひどい機能だな。本文読んでないのか?」
「ほぼ読まないね。要約内容を読んでパターンから自動返信させるか、連絡だけは目を通すボックスに移動させるかだ」
「これ、聞かれたらあなた相当やばいよな。刺される」
「ちゃんと刑部のは読んでるぞ。教えたメールアドレスも読むほうのアドレスだし」
呆れた顔の梨乃と会話をするうちに、電車が到着するアナウンスが聞こえる。滑り込んできた電車に乗り込むと、シートに座り、梨乃にチケットを一つ渡した。
電車に揺られること三十分。遊園地の最寄り駅で下車した。徒歩五分もしないうちに入場ゲートにたどり着いた。唯人はここに来るのは初めてではなかったが、梨乃はそもそも遊園地というものが初めてらしく、
「ここが、遊園地という場所か」
呟いた。
「言い方がすごい大昔に封印された悪魔が初めて魔界から人間界に来た時みたいだな」
「なんかあなたって、ゲームとか漫画とかのシーンに例えること多いな」
「人並みにはするから、ゲーム。それにエロゲに例える人には言われたくない」
「なんかイメージとは違うな。付き合い始めてからのイメージは、『今日は勉強するから』とか言って虫除けになってくれることが少ない気がしたけど実はゲームとか漫画に夢中だったのか?」
「いや、平日は勉強してる。土日はしたくないからこそ平日に」
「土日だけでゲームしてるわけだ? 私は、ゲームは毎日のようにしてるぞ。後は読書だな。どちらもシナリオを読むためにやっているようなものだが」
「文章を読むのが好きなのか?」
「そんなところだ」
ともあれ、開園まで十五分ほどの時間がある。年間パスポートを所有している人はすでに自動改札に券を押し当てて入場し始めている。一般客は、無料券を持っていても時間丁度にしか入ることができない。そこまで有名な場所でもないくせになんだか生意気だと見当違いのことを思いながら、唯人は数十組いるうちの最後尾に並んだ。
「刑部って、家族でこう言うところは来ないのか?」
唯人はそう問うてから顔を見た。
「いや、私は行かなかったな。そもそも行く機会がなかったし、肌が日光に弱いから日の当たるところにはあまり行かなかったな」
「そうなんだ」
梨乃の表情はほとんど変わっていないが寂しそうに見えた。
「それじゃあ、初めてなわけだ」
「そうだ、初めてだがアトラクションは何種類か知ってるぞ。テレビで見たことある。後エロゲで。観覧車とか定番だな」
「そりゃそうだろうな。今時、遊園地を知らない人間のほうが珍しい。たいていの人間は知ってるだろうよ。って、おい。観覧車を汚すな」
入場の時間になったのか、列が少しずつ進み始めた。自分たちの番になって、チケットを渡して入場する。梨乃は遊園地の様子を見て感心したように言った。
「へぇ、こんな風なんだな。大きいし、天井も高い」
「そりゃあ、天井が低かったら入場してすぐに圧迫感を感じることになるだろうから、高く作ったんじゃないか? 後は雨の日でも少しは楽しめるように待避所としての役割もあるんじゃないか?」
「なるほどな。そして高い入場料か。確かにこの施設を保つには金がかかりそうだし、黒字にしなければならないのなら妥当とは言わないが、仕方のないことかもしれないな」
「とりあえず乗ってみたいのとかあるのか? 興味を持っていたようだし」
「別にアトラクションに興味があるわけではない。ここに来ることでなぜ楽しいのかを知りたいだけだ」
興味深そうに梨乃は見る。それから、
「別にここに来る必要なんてないんじゃないか? 入場料を払う代わりに、近場の焼き肉店でも行ったらどうだ、と言いたくなるな」
唯人は呆れながら、
「それとこれとは別だろ? そもそも俺も遊園地には興味がないけれど、ジェットコースターが好きな人間だっているだろうし、子供にとっては年に数回連れて行ってもらえる、退屈ではない場所なんだろうさ。あとは雰囲気を楽しみに来る人とか、恋人のデートコースだったりする」
「まさしく今の状態なわけだ」
「普通は楽しいとかではなく、楽しそうな雰囲気だからとつられるだけなんだろうさ」
「今日はせっかく来たんだからいろいろ乗ってはみようじゃないか」
「なんか投げやりだな」
「そもそもアトラクション目当てではなくて、理由探しだからな」
「お前って、そんなことばっかり考えてるよな。純粋に楽しんだほうが良いと思うぞ。学校でも変な質問ばっかりして、周りから引かれ気味なの知ってるか?」
「別にそんなことはどうでもいいんだよ。教師ですらまともに答えないからな」
「なまじおつむの出来はいいだけあって、教師も全くの無視とかスルーはできないわけだ」
「役に立たん回答ばかりだがな。そもそもなぜ生きるかという問いは人それぞれの回答を期待していたというのに呆けよってからにな」
「いや、普通の反応だ」
唯人は梨乃と話しながら、変な奴だが面白くはある。だが心の底には闇がありそうな人間だと評した。しばらくしてアーケードを抜けると正面には観覧車が見え、左から右へとジェットコースターのレールが走る。その他にもメリーゴーランドやコーヒーカップも見えてくるが、
「メリーゴーランドよりも乗馬のほうが面白そうだ」
「回るだけの何が楽しいんだか」
酷評である。唯人は乗馬なんてするやつが一般人にはいないだろうななどと突っ込むのはやめておいた。
ようやくお昼時になったころにはすでに唯人は疲れ果てていた。昼食を採るべく入ったレストランでこう告げた。
「文句ばかりじゃないか」
「いや、感じたままを述べただけだが?」
「それにしても、気分だけは楽しめよ。というか、希望できたんだから楽しそうにしろよ」
「楽しそうにしたが?」
「俺は結構モテる」
「唐突だな」
「そして、お前も見た目は奇麗系だから目立つ。話してみると毒は吐くし、めちゃくちゃ言うから腹立つけどな」
「そもそも人と話すのは苦手でな。学校では教師と生徒ともに最低限しか言葉を交わさない」
「人が嫌いで話してないんじゃ?」
「それはそうだが、話すのが苦手であなたみたいに外で猫をかぶって自分を偽るのが苦手なだけだ」
「それは置いておこう」
唯人は続けた。
「とにかく、にこりともしない女を連れた男を見たら周りはどう思う? せっかくの遊園地なのに興がそがれるだろうが。つまりもっと笑え」
アルカイックスマイルを浮かべる梨乃を見てやるせなくなった。
「それはそれで怖いから、自然に笑え」
「面白くもないのに笑えるか!」
「面白くても笑わないくせによくほざく。どこの芸能人だ」
もはや遠慮はなくなっていた。
「結構笑う練習させてるよな?」
ほっぺたを持ち上げて口角を上げさせる。それから目尻を引っ張って下げさせてから、
「何変顔してるんだよ」
「あなたが動かしたんだろうが」
梨乃はついに唯人の頭をはたいた。
「それに乙女の頬に許可なく触れるとはどういう了見だ?」
「誰が乙女だ」
鼻で笑うと梨乃は唯人の頬を引っ張った。周囲では喧嘩かしら、などという声がひそひそと聞こえるようになる。さすがに二人は言い合いをやめた。
とそこに、
「ハンバーグランチセットです」
料理が届いた。
「美味しそうだ」
ナイフとフォークをきちんと持って上品に切り分けると、
「いただきます」
一口食べて嬉しそうな顔をする。唯人は、普通に笑えるじゃないか、と思いつつも食べる様子を眺めていると、
「これはあげないぞ。このハンバーグは私のだ。こっちのにんじんはくれてやる」
「お前は子供か。そして自分の料理が来るのくらい待てるわ!」
「それでもこのにんじんはくれてやる」
ちょうどきた料理を見て、
「そこにあるジャガイモを交換してやる」
「だから、子供か。好き嫌いなく食べなさい。でないと、大きくなれないぞ」
梨乃は、
「別に大きくなれなくとも構わないさ。百六十も身長があったら十分だ。あなたこそ百七十五だったら中途半端だからあと五センチ伸ばしなさい。そして学校教育ではまかり通っている好き嫌いすると大きくなれないよ理論は正しくないと証明されているはずだが。あれも体罰の一部に入ると思うのだがどうだ?」
無茶苦茶である。そして大きくなれないよ理論で泣いたのだろうなと思う。唯人は、もう引き下がらないだろうし相手をするのも面倒になってきてにんじんとジャガイモを交換してやった。ドリアと蒸し野菜がついたセットを完食してからすでにハンバーグを食べきった梨乃を見てから、
「ファミレスとかあんまり行かないだろ?」
「行かないな。外食は基本しないな、自分で作る。これでも料理は上手いほうだと自負している」
「ハンバーグは作らないのか?」
「作る時もあるが、外で食べるほうがおいしいと感じるな。それはあなたと食べたからかもしれない」
「そう言えば前に一人暮らしって言ってたよな。一人で食べるよりはおいしく感じるか?」
「そうなのだろうな。別に私の味蕾が変わるわけでもないのに不思議だな」
唯人は思う。確かに、一人で食べるよりも香織の家で食べるほうがおいしいかもしれないなと。
「俺も一人で食べることが多いけど、そもそも料理しないな。片付けが面倒で、コンビニの弁当とか食べることが多いし」
ふむ、と頷いた後、梨乃は、
「バランスを考えて食事をすることは大切だぞ。コンビニ弁当ばかりでは体に悪いだろうから、今度機会があればごちそうしてやろう」
「そりゃどうも」
好き嫌いをする人間がバランスの取れた食事を勧めるだなんてどこかおかしい気がするがそれは言わないでおいた。そんなこんなで会話をしながら、会計を済ませ外に出る。
「まだ何か見て回るか? 興味を引くものはあったか?」
「もうたくさんだ。後は土産物店でも見て帰ることにしよう」
最初のアーケードまで戻ってくると、さほど広くないグッズ販売スペースに入った。中で売ってるだけで値段が異常に高くなるのはどうしてなんだろうか。そう不毛な考えをしながら、チケットを譲ってくれた香織への土産を考えていた。クッキーとかチョコでいいかと結論づけるにはさほど時間はかからなかった。
「俺は決まったけどなんか買うか?」
「別に私は買う相手がいないからパスで、と思ったがあなたとおそろいのキーホルダーをカバンにつけよう。それで遊園地に行くという宣言は嘘ではないことが分かるし、何度も話しかけられなくて済むから楽だ」
「ほんとにお前は話しかけられるの嫌いだな。まあ、同じくだが」
揃いの小さなマスコットキャラクターキーホルダーをつけることにする。唯人は会計時に微笑ましいものを見るような視線にイラっと来たが、梨乃同様に表情を変えることはなかった。
それから電車に揺られて集合場所に戻る。そして、ちゃんと月曜日にはキーホルダーをつけることを確認して解散した。なんとなく唯人は少しは楽しかった気がした。
第三節
日曜日にはどこにも出かけるつもりはなかった。土曜日の夜には、すでに父親は家を出ていた。父親がいるからどうとか、いないからどうとか、そんなことはあまり関係がなかったが、唯人は無感動に、『ああ、また出かけたのだな』と思っただけだった。
しかし、どこに行くつもりがなくても人がやってくることはある。無慈悲にならされたインターフォンのカメラがとらえたのは香織だった。
「何か御用で?」
インターフォンのマイクに向かって話しかける。ここで出ないという選択肢もあるが、次の日につかまったことがあるためどうせ避けられはしないとあきらめていた、しかし、用を聞いてみるべきだろうなという思いから声をかけたのだ。
「昨日のこと聞きたいからとりあえず入ってもいい?」
「どうぞ」
玄関のカギを解錠すると扉を足で押さえられ、インターフォンから隠れていた残りの三人もなだれ込んできた。
「それで、たくさんできたのな」
「何か問題でもあるのか?」
亮太の問いに、別にという風に首を振る。
「昨日の話が聞けると聞いてー」
食い気味な春香と面倒臭そうな無理やり連れてこられた風の浩志がいた。浩志はだいぶと立ち直ったように見えて、それでもどこか寂しそうな表情をしていて、亡くしてすぐなのに気を張っていつも通り振舞おうと心掛けているのが透けて見える。春香が連れてきたのは意外だったが、久しぶりに顔を見て思ったより元気なようで安心した。
唯人は何も触れずに玄関の錠を落とす。
「とりあえず、リビング行くね」
浩志はパソコンを小脇に抱えて真っ先に入って行った。
「そこで止まってないでとりあえず早く行けよ」
残りをリビングに押し込むと、真横のキッチンでコーヒーの準備をした。それぞれに砂糖の量もバラバラなため砂糖の容器ごと食卓に出し、続いてコーヒーを運ぶ。コーヒーが苦手な亮太には牛乳をたっぷり入れて薄めたのを差し出した。
「それで、昨日のデートはどうだったのー」
「特に面白みもないぞ。なんせ相手が相手だからな。それから早くに帰ったからな」
「ええー、そうなのー」
つまらなそうにする春香にコーヒーと菓子を勧めながら、
「そう言えば、香織と約束してたどんな人間か教えることだが、本人の許可は取った」
「へぇ、それでどんな人だったの?」
「それが、やっぱり面倒臭い奴だというのは確信できた。あとは意外と子供っぽいとか」
香織は、意外そうな顔をした。
「あの人って、無表情の完璧超人に見えるんだけど」
「それが、意外な弱点としてにんじんが発見された」
「にんじんって……。子供ね」
納得したかのような表情に続けて言った。
「ハンバーグを食べて笑ってたな」
「笑ってた?」
興味なさげだった浩志は口をはさんだ。すっかりパソコンは閉じてソファから食卓に近寄ってきた。
「ハンバーグを食べ始めたとき少しだけ笑ったんだよ。まあ、ほとんど分からん程度にな。それで顔をじっと見てたらハンバーグはやらんってさ」
「それも子供っぽいけど笑ったのが意外過ぎるな。あいつが笑ったのどころか怒った表情も見たことないのに」
「学校では鬱陶しく感じてるらしいぞ。無視を決め込んでるけど」
「意外と人間ぽいんだ」
亮太が突然、
「刑部梨乃がロボット説が提唱されてるんだよな」
会話に割り込んだ。それを引き継いで浩志が、
「だって授業中話聞いてない風なのに当てられたらきちんと正答するし、小テストも満点だし人間業じゃないと思われてるわけだ」
「意外と面白いやつなのにな」
「それは仮にも恋人のゆい君しか分からない感覚でしょうね。でも、いやいや始まった関係のわりに長続きするのね。喧嘩もなしに」
「いいや、たまに喧嘩はする。互いにビジネスパートナーと思ってるから何ともないんじゃないか? あれが、本当の恋人になろうものならきっと苦労するぞ」
「そうかもしれないね」
亮太は香織の肩を急に抱き寄せると、
「これぐらいのことはできなければ世間は騙せませんぞ」
と言った。
「まあ、一か月で進みすぎるカップルには言われたくないわな」
浩志の一言に、
「何が進みすぎるって?」
香織が笑顔で聞いた。「これって、聞いちゃダメな奴?」といった風な目で唯人を見ると、唯人は頷いた。
「あのね、かおちゃん。皆知ってるよ、少なくともここの三人はー。だって、翌日すごくよそよそしかったし、妙にそわそわしてたしー」
春香の言葉に全力で同意する浩志はその背後に隠れた。表情を戻すと、
「別に知られたところでねぇ。どうでも良いや」
助かった、と頷いた。
「ともかく、ファーストアプローチが衆人環視の中のハグな人は十分騙せてると思うけど?」
「いや、あれは向こうからで、耳元で『約束は守ってもらう』って低い声で囁かれたんだぞ。逃げてやろうと思ってたのに台無しだよ。あれは怖い」
「良いじゃないか。偽の恋人でも十分仲いいし、それに言い寄られる件数も減っただろ? 相手が刑部梨乃じゃ、どうしようもないっていう話なのか、変人を選んだお前に少し引いたのかは知らんけど」
「後者だったら嫌だな。あいつは変人だが、俺のセンスまで疑われてはどうしようもないからな」
唯人は困った、という風に腕組みをして見せた。
「ねえ、お菓子もうないの?」
のんきに聞いた春香にいつもの戸棚にあると指さすと話を戻した。
「とりあえず、あいつは遊園地に行って遊びたかったのではないらしい」
「その心は?」
「なぜ遊園地に行くのが楽しいのか知りたかったらしい」
「変わってるなぁ」
「曰く、焼き肉屋のほうが幸せになれるのだそうだ」
「それに関しては僕も同意だな」
浩志の言葉に、
「いや、それってどうなんだよ。全然方向性が違うような」
亮太が突っ込んだ。
「でも、遊園地は構造とか見るのは好きかな。あとは制御系とか興味あるな」
「完全に仕事っぽいな」
「私は、写真撮るかなー。ホームページに載せる用の背景にちょうどいいかもー」
「それこそ仕事じゃないか」
亮太がは呆れた顔で疲れながらも突っ込んだ。
「それで、他の話はー? 手をつないだとか、キスしたとか、ついでにそのシーンをとらえた資料はー?」
「ないわそんなもん。仮にあっても出さんわ!」
唯人は渾身の突っ込みを見せるとがっかりした表情の春香を無視して言った。
「そんなつもり、互いにないしな」
香織はその言葉に対して答えた。
「そんなの分からないじゃない? いつ本気になるかって感じでしょ。別に仲が悪くないならそのまましとけばいいよ。そう言うのが好きじゃないのは知ってるけど、無理して否定する必要もないんだよ。本心からならそれで何の問題もないけど。それにどれだけ本気でも仲良くても突然終わる人もいるんだから」
唯人は顔を向けた。ここにいる人間は信用してるし、幼馴染だからこそ母親がいないことも父親が家を空けているのも、自分が勉強していた理由も知っている。だからこそ、忠告にはきちんと従うべきだろうなと漠然と思う。曖昧なものが、感情だけで動くようなものが嫌いだと思ったが、唯人はこの四人との関係性は大切にしているし、この四人との関係性そのものが不安定ながらもずっと続いてきたんのじゃないか、と思いながら返事をした。
「きちんと向き合うよ、その時が来たら。今のところはその時は来ないだろうと思うし、多分あいつとでもないだろうって思う。だからありがと、今日は来てくれて」
「素直になられるとちょっと気持ち悪いんだけど」
「今の感謝の言葉返せ!」
渾身の叫びに、
「そしてもう帰らせようとしてるけど昼食はごちそうになるつもりだから。材料は買い出しに行こうね」
香織はすんなりと答えた。
「私は昼食、ミネストローネがいいなー」
「春香、結構暑い時期にそんなものを所望するか」
「俺は、ピザがいいな」
「生地作るのに時間かかるから駄目だな」
めちゃくちゃであった。唯人は一言、
「今日の昼食は手羽先でも焼くことにする。買い出し班はよろしく。あとは飲み物も」
「じゃあ、私が行くよ。春香もついてきたらお菓子一つだけ買ってあげる」
「分かったー。かおちゃんと行くー」
「じゃあ、僕は食器でも並べるよ」
「机拭いとくな」
にぎやかな友人に囲まれるのもやはり悪くないなと改めて唯人は思う。
「じゃあ、たれ作っとく。甘辛のやつ」
言って、キッチンへと入った。米を炊いておかなければならないなとか、中華スープをつけようとか考えながら準備を進めた。まあ、何とでもなるか。それはその日に唯人が思った結論だった。
第四節
「んっ、んっ」
断続的に甘い声が部屋に響く。香織は部屋に一人の状態でカーテンを閉め切っていた。夜の部屋に一人で声を抑え気味に一人でオナニーをしていた。それは十数分続いて、断続的な声の後に一際高い悲鳴めいた長い嬌声を上げる。身体を痙攣させて恍惚の表情でベッドに横たわった。
「はぁ…………」
長い溜息を吐いたのは仕方のないことかもしれない。無性に虚しくなっていたのだ。ティッシュで股間を拭うとパンツを履いた。
亮太と別れてから欲求不満だった。それまでは毎日のようにセックスをしていてそんなことを感じたことは久しぶりだった。思えば中学一年生から今に至るまではオナニーの回数よりもセックスの回数のほうが多いのかもしれない。それはそれで健全ではないが、自分でするよりも虚しくはなかった。人の温かみを感じられていたから。
玩具を使ってもあの時の胸の高鳴りと高揚感は感じられなかった。
「亮太もしてるのかな」
元カレのことを想った。亮太とは身体の相性が良かったのだろうと思う。他の人としたことはないが、きちんと絶頂を迎えることができていた。それを思って虚しさからさらに股間に手を伸ばしそうになる。
「一回だけって決めたんだから。このことも想定して別れたんだから我慢しなくちゃ」
香織はパジャマを持って風呂場へ向かった。香織は両親が外泊中で家に一人だという状況を知っていた。何も思わずに風呂へ向かったのだ。
シャワーを浴びる。髪を洗って、それから身体を洗う。秘部にシャワーが当たると身体が跳ねる。スポンジが乳首に当たるたびに感じてしまう。
「病気だね、私」
自分がストレスから性欲に逃げてきた代償を感じた気がした。少しセックスしないだけでこうなってしまうなんて思いもよらなかった。
別に誰でもいいのかもしれない。今度誰か別な人に抱かれてみようか。別れているのだから問題などないはずだ。脳裏に亮太が浮かんだ。彼に抱いて欲しい。そう思った。それでも抗いきれない衝動に包まれた。
香織は無意識にいじっていた乳首とシャワーを当てていた秘部に高鳴りを感じて、一回の決意を破って二度目の絶頂を迎えた。
シャワーを終えるとパジャマに着替え、スキンケアやヘアケアを素早く済ませて部屋に戻った。籠った熱気を逃がすように窓を開け放ち、そこでメールが届いていることに気が付いた。
誰からだろうかとメールを見ると唯人の名を見た。
「明日、浩志の家に行くからそのつもりで」
短文。窓の外をカーテンを開けてみると向こう側からこちらを見るのに目が合った。小さく手を振ってからベッドに倒れこんだ。大きな溜息が出た。
第五節
「浩志の家に行くよ」
春香がそう言ったのは自然なことかもしれない。表面上は元気そうに振舞っていても内心平気なはずがない。浩志が縁を切りたいほどに思っている金の亡者の親族に会わねばならないのだ。葬式があるのだから行かないわけにはいかない。
遺体が引き取られてから数日が経っている。参加したくないと言っているが、それはきちんと祖父母に別れを告げる機会を失うということで永遠に後悔しかねないことだ。だからこそ無理やりにでも連れていくといったのだろう。しかし葬儀会場の近くに連れて行くだけで中まで入ることは多分できないのだからそこから先は本人の戦いであることを分かっていた。
唯人は香織と連れ立って浩志の家に向かった。
家の前にたどり着くと浩志が春香に連れられて出てくるところだった。
「行きたくない」
「でも、行かないと後悔するよ。二度と機会はないから」
春香が浩志の言葉に告げていた。唯人はそこで合流した亮太に話していた。
「やっぱり行きたくないんだろうな」
「そりゃあ、そうだろう。もちろん葬儀に出て供養したい気持ちもあるだろうけど行けば間違いなく嫌な気分になるのは分かっているからな。俺だったら悩むな」
「私は、春香が言っている通り行かないと後悔すると思うな」
「それじゃあ、とりあえず会場の前までは連れて行こうか」
浩志の元まで歩くと腕を取った。
「唯人……」
恨みがましい目線で見る浩志に、
「絶対後悔するから顔だけは出して線香は上げて来い。浩志は爺さんと婆さんのこと好きだっただろう? 他の奴なんか相手にしないで二人の冥福だけを祈ってくればいいんだ」
「…………」
逡巡している浩志に、
「行きなさい。それで終わったらすぐ帰ってくればいいから。ごはん帰ったら作ってあげるから何が良い?」
「和食」
「ざっくりしてるな」
ようやく行くことを決断した浩志を春香が、呼んでおいたタクシーに乗せる。
「それじゃ、私は近くまで一緒に行ってくるから」
「よろしく。帰りは私の家に来てね」
香織の言葉に頷く。
「来たな、浩志」
そう言って声を掛けてきたのは父だった。浩志は小さく頷いた。
「葬式だからこれに着替えろ」
手渡されたのは黒いスーツだった。確かに今のジャージ姿は似つかわしくないなと思い、受け取ると着替え始めた。家族の控室には両親といとこ家族がいた。いとこ家族とはごく小さい時に会った記憶しかない。いとこはすでに成人していて働いていると聞いた。
自分とは関係のないことだ。浩志はジャージを畳んで荷物の中に入れた。
始まるまでの時間は誰からも話しかけられず、ただ静かな時間だった。一人で宙を見つめていると未だに祖父母が死んだことを現実として受け止め切れていない自分を感じた。理解できても受け入れられないというのはこういう感覚なのだなと思った。
その後の葬式は粛々と進んだ。読経から火葬までスムーズすぎるものだった。最後に骨を壺に詰めて家に持ち帰るという段階で納骨は後日ということになり解散になった。
「浩志、少しこっちに来なさい」
帰ろうとした浩志を呼んだのは父だった。疲れた顔をしていた。さすがに答えたのだろう。この場で金の無心などはないだろうと思った。
「遺言状が出てきたからお前も読みなさい」
中身を見てみれば遺産を全て浩志に譲るというものだった。ここで理解した。この人はこんな時でも遺産目当てなのか。遺言状が握りつぶせないのは弁護士に原本を預けていると書かれているからだ。
どうしようもない。人は金でしか動かない。金さえあればなんでもいいのだろう。すでに疲れた顔は守銭奴で亡者の顔に見えていた。