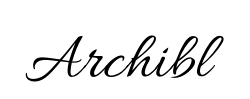第一節
「暑すぎる。溶けてなくなってしまいそうだ」
唯人は、放課後の教室で目の前の亮太にぼやいていた。季節は夏に差し掛かったあたりで、夏休みまではあと三週間ほどある。気温は昨今の異常気象のせいで摂氏三十度近くを指していた。浩志は学校に来ていなかった。電話もメールも通じない。その前のメッセージではしばらく誰とも会いたくないから来ないでくれとあった。それから一月近くが経っていたが心の整理がつくまでは構わないほうが良いだろうと結論を出していた。
朝のニュースコーナーでは、暑さの本番はこれからだなどと言われており、思わず『人間の蒸し焼きでも作るつもりかよ、地球』と一人で突っ込んでしまっていた。日本の夏は暑いが、それは蒸し暑いというものでアフリカのように乾燥した暑さではなく、体中にまとわりつくような暑さだということは小学校の社会で習うことだろう。
「そんなこと言っても涼しくなるわけじゃないんだ。むしろ言葉にしたほうが暑く感じるというじゃないか。余計なことは言わずに作業に集中したまえ」
さすがにこの暑さなので朝から夕方まで、授業中はエアコンが効いている。しかし、放課後の教室はうだるような暑さで、エアコンの恩恵は受けられていない。もちろん文化部の活動教室にはエアコンが入れられているが、それ以外の教室では電源が切られているのだ。
「というか、あの教師は人に仕事を頼むんだったらエアコンつけっぱなしにしておいてくれよな、ほんと」
「いつもはついてるらしいんだけど、今日は申請を忘れたらしくて。すまなそうな顔してたじゃないか」
亮太にそう言われて、それでも納得がいかない唯人は、教室に二人しかいないのをいいことに机をたたいた。
「同情するなら、仕事を任せるな。何なら職員室の片隅でも貸してくれればいいのに」
「それは無理な相談だろうよ。そもそも書類の仕分けを頼まれたのは、今日の職員会議で時間が取れないからだろうに」
「押し付けやがって……。保健室の亜美ちゃんは場所貸してくれないかな?」
「職員会議だろうし、放課後は部活の生徒がけがしてきたら見ないとダメだろ? 俺たちを甘やかしてることを知ったら、他の生徒が自分も自分もって寄ってくるから邪魔になるじゃないか。授業中のサボりの口裏合わせしてくれてるだけでも世話になってるんだからさ」
保健室の亜美ちゃんこと佐々木亜美養護教諭は、唯人たちと年齢が近い新卒採用だからこそ秘密を共有する友達のような感じで、唯人が優等生を演じていることを知っていながらも黙っていてくれている。唯人はそのことに感謝しているし、迷惑をかけたくないとも思っている。
「それにしても、担任ってだけで俺たちを便利に使いすぎじゃないか、山下は」
担任の山下義明教諭はこわもてのながらも、根は優しいことから生徒には人気がある。そして、二人もなんとなく信用もしているし、多分唯人の本性もバレている。それを黙っているうえで相談にも乗ってくれる普通のいい先生なのだが、二人を便利に使っている感も否めない。
「この書類、何枚あるんだ?」
「全校生徒分らしいから九百枚くらいじゃないか? いや、教師の分もあるから千枚くらいかだろうな。アンケート調査らしいからな」
厚い紙束をひらひらさせることはできず、持ち上げて見せるだけにとどまった亮太の口からの衝撃の結果にうんざりした。
「こんなもの、マークシート式にして機械で読み取らせろよな。きっと一瞬だぞ、一瞬。なんだってこの世の中に手作業なんだよ」
「そんなことは学校に言ってくれよな。そんなことよりも早く手を動かせ、口じゃなくてな」
このアンケート用紙は、先日学校全体で集められたもので、文化祭に向けたものだ。毎年、生徒や教師の疑問に校長や教頭が答えるというもので、かれこれ十年以上は続いているものらしい。文化祭の当日に壁に掲示として貼られるのだが、意外と人気コーナーでやめるにやめられないそうだ。先生は何のキャラが好きですか、といったくだらない質問から、どうやったら勉強が楽しくなりますか、といった真面目なものまですべて答えるのがこのコーナーだ。
唯人も去年、この掲示を見たが、よくもまあこんなに答えたものだと感心していたが、これは教師が仕分けしてまとめて、データ入力して、それから答えてと二か月も準備期間がかかるのも仕方ないといった代物であることをようやく理解した。
「意外とこのコーナー面白かったよな。去年も生徒教師問わず人気だったじゃないか。それに校外からの客も来るし、気合入ってるよな」
「気合い入れるのはいいけど自分たちで完結させてほしいよな」
唯人の言葉に激しく同意した亮太は再び紙束に目を落とした。
「生徒会とか手伝わないかな、これ」
「無理だろ。毎年通りならともかく、他校との合同文化祭なんだぜ今回は」
唯人は溜息を吐いた。余計なことはしなくてもよいというのに、なぜか今年の生徒会は活動的で、他校との合同文化祭を決めた。生徒同士の交流を図り、互いに刺激を受けることで、青少年の健康的な精神の育成に寄与するために開く。こんな風に至極まっとうな理由を、それっぽく据え付けていた。
おかげで去年までは質問がある人だけ提出だったのが、何かしら書いて提出に変わってしまったのだ。校長も教頭も、そして唯人たちもとばっちりである。
「そう言えば、お前の彼女は休み続きらしいぞ。病気なのかもしれないな」
亮太の言葉に、
「そうだったのか。道理で顔を見ないと思ってたんだ」
何でもないことのように唯人が返すと、
「ひどいじゃないか。仮にも付き合ってるんだから、気にくらいしてやれよ」
「いや、メールは返ってくるし、たまにかかってくる電話では元気そうだし、別に何ともないかなって」
「へぇ、電話するくらい仲良くなったんだ?」
にやつく亮太の頭をはたくと、
「別に、口裏合わせだからな。例えば行ってもいない放課後デートの思い出話のこととか、脚本は刑部で考証が俺なわけだが、結構みんな騙されてくれるよな」
「え、あれ嘘だったのか?」
驚きの表情と、嘘を見抜けなかったことのショックを感じている表情とが入交になった感じでこちらを見ていた。
「嘘と本当が混ざっているからこそ、見抜けないものになるんだよ」
「お前らがファストフード店でデートしたって噂は?」
「あれは本当だ。ただの食事だったがな。そして行った回数は半分だ。六回の噂は三回だ。全部香織にそれとなくばらまいてもらった」
「香織は知ってたんだな」
「お前、嘘が下手そうだもん」
さらなるショックを受けた感じの亮太は、しょんぼりとしていたが、
「それとこれとは別だが、お見舞いくらい行ってやらないのか? 意外とさみしがり屋かもしれないぞ?」
「それはないだろうな。彼女、ずっと一人でいたみたいだし、人に興味なさそうだし、病気だったら家に来られてもしんどいだけだろう。それに家を知らない」
「そりゃそうか、家を行き来するようなことなさそうだもんな」
唯人は黙って手を動かし始めた。亮太も黙々と作業をし始めた。一時間後、すでに半数は片づけたところで集中力が切れてしまい、二人は残りを明日に回すことにして帰宅の準備を始めた。
職員室へと向かうとすでに会議は終了していた。いつも通り談笑する教師たちの中に山下の姿を見つけると、唯人は迷いなく足を運んだ。
「先生、作業は半分明日に回していいですか?」
半分は自分でやればいいのに、とか思いながらも表面は取り繕って話しかけた。
「ああ、ご苦労さん。ちょっと待っててくれ、ジュースとってくるから」
去ろうとする山下の背中に、
「長谷川君も手伝ってくれたので、二本お願いしますね」
手を振って了解の意を示すと冷蔵庫に向かって歩いて行った。手持無沙汰になった唯人は、職員室を見回していると一人の教師に手招きされた。
「ちょっと遠野君、来てくれる?」
教師の中でも高齢な方で、教師の中にも教え子がいるという深田美恵子に呼びかけられた。来年で定年なことは結構有名なことで、国語ができない生徒を集めて長期休みに講習会を開いて、休み明けのテストでは八割以上を取らせるという超有能な教師だが、参加者は二度と参加したくないと思うほどに徹底的にいろいろ叩き込まれ、できるまで帰さないという恐怖政治をしているとの噂もあるが、唯人には関係のないことだった。
「どうしたんですか?」
書類の山がある机と机の間を辛うじてすり抜けて深田のもとにたどり着くと、封筒を渡された。
「あなたって、刑部さんとお付き合いしてたわよね?」
その問いに、教師にまで広まっているのかと苦々しい思いを胸に、
「ええ、そうですけど」
平静を保ったまま答えた。
「やっぱりそうなのね。それで、お願いがあるんだけどこの封筒、刑部さんに届けてくれないかしら? この後用事があって、私が行ければよかったんだけど……」
「いいですよ。でも、家の場所知りませんよ。教師が勝手に生徒の住所を教えるのは問題でしょうし」
これで引き下がることはなく、意外な答えが返ってきた。
「すごい熱らしくて、電話した時に、書類を届けてもらえるなら遠野君にだけは住所を教えても構わないと言われたのよ。もともとはそんなつもりなかったんだけど、予定が入って、しかもちょうど職員室にいるからお願いしようかなって」
余計なことを言ってくれたな。唯人は恨みがましいことを心中で考えた。平日の夜は勉強時間に充てることにしているのに、その時間を削れというのか。今週の土曜日は勉強せねばならないな。そう結論付けると、封筒をちらりと見た。
「これ、住所だから。悪いけどよろしくね」
唯人は受け取って山下の机に戻った。
「これ、お礼だ」
オレンジジュースだった。ただし、果汁百パーセントの高いものではなく、五パーセントの安いものだったが。
「教室は暑かったので、冷えた飲み物はうれしいです」
そこはかとなく文句を口にすると、
「ちゃんと次からは前日までに申請書出すから」
次も何か頼まれるのか、それは確定なのか。唯人は職員室を後にすると、教室に戻り、亮太に一本を手渡した。
「また、何か頼まれるかもな。次からは前日までに申請書出すってさ」
「これもそれも頼まれるのは唯人だろ? もうこりごりだね。明日、残りの整理を手伝うのも嫌々だっていうのに」
「今度プリン作ってやるから」
「おい、なんか俺はプリンごときで働く安い労働力みたいじゃないか」
「実際そうだろ? ホイップクリームと果物も載せて、プリンアラモードにしてやるから」
「そこまで言うなら仕方ないな」
唯人は、プリンで釣れる安い奴だと思った。間違いはない。しかし、亮太が友達だから手伝ってくれていることも分かっていたので、
「ありがとな。ところで溶けたチョコレートいるか?」
たまたま買って保冷バッグの中に入れ忘れていた袋入りのチョコテートを差し出すと、
「いや、いらんだろ、べっとべとのチョコなんか。チョコレートファウンテンとかならうれしいけど」
「そうか」
今度こそ保冷バッグに片付けると、
「そう言えば、さっき配達頼まれたから先に帰るわ」
「配達? 帰りに郵便ポストに入れておいてくれとか、そういう話か?」
「いや、刑部の担任からこの封筒を届けてくれってさ」
ひらひらと見せると、それからカバンにしまい込んだ。
「家の住所知らないんじゃなかったのか?」
「教えてくれた」
「それ、教師が個人情報流して大丈夫なのか?」
「本人が電話でいいって言ったらしい。 本当に面倒なことをしてくれた」
肩をすくめて見せる唯人に、
「本当にさみしがり屋だったのかも知れないぞ?」
亮太は教科書の最後の一冊を詰めながら言った。
「どうだろうな。俺を使いっぱしって楽しんでるだけとか、熱出てるらしいからうつしてやれとか、そういう邪悪な魂胆かもしれないぞ」
「それだったら面白いな」
唯人は、笑いながら手を振って教室を後にした。
「それにしても高いな」
目の前にした建物を見て唯人は言った。教えられた住所は家とは反対の方向だった。町の中心地にほど近く、スーパーマーケットやショッピングモール、百貨店やパチンコ店などが所狭しと並ぶ、前に待ち合わせしたのとは違う駅の近くだった。
同じ町でも、中心部と住宅街ではこうも違うのかと圧倒された。自宅近くは時々通る竿竹屋か廃品回収車のアナウンスくらいしか聞こえないというのに、なんと騒音に満ちたことか。
そんな場所に立っているからか、セキュリティは厳しい。玄関には管理人がいる部屋があり、そこから先に入るにはインターフォンで訪問先の人間に解錠してもらうか、暗証番号と物理的なカギを用意するか、もしくは管理人同伴で施設点検するかくらいしか方法がないように思われた。
教えられた部屋番号を呼び出すと、ガチャリと受話器を取る音がして呼びかけがあった。
「どちら様ですか?」
唯人はカメラの前に立つと顔を近づけ、
「遠野です」
と答えた。
「今開けるから部屋の前まで来て」
自動ドアが開き中への通路ができる。唯人は管理人に少し頭を下げるとエレベーターへと向かい、ボタンを押した。エレベーターは十人くらい乗れそうな広さがあった。新しいものらしくすっと抵抗もなく建物を昇り始めた。回数表示が目まぐるしく変わると、すぐに目的階で扉が開いた。
エレベーターを出ると左右に通路が伸びており、案内表示板に従って部屋番号があるほうへと歩いて行った。その間も等間隔に監視カメラが設置されている様子を見ると、別に悪いことをしているわけでもないのに、なんとなく居心地が悪かった。唯人はそそくさと部屋番号の前までたどり着くとインターフォンを鳴らすとすぐに応答があった。
「来たね」
扉が開くと、ジャージ姿の梨乃が扉を押し開けた。
「とりあえずこれを届けに来たから」
言うと唯人は茶封筒を差し出した。
「これはどうも」
若干ふらふらしながらも受け取ると、梨乃は唯人を導きいれた。玄関は靴箱がおいてあり、正面には廊下があり、そこに扉が五つあった。
「これ渡したし帰るから」
唯人は扉に手をかけると、
「せっかく来たんだ。もうちょっといてくれ」
そう言われて、唯人は靴を脱いで上がり込んだ。
「部屋の上に、倉庫とか寝室とかトイレとか洗面所とかリビングとか、全部書いてあるのな」
唯人は思ったことを口に出した。
「私はこう見えても几帳面だからな。なんだか、分類わけしておきたくなる」
梨乃はリビングに入る。リビングには調度品といえるものはシンプルなものでそろえられていた。壁にはテレビがかけられ、その前にはローテーブルとソファが置かれる。淡い緑のカーテンが引かれ、食卓は木目調の趣味の良いものだった。
「部屋、綺麗だな」
「散らかすようなものないからな。テレビなんてあるだけでほとんど使ってない。一応、以前の家から持ってきたゲーム機は接続してあるが、ここではパソコンでするからあまり使ってない」
「そうか」
唯人は何も手土産を持参していないことに気が付き、先ほど山下からもらったジュースを横流しすることにした。
「水分採れよ」
いかにもこのために買ってきたかのようにオレンジジュースを差し出すと、梨乃は礼を言って受け取った。
「意外と気が利くのだな」
きわめて平静に努めて、
「何回かの外食で、毎回オレンジジュースを頼んでいたからな。飲み物がないと悪いと思ってさ」
嘘は見抜かれなかった。くれたのがオレンジジュースだったことを山下に感謝しながら問いかけた。
「そう言えば、大丈夫か? ずいぶんしんどそうだけど」
クーラーが程よく効いている室内は快適だった。
「そういえばって、あなた。まあ、そこそこよ。毎年この季節には体調を崩すのよ。多分、一週間かそこらで治ると思うけど」
「それなら、いいんだ。一人暮らしで倒れでもしたら大変だろうし」
「心配してくれたんだ」
じっと顔を見つめる梨乃に耐え切れなくなって白状した。
「メールと電話はあったから学校に来てないのには気づいてなかった」
梨乃は顔をそむけると、
「そうだろうね」
言った。
「別に心配してほしいわけじゃないからいいけど」
「あのな、無表情で平坦な声で言うのやめないか? 怖いんだけど。ちょっとくらいすねた感じで言ってくれると印象ましなんだが」
「べ、別に心配なんかしてほしいわけじゃないんだからね」
棒読みである。若干表情はむっとしたふうを再現しようと努力しているのは分かる。
「それはツンデレっていうのを再現しきれていない。それに来てくれて嬉しいの裏返しだぞ。演技するならもうちょっとクオリティーをだな」
「そんなものを求めるな。もう結構疲れているんだ。しかも、ちゃんとすねた顔をしておいただろうが」
「いや、ほとんど変わってないわ。それに多分他のやつじゃ変化に気づきもしないわ!」
「自分は分かるっていう感じだな」
「そりゃあ、なんとなくは読み取れてるわ。自分でも意外なことにな」
そこで、またふらふらし始めた梨乃をソファに座らせる。
「ちゃんと食べてるか?」
「食欲があまりなくてな。それに作る元気もなくてリンゴとバナナをかじっている」
「それじゃ、良くならんだろ。家族に連絡したか?」
ここで、梨乃は初めて動揺したように、
「あいつらは家族でも何でもない」
ローテーブルに置かれた家族写真をにらみつけて言った。今までにない激しい憎悪の予感がして、すこし後悔した。唯人はにらみつける先の家族写真を伏せて、梨乃をソファに横たえた。
「おかゆ作ってやるから食べろ。食器とか米とか勝手に使わせてもらうから」
先ほどの憎しみを霧散させた梨乃は、
「ありがとう。流し台の下に土鍋があるから使ってくれ。米は電子レンジの下だ」
唯人はうなずくと、近くにあった毛布を梨乃にかけた。キッチンに向かうと言われた通りの場所から土鍋と米、冷蔵庫から梅干しや昆布を見つけてきて、皿に出した。
先ほどの激しい感情の露呈に、動揺していた。あれほど、無表情で平坦な声色の梨乃が感情をあらわにしていたのが意外だった。見たこともないほどに顔がはっきりと歪められているのには驚いた。
では写真など飾らなければ言いじゃないか、と唯人は思った。あれほど憎んでいる相手だというのに、写真を飾る意味などあろうか。
唯人は米を研ぎ、水を入れると土鍋を火にかけた。しばらく時間があるな、と思った唯人は薬缶に水を入れて麦茶のパックを放り込んだ。冷蔵庫の中にはほとんど食材がなかったばかりか、飲み物もなかった。二リットルの容器に残り僅かしか麦茶がなかった。
しばらくしてお粥が完成すると、梨乃のいるソファに運んだ。ずっと起きていたらしい梨乃は、体を起こすとよそわれた茶碗に梅干しを載せて、スプーンですくって口に入れた。嚥下すると意外そうに、
「うまいもんだな。きちんとできているじゃないか。土鍋だと早くできるからいいだろ? あとはふうふうあーんがあれば合格だな」
「俺がおかゆの一つも作れない男に見えたのか? 料理は一応できるほうだ。それとふうふうあーんって望んでるか?」
「いや、一度も作り方を聞いてこなかったのでな。あきらめて炊飯器のおかゆボタンで作るかと思ったが? あと定番なだけで望んでいない自分のペースで食べたいからな」
「それも考えたが、土鍋の場所を教えられたのに炊飯器で作るとなると負けた気がするじゃないか。おかゆの一つも作れないなどというレッテルは貼られたくないからな」
「なるほどな」
久しぶりにまともなものにありついたかのように食べているのを見て、食欲がないとか言っていたけど、出せば食べるんだな、と唯人は思った。黙々と食べ続けて完食したのを見て、
「足りなかったか? なんだったらもうちょっと作るけど」
その呼びかけに、
「大丈夫だ。十分食べたから、おなかいっぱいだ」
「それじゃ、片づけてくるから」
唯人は鍋と茶碗を流し台に置き、洗剤で洗った。
「ありがとう、助かった。実を言うと食欲がなかったわけではなかったが、作る気にもなれないでいただけだ」
ソファのもとに戻ると梨乃はそう言った。すでに写真立ては起こされ、それを見つめていた。唯人は、どうして伏せたままにしておかなかったのだろうか、あれほどの目で見ておきながらまだ見ている。別に嫌ってるわけじゃないのかもしれないな、と思った。
「そう言えばこのマンションすごいな。セキュリティは厳しいのを選んだからな。金に糸目はつけていない。私が払うわけじゃないからな」
「ふーん。実家は金持ちなんだな」
「そうだな。でないとこんなところに住んでられない」
忌々しげな声を感じた。ここで、どうして一人暮らしなのか、とか家族はどうした、とか聞いてみたい気もしたが、それは踏み込んではいけない領域な気がして、他人としての境界線を踏み越えないように注意した。
「あと、どれくらいで直りそうだ?」
少し悩むと、
「一週間もかからないだろうな」
この言葉に唯人は、自分でも何言ってるんだろうと思いながら、思わず、
「じゃあ、明日も晩御飯作りに来ようか?」
声をかけた。
「それじゃあ、よろしく頼む」
意外なことに梨乃はすんなりと受け入れた。熱があると弱気になるのか、それともまったく気にしていないのか知らないが、こちらを見ていった。それからついでとばかりに、
「汗をかいて気持ち悪いからタオルを絞ってくれないか? 洗面所にタオルはあるから」
「了解。寝室に行ったらどうだ? 着替えもありそうだし」
「そうだな。肩を貸してくれると助かる」
肩を借りなければならないほどに弱っていることに驚きながら唯人は、梨乃が立ち上がるのに手を貸してから腕を肩に回させ、寝室へと連れて行った。
寝室は大いに散らかっていた。奥には大きなベッドが据え付けられ、入り口近くの壁にはパソコンがあった。以前の話で、高性能なパソコンだと聞いていたが、その大きさに驚いた。地面にちりばめられた服や紙をまるで地雷を気にするようによけて歩いた。梨乃は気にするそぶりも見せずにそれらを踏みつけてベッドへと向かっていった。
それから唯人は洗面所に向かいタオルを濡らす。風呂場から桶を一つ拝借して、その中に入れて寝室に運んで行った。すでに梨乃は着替えのジャージと下着をベッドの上に並べていた。
「これでいいか?」
「ありがとう、助かった。しかし、先ほど整理が好きだとか言っておきながらこの惨状は驚いただろう?」
「まあ、しんどい時にはこうなるだろうさ。仕方ないことだろうな。まあ、端に積むとかしておけばいい、特に紙ならパソコンデスクに積んでおけよ、とは思ったけれど」
「もともとはそうしてあったんだが換気のために窓を開けたらこうなった。高層階だから風通しがいいのかもしれないな」
なんでもないといった風に言って、唯人から桶を受け取ると服に手をかけて、
「いつまで見てるつもりだ?」
じっと見られた。唯人は慌てて部屋から出ると、扉を閉めて前に座った。スマートフォンにメールを知らせる通知が来ているのに気が付いた。香織が、家に帰っていないことに気が付いてメールをよこしていたのだった。唯人は、少し出かけてるだけだから大丈夫と返信すると、すでに時刻が十八時三十分を回っていることに気が付いて、いつもならもう一時間早くに帰ってるなと思った。
「そこにいるか?」
「いるけど、どうした」
声をかけられたのは十五分後だった。ネットニュースを読んで時間をつぶしていた。
「着替え終わったから入ってきていい」
「はいよ」
扉を開けると先ほどとは違うジャージに着替えていた。梨乃は着替えた衣類を桶の上に乗せると、
「洗濯かごに入れておいてくれ。あとは、そうだな。着替えた脱ぎたての下着もあるから使っていいぞ」
「真顔で言うのやめろ。使わないからな」
「エロゲでは常套句なのだがな。そしてそのあと、襲われると」
ひらひらと手を振る梨乃に、
「なんだ、襲われたいのか? あと何度も言うがエロゲ基準にするな。俺がお前を襲うことはないだろうさ。しかもこの熱が出ているところに付け込んでなんて」
「そうだろうから言ってるんだ。別に洗えばいいから使ってもいいというのは本心だぞ? 洗濯はしておいてくれればそれでいい」
なおもしつこい梨乃から桶を奪い取ると洗面所の洗濯籠に投げ入れた。唯人は、こいつは何で無表情にこんなことが言えるのだろうかなどと考えていた。何を考えているか分からない。しかし、家族への憎悪は本物だ。それと同時に何かすがるような気持ちも持ているのかもしれない。
考えながら部屋に戻ると、床に散らばった紙を集めていた。
「それは俺が集めておくからベッドに寝転んでおけよ。ふらふらしながら集めてるのをみていて手伝わないとなんだか悪い気がする」
「それじゃあ、よろしく頼むよ。その服たちは端に寄せておいてくれたらいいから」
「はいはい」
唯人は何か印刷された紙を拾い集める。
「中は見ないでくれよ」
「見ないよ」
言われたとおりに機械的に拾い集めてパソコンデスクの上に置いた。服は集めて畳み、端に寄せておいた。
「意外と世話焼きなんだな、あなたは」
「そうか? 散らかっているのが気持ち悪いだけだが、自分でもここで片付けすることになるとは思ってなかった。足の踏み場もないから仕方なくだ」
「そうか。どちらにせよありがとう。今度昼ご飯でもごちそうするよ」
「楽しみにしておくよ」
唯人は、用は済んだとばかりに部屋から出ようとした。
「ちょっと待ってくれ」
梨乃の呼び止めにいぶかしげな顔を向けると、
「寝るまで横で話でもしてくれないか? ここのマンションはオートロックだから帰るときはそのままにしてくれればカギが閉まる。それに少し暇なんだ」
亮太の意外にさみしがりかもしれないという言葉が脳裏を走る。確かに、病気の時は心細くなることがある。家にはたいてい父がいないから香織たちが見舞いに来てくれると無性にうれしくなる時があった。
そう思い、梨乃も同じような気持ちなんかもしれない。家族に頼れないどころか、友人もいないとなればそうだろう。唯人はそう思うと、
「かまわない」
今日する予定の勉強はどうせ土曜日に回すんだから、少しくらい遅くなってもかまわないだろうと結論付けて、そう答えたのだ。
「何の話がしたいんだ?」
布団の中の梨乃に問いかける。
「面白い話をしろというのは、地獄の振りではあるな。そうだな、あなたの友人の話でも聞かせてくれると嬉しい。今までまともな友人などいたことがないからな。そういう風にふるまっていたのは自分だろうにな。こういう時に来てくれる友人がいないのは寂しいというのと、自分を心配する友人がいないの気が楽だというのと、相反する感情があるものだよ」
梨乃はそう言って口元まで覆い隠すように布団を引き上げた。
「そうだな。俺の友人は変人ばかりだけど面白いんだよ」
どうしてこんな話をこいつにしているのだろう。唯人は疑問を感じながらもベッドに腰かけて話した。そして、しばらくして寝息が聞こえてくる。
「ようやく寝たか」
顔は布団から出ていてはっきりと見える。常夜灯が照らす中、自分がどうしても寝顔に目を向けてしまうことを自覚する。離れようとすると、梨乃の手ががっちりと裾をつかんでいることに気が付く。仕方なく隣に座ると窓の外を見ているとだんだんと眠気が襲ってきて、瞼が下りて、意識を手放した。
「…………」
遠くで歌う声が聞こえる。歌う内容は分からないが、美しい音色に思わずうっとりと聞き入ってしまう。唯人はいつの間にか寝込んでしまっていた。気が付かないうちにベッドに横になっていた。
「起きたのか?」
寝返りを打つと、そこには上半身を起こして歌を口ずさんでいた梨乃がいた。
「悪い、いつの間にか寝てた」
謝罪すると、
「私が裾をつかんでいたせいだろう? あなたは悪くない」
梨乃は言った。ベッドから立ち上がってカーテンを開けると、月が見えていた。
「月が綺麗ですね」
唯人は梨乃に言った。
「夏目漱石の訳なのか、そのままの意味なのか」
「そのままの意味だよ。今日は満月ではないけれど、雲もなくはっきりと見える」
「確かに、月が綺麗ですね」
梨乃の言葉に、
「それはどっちの意味だ?」
問うと、
「どっちの意味でしょうかね」
「だから、それはいたずらっぽく笑って言えよ」
「精一杯だが?」
「そうか」
カーテンを閉めようとすると、
「そのままにしておいてくれ。だいぶ楽になったから、もう少し見ていたい」
「じゃあ、このままにしておく」
唯人は答えてからスマートフォンをスリープ状態から起動する。
「もう真夜中じゃないか」
時刻は零時を示していた。いくら活気のある場所とはいってもすでにほとんどの施設は眠りについている。
「もう真夜中だな。今日は泊まって行けばどうだ?」
言う梨乃に、
「それはさすがにまずいだろ。第一に学校があるんだから家に帰って風呂に入って着替えたい」
「確かにそうだな。長々と引き留めて悪かったな」
「まあ、いいさ」
去ろうとする唯人に、
「なぜ人は生きているんだ?」
あの日の問いかけがなされた。唯人は、あの日は嫌々生かされているなんて答えたっけな、と思い返した。
「それは、前回の答えとしては嫌々生かされているだったわけだが、今回は少し回答が変わるかもしれないな」
「どんな答えに?」
首をかしげる梨乃に答える。
「生きる意味を探すために生きているんじゃないか?」
唯人は答えると、
「前回よりも詰まらない答えになっているな。そんなことはきっと哲学者が言う言葉だぞ」
「確かにつまらないな。でも、面白さを求めるためにこの問いをして回っているわけでもないんだろう?」
唯人の言葉に、月を見たままの梨乃は、
「そうだな」
ただそう答えた。
「どうして生きてるんだ?」
唯人は同じ質問を返す。
「どうして……か。どうして生きてるんだろうな、私は。そもそも生きている価値はあるんだろうか。これは生かされているだけじゃないのか。それこそ答えは出ないさ」
言葉を切る。
「だからこそ、他人に答えを求めてばかりなんだろな。最初にあなたが言ったとおりに、人それぞれ生きる目的は違うだろうな。もちろん、死にたくて死ねなくて生きているのもいるだろうがな。私は、」
梨乃は唯人を見た。
「私は、生かされているから生きているんだ。私に生きる価値なんて問うだけ無駄なんだろうな。何の価値もない、空虚で、作られた、感情の抜け落ちた、無表情な、道具として生かされているんだよ。生きているわけじゃない。とっくに私は死んでいるんだろうな」
「それって、」
真意を確かめたい気がした。しかし、
「……何でもない」
唯人は、ここで何を言っても無駄だし、何も聞かないほうがいいと思った。何でもない、とただ答えて部屋から出た。梨乃は再び月を見ていて、その様子はまるで人形のように美しかった。
暗い、全体が寝静まった住宅地は、これでもかというくらい無言の圧力をかけているように感じた。実際はそんなことはない。ただあるだけだ。
しかし、何も答えない、うすぼんやりとした切れかけの電灯以外は光のない住宅地にたどり着いた唯人は、先ほどの問いと答えを思い出して、どうしても陰鬱な気分に沈まざるを得なかったのだ。
家の前にたどり着くと、鍵を開けて中に入った。家には誰もいない静寂が満ちていた。そうだ、誰もいないのだ。唯人は無性に悲しくなった。誰もいないことにではなく、それに何も感じない自分に。
幼いころ母を亡くしてから、ほとんど一人だった。幼馴染はいたけれど、父親からの愛情は、その時から感じられなった。父親は、母が死んでから働きづめで家に誰もいないことに慣れきってしまった。祖父母とは疎遠だった。
父親に自分を見てほしかったのかもしれない。そのころから勉強を一生懸命にするようになった。しかし、成績で褒められることもけなされることもなかった。ただ、見てほしかった子供は裏切られた。そこからは惰性で勉強を続けて、気が付けばほとんど頂上にいた。全国順位は一桁で、それでも父親は見てくれなかった。
きっともうあきらめている。そう、家族をあきらめているのだ。梨乃のような憎悪も、普通の価値のように愛情も、憐憫も、慈愛も何も感じず。何も期待していないのだ。どうせなにもかもが停滞したままだ。
唯人は風呂に入ってシャワーを浴びた。服を着替え、リビングにあったパンを一切れかじるとスマートフォンにメールがきているのに気が付いた。
「夏休み最初の土曜日、出かけよう」
時間はまだまだあるはずなのに、早くから約束を取り付けようとしていた。用事があるわけではない唯人は、
「分かった。遊園地の時に待ち合わせした駅でいいのか?」
すぐに返信された。
「私の家の近くの駅前に集合してくれ、噴水広場の時計の前に」
「了解」
唯人はそれだけ返信するとソファに身を投げ出した。なんだか、猛烈に疲れた気がした。
目をさすような光に、カーテンを閉め忘れたか、と思うと、部屋の照明をつけたままにして寝ていたことが分かった。昨日ソファで寝てしまったらしい。結論を導くと、カーテンを開けた。まだ、時刻は六時を指したばかりだった。制服に着替えると、だらだらと朝食をとり、テレビをつけた。天気予報では晴れ。確かにその通りになりそうだな、と思った。鞄の中身を自室で詰め替えて、身支度を整えて家を出ると、そこには香織がいた。
「昨日、遅かったんだね」
「そうだな、一時くらいだった」
「どこに行ってたの?」
「野暮用だ」
「刑部さんの家でしょ?」
香織の言葉に、
「なんだ、知ってるんじゃないか」
返した。
「亮太から話を聞いたの。あまりにも遅いから、どこにいるんだろうって」
「まあ、教室で話したからな」
「何かしてたの?」
うかがうような目で見てから、
「何かあったの?」
言い換えた。
「別に何もしてないし、何もない。ただ、熱出してたから飯作って、話して、それから帰っただけだ」
「ふうん」
それじゃいいけど、といった風に歩き出すと、
「でも、困ったことがあったら言ってね」
笑顔で、
「私たち、幼馴染なんだから。ゆい君は大切な時に人にあんまり頼らないっていうのは長い付き合いなんだから知ってるよ。特に、本当に大切なことは。だから、言っておくね。私じゃなくてもいい。亮太でも春香でも浩志でも、誰でもいいから、頼ってね。そして私が頼ったら助けてね」
その言葉に、唯人は言った。
「分かってる。何かあったら頼るから心配するな。今日はさっそく、香織に頼った。多分外にいるんだろうなって思いながら出たから。十分助けられてるよ」
「そっか」
それだけ言うと、二人は学校へと向かう道に歩みを進めた。
第二節
「いらっしゃい。夜遅くに」
香織が唯人の家を訪ねるととっくに来るのが分かっていたかのように出迎えられた。
「どうして来ると思ったの?」
香織は疑問をぶつけた。
「私が頼ったら助けてって付け加えたときに、何か悩みでもあるんだろうなって」
「悩みの内容まで分かってる?」
「分かってる、つもりだ。何年付き合いがあると思うんだ。大抵のことは分かっているつもりだ」
唯人の言葉に、隠そうとしていたはずの人にはとっくにばれていたんだ。いかにも恋人らしい行動をとって隠そうとしてみたが不自然さはなかったはずだがどうにも敵わないらしい。
「それで、私が悩んでることを知ってて放っておいたんだ?」
「絶対に話に来ると思ってたから、確信があったから。でも夜に来るのは想定外だったな」
「そっか、そこは分からなかったんだ」
香織はリビングに歩きながらそう呟いた。唯人は冷たいココアを入れてテーブルに置いた。
「とりあえずこれでも飲めよ」
「熱いココアじゃなくて冷たいココアなのね」
「暑いからな」
冷房のスイッチを入れると椅子に腰を下ろした唯人の前の席に腰を下ろした。冷たい飲み物が身体に染み渡るように喉を通る。パジャマ姿で来たことに関しては何も触れないのは唯人らしいなと思った。別に女として見られていないのだから当たり前だろう。
「あのね、ゆい君。私と亮太は今別れてるの」
「だろうね」
「私から言い出したの」
「だろうね」
「それで秘密にしてそのうち復縁しようと思ってたの」
「分かってた」
本当に敵わないなと思いながらも続けた。
「亮太が私を本当に好きでいてくれているのは分かってると思う。でも私自身がどうなのか確証が持てないの。今まで最初に背中を押されてからずっと一緒にいて、一緒にいるのが当たり前で、最初は好きだったんだと思う。でも最近は本当にそうなのか分かってないの」
「それでどうしろと?」
「私がどういう人間で、どうして亮太とあれだけ頻繁にセックスしているか知ってるよね?」
「知ってる。だからと言ってどうこうしようとは思わない。気持ち悪いとも思わない。ただ、そうなんだ程度のことしか考えない。幼馴染で付き合いが長いからな。学校では隠し通せてるみたいだし」
「それで行為だけが、セックスをするためだけの相手としての存在だけが目的になってるんじゃないかって思って。それでそうじゃないことを証明したいの」
香織は息を吐いた。
「私と……」
そこで唯人が言葉を切った。
「俺はそんなつもりはないぞ。お前とはセックスしない。それは分かってるだろうが」
先に言うことはバレていたのだ。分かってもいた。唯人がそんな人間じゃないことも。それでも一度だけ試してみたかった。亮太以外の人間で。
「最後まで言ってないけど」
「言わなくても分かる。幼馴染だからな。でも止めておけ。言うな。俺としてしまったらもう幼馴染だとか友達だとか、そういう純粋な関係には戻れなくなるぞ。今の関係も壊れるだろうな。そこまでして俺とする価値はないだろ?」
「確かにそうかもね。でも誰かと、亮太以外と……」
唯人はいつになく真剣なまなざしで、
「亮太以外としようがどうしようが俺には関係ないし、金をもらって一夜の関係になってもどうでもいいかもしれない。でも亮太のことは考えてやれよ。知らない奴として、それで自分より良かった。自分でなくても良かったとお前が気が付いたらどうしようもないぞ。あいつが求めるのはお前だ。だから壊れてしまうかもしれない」
「壊れるだなんて……」
「いいや、壊れるだろうな。捨てられて生きる希望を失って、不用品になった自分を自分で嘲笑して」
香織は唯人の言葉に確信めいたものを感じていた。確かに亮太が自分に依存しているだろうし、それを知っている。だからこそ依存相手は自分でなくてもいいのではないか。依存先を変えればもっと幸せになれるのではないか。そう感じてしまう。
「浩志のもとには絶対に行くなよ」
「先に読まれてた?」
「今、辛いあいつのもとにつけこむのは簡単かもしれない。だがそれこそ二度と戻れなくなるぞ。春香と浩志の想いには気が付いているのだろう? 春香は許さないだろうし、浩志も後悔して終わるぞ。この関係を、幼馴染という枠組みも何もかも失ってバラバラになって二度と関わらない他人になるだろうな。それはお前だけじゃなくて、多分俺たち全員が」
「そうかもね。ココア御馳走様」
香織は席を立った。唯人に目を向けた。確かに正しい。どこまでも正論なんだろう。でもどうすればいいんだ。中途半端な状態でどうしろっていうんだろう。
「復縁しろ」
思考を読んだように言われた。
「多分十分好き同士だよ。俺と刑部なんかよりもずっとな」
「歪んだ依存関係なんか気持ち悪くない?」
香織は不安を押し殺しながら聞いた。普通は気持ち悪いのだろう。しかし、唯人は、
「それは人それぞれだろう? 人という字は支えあって生きているというじゃないか。依存だって支えあっていることに違いはないさ」
「そっか」
香織は家に帰るしかなかった。
第三節
「もう嫌だ」
薄暗い部屋。カーテンは閉め切られている。浩志は一人で呻いていた。呻いているというよりは怨嗟を口にしていたといったほうが正しいかもしれない。
葬式があってから散々な目に遭っていた。遺言状の中身が問題だったのかもしれない。全ての財産は浩志に譲ると書かれていた。自分で稼げていた浩志は必要以上のものだった。別に形見分けで少しの遺品がもらえれば良かった。しかし、全てが自分のものになってしまったのだから他の親類から見れば気に入らないことだろう。
そこそこに貯めていたらしい財産を少しでも手に入れられればそれで良いと思うのだろう。高校生に対して泥棒だとか全部放棄しろだとか、譲ると一筆書けだとか。人として恥ずかしくはないのだろうか。浩志は思いながらも弁護士事務所の原本を確認するために両親といとこの両親と共にそこに赴いた。そしてそこで遺言状とは別に個人的な手紙が一人ずつ保管されていた。
自分たちの命が交通事故に遭おうが遭うまいが短いと感じていたのだろうか。準備周到さに驚かされた。
そしてその手紙に書かれていたのは、財産は誰にも渡さず自分のために使いなさい、貯めておくだけでも良いし、形あるものは売り払っても良い、だがお前のことを大切に思ってもいない血の繋がった他人にだけは渡してはならないという内容だった。
だからこそ、財産を全て渡して楽になることは祖父母の遺言に背くことになるし、全て放棄しろと迫る他人にだけは渡してしまいたくないと思った。渡せば楽になるという感情と渡してはならないという感情に板挟みになっていた。
イーサネットケーブルと電話線は引き抜き、スマートフォンの電源は切っていた。外界と関わればすぐに金を、財産をせびられ、かといってずっと閉じこもるかといわれればそういうわけにもいかなかった。
この状態は限界が近いのだろうなと自分の精神が摩耗していることを感じていた。これ以上は心が壊れてしまうかもしれない。
冷蔵庫に入っている残り少ない食料と飲料を目にした。麦茶をコップに注いで飲もうかと思ったその時、ふと果物ナイフが目に入った。魔が差したのかもしれない。浩志はナイフを手にしてその場で手首に突き刺そうとした。
これで楽になれるのかもしれない。そう思い晴れ晴れとした気分になる。そして手首に突き刺さる……ことはなかった。ナイフを持っていた手に衝撃が加わり取り落とした。誰もいないはずなのにと考えながらも虚ろな目で正体を確かめる。
「どうしてここに?」
春香の姿を目にした。どうやってここに入ってきたのだろうかと思いながら問うた。
「いつかこうなるんじゃないかって思って」
「どうやって?」
「管理人さんに事情を話して入れてもらったの。どうしてもって無理を言って。でも間に合って良かった。私、今日来てなかったら一生後悔する羽目になるところだったよ」
「僕には金以外の価値なんてないだろう? 春香が後悔することなんてないだろう?」
「そんなことないよ」
目に涙を貯めながら言った。
「絶対にそんなことない。お金なんてどうでも良いの。そこに価値なんて見出してない。こうちゃん自身にしか価値を感じてなんていない」
「そんなこと口先だけではどうとでも言えるだろ」
浩志は自分が嫌なことを言っていることに気が付いていた。しかし、止めることなどできなかった。
「葬式ですら金の話。遺言状のせいで人に渡すこともできない。それなのに電話とメールは頻繁で、家にすら来ようとする。金しかない」
嗚咽を自身が漏らしていることに気が付いていた。どうすることもできない怒りと諦めが涙として流れる。
「僕なんていなくなれば……」
突然唇が塞がれた。柔らかい感触が皮膚を通して伝わる。しっとりと濡れたそれが無理やりに言葉を止めていた。唇が開かれて口腔内が蹂躙される。逃れようとしてもがっしりと顔を押さえつけられてそれもできない。
しばらくしてすっと離れる。名残を惜しむように細い唾液がつうと口元から口元へと橋を架けていた。
「これで証明できた?」
春香はいつになく真剣な目で、低い声で、ふわふわとした雰囲気を消して囁いた。
「なんで……?」
浩志は困惑と驚きを声に乗せた。
「私が男性恐怖症だってこと知ってるからどうしてこんなことをしたのか分からない? そんなの決まってるじゃない。それすら乗り越えてこうちゃん自身に価値を感じてるからだよ。私にとっては唯一無二なの。だから恐怖なんて乗り越えられる。優しいこうちゃんは怖くなんてない」
ぐいと手を引っ張られた。そのまま寝室へと運ばれベッドに押し倒された。普段なら絶対にしない行為に声も出なかった。
「これで証明できる? 私はこうちゃんが好きなの。どうしようもない想いなの。こうしているのが幸せなの。優しいから私からの行動を待っていてくれたんでしょう? 恐怖が克服できたときに行動するのを。だけど今なの。今じゃないと駄目なの。大好きなこうちゃんが壊れてしまうのを目の前で見て、それでも知らない顔して気が付かないふりをして、失って。そんなの絶対に許せない。だから、」
春香は妖艶な笑みを浮かべた。
「ちゃんと証明して、口先だけじゃないこと解らせるから。解ってもらいたいから」
するりと服を落とした。暗い部屋の中で肌が映えた。小さな胸元を隠すこともなくさらけ出している。下着を脱いでいた。呆然とする浩志は服をなされるままに脱がされ、
「抱いて。私を」
こう言われていた。答えて、
「僕は春香のことが好きだよ。でも傷つけたくない。今は優しくできない」
「それでもいいよ。好きにして」
「もう顔を見るのが嫌になるかもしれない。二度と近づきたくないと思うかもしれないよ。あの時の、小学校の時にもう少しで犯されるところだった体験以上のことなんだよ。僕に犯されるんだよ?」
「それで良いの。私はこうちゃんに犯されたい。だから、乱暴でもいいから」
浩志は春香を抱きしめて逆に押し倒していた。
「後悔しても知らないよ」
「しないよ。後悔なんて」
二人は一つになった。
ベッドに寝転がる。二人とも汗だくで疲れ果てていた。
「僕と付き合ってくれるってことで良いんだよね?」
浩志は訊ねる。
「うんとねー。付き合わないよー。今はー」
「どういうこと?」
「高校を卒業するときにね、まだ好きだったら付き合ってほしいなってー」
「どうして?」
「勉強も仕事もしなくちゃだし、それにこういうことを次にするのは卒業してからかなって」
浩志は春香の意思を尊重することにして頷いた。それから隣の春香に笑いかけた。
「ありがと」
「どういたしまして」