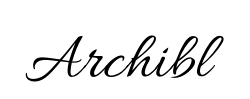第一節
夏も始まったばかりで、一週間も経っていない最初の土曜日。夏休み前の七月前半ですら三十度を超えていたが、まだこれからが本番と余力を残し、あれから三度ほど温度を上げた今日この頃。異常なまでのセミが大合唱をしている。
唯人は、この暑さと騒音との相乗効果で苛立ちを募らせ、そろそろ怒鳴りそうにないながら、街の中では一番栄えた場所であるこの駅前に立っていた。もちろんこれは、少し前に梨乃と出かける約束をしていて、その約束を果たすために待ち合わせ時間に合わせてきていた。
この暑さになるならば近辺の喫茶店での待ち合わせにでもしてくれればいいのに、と思わなくもないが、駅前の噴水広場、そこにある時計の前で待ち合わせをしようと約束してしまっていたがためにしかたなくそこに立っているのである。
メールで場所を変えないかと連絡をしてみたものの、ぜひそこでとの返答があったから困ったものである。あの時一方的に、ここで待ち合わせに変えると通告していたら場所は変わっていただろうかと今更遅い後悔をするが、それも今更のことであった。
唯人は、夏らしい白いシャツを着て、デニム生地のズボンをはいていた。かばんは小さめの肩掛けのもので、中には財布とスマートフォンが入っているだけの軽いものだった。帽子やサングラスをしていればましだったかもしれないと思うが、ここ数年は暑い日に外に出るのは学校だけと決めていたので、そのようなものは持ち合わせていなかった。
待ち合わせの五分前にはすでに額から汗を滴らせ、ハンカチで拭いながら待っていたのである。肝心の梨乃は、時間きっちりになってから現れた。
長袖の生地の薄い、白いワンピースに日傘という組み合わせで現れた彼女は、自身の白い肌や髪と相まって、なんだか色とりどりの駅前に生じた、キャンパス上の余白のように感じられた。小さなポシェットを肩から掛けてこちらを見て、手を挙げた。
「ごめん、待ったかな?」
「待った、五分ほど」
いつかと同じようなやり取りをすると、
「五分は待ったうちに入らないし、普通は『全然待ってないよ、今来たところ』とでも言うものだがな」
ふいっと、そっぽを向きながら言った。駅前にはまだ朝の時間とは言え、土曜日だろうに夏休みに入ったのは子供だけだと主張するかのようにスーツ姿のサラリーマンが少々行き来していて、一部に混じる夏休みであろう子供や休みの家族連れもちらほら見られた。
唯人も梨乃も自分の容姿の良さは自覚しているつもりだったが、向けられる視線は多く、それに耐えかねた梨乃は、
「とりあえず喫茶店に入ろうか」
そう言った。
駅前にはいくつかの喫茶店が存在している。誰もが知る有名チェーン店から個人経営の小さな隠れ家的なところまでいろいろと目についたが、梨乃は一本裏に入ったところにある、ほとんど中央部だというのにそれを感じさせないような小さな喫茶店に入った。
店内は磨き上げられた木目調の優しい色合いの床の上に、いくつかのアンティークのテーブルセット、カウンター席の目の前には黒々としたつややかなコーヒー豆入りの瓶が並んで、奥の戸棚にはコーヒーカップが並んでいた。カウンターの向こう側に座る店主は、程よいひげを蓄えた優しげな表情で、店の正装なのだろうか、白いシャツに黒いズボン、その上に黒のエプロンを着て蝶ネクタイをつけていた。年齢も六十代後半から七十代前半に見えるので、趣味でやっている店を体現しているようだった。
客は時間のせいか、それとも曜日のせいか、一人がカウンターに座るだけで、残りは空席だった。店内には、スピーカーからごく小さな音でヴァイオリンの演奏が流れており、落ち着いた空間を演出していた。
「お好きな席へどうぞ」
店主からそう告げられると、梨乃は迷うことなく入り口から一番離れた、奥まった席へと向かい、腰を落ち着けた。唯人はその向かいに座り、程よい空調で汗が止まったことを自覚しながらメニューを見た。
「ご注文はお決まりですか?」
その問いかけに、すでに決まっているらしい梨乃は唯人をちらりと見て、頷くのを待ってから答えた。
「私はレモンティーで」
それに続けて、
「アイスコーヒーで」
そう答えた。これだけコーヒーの豆が置いてあって、いかにもコーヒーにこだわっていそうな店で、慣れた感じでレモンティーを頼む梨乃を見て、コーヒーが嫌いなのかななどと勝手に思考を巡らせると、メニューをメニュー立てに戻した。
何も話さなうちに少し時間が過ぎ、注文した飲み物が届くと、唯人はそれで口を湿らせてから、そう言えばコーヒーも紅茶も利尿作用があるから暑い日の水分補給にはあまり向かないのだったか、などと思いながら話しかけた。
「この喫茶店、よく来るのか?」
その問いに、すでにレモンティーを四分の一飲み終わった梨乃は、ストローから口を離して答えた。
「時々来るな。私はそもそも外に出ることは少ないが、コーヒーや紅茶を飲むのが好きで、喫茶店を回るのが趣味なんだよ。引っ越してきてからすぐにこの近辺の喫茶店をチェーン店から個人店まで回った結果、ここが一番おいしいと感じたからたまに飲みに来るんだ」
以外そうな目で唯人に見られた梨乃は声を潜めて、
「それ以外にも、ここは客が少ないから落ち着くんだ。人からの目線を集めないし、話しかけられることもないからな」
納得の表情を浮かべると、カウンターの向こう側の店主は、
「聞こえてますよ。それに声を潜めて言わなくてもここは趣味のお店ですので、仕入れ分が稼げていればそれでいいのですよ」
にっこりと笑った店主の顔を見てから梨乃は付け足した。
「それに店主は優しいから気に入ったのもある。お勧めのスーパーを教えてくれたり、豆や茶葉の種類の違いを教えてくれたりする」
梨乃はちらりと店主を見ると、これでいいかとばかりに視線を送った。
「そうか、それはよかった」
唯人も空気を読んでそう言うと話を変えた。
「そう言えば、どうして待ち合わせをあんな暑いところにしたんだ? あそこって、日陰はほとんどない上に噴水も常に流れているわけじゃなくて決まった時間に流れるからあんまり涼しくならないだろ? 大体、時計の周辺どころか広場にはベンチすらないから座れないし。最初からここを集合場所にしておけばよかったんじゃないか?」
不満を口にすると、梨乃は手を開いたり閉じたりしながら、
「だって、あそこが一番分かりやすいから。待ち合わせって言っても、家の前に来てもらうとかじゃ面白くないし、ここの住所は正確に知らないし」
そう言い放つ梨乃に対して、
「ネットで調べれば分かることだろうに」
「じゃあ、待ち合わせをしてあなたがきちんと、『待ってないよ』って答えるの期待していたということにしておくよ。それも不合格だったがね」
「別に試験じゃないし、合格を願ってもいない上に、そんなやり取りを望むような仲か?」
「君と私は、一応恋人だろう? それに今回のテストでも私は満点で一位、あなたは二点失点で二位だったじゃない? 勝者に従うのが敗者の務めなんだから、勝者の望むように行動しなさいな。そして、悔しかったらテストで打ち負かしてみなさいな。同じテストなんだからできるはずでしょ、満点回答が」
唯人は悔しい思いを胸にこらえながらも、まあその通りだと納得する一方で質問を返した。
「前回のテストのための学習時間は?」
逡巡しながらもはっきりと、
「多分、ほとんどゼロね。だって、勉強なんて学校の授業を聞くだけだし、テストもそこからしか出ないじゃない? 要は、教科書と授業内容を授業中に丸暗記すればいいのよ」
「ためらいながら答えた結果がそれか? 全世界の一生懸命勉強した人に申し訳ないとか思わないのか?」
「思わないよ。だって、できて当然、できないのが悪いんだから。高校の指導要領以上のことなんて模試でもほとんど出ないんだから校内の試験なんてできて当たり前。できないことを確認するのが試験じゃなくて、できることを確認するのが試験なんだから」
「そうだよな。お前に言った俺が馬鹿だった。だって、できないやつの気持ち分からないもんな」
「ええ、知らないわよ」
淡白で切れ味の良い包丁のような回答に、少しばかりの苛立ちと大半はあきらめと尊敬の思いが心を巡った。唯人は、こういう天才のことを、努力では決して届かない至高の存在というのだろうな、と勝手に思った。
「そう言えば、だいぶ前に……お前の家に行った日の夜から約束していたけど、今日は何かあるのか? それとも気まぐれで今日にしたのか? それと、どこに行く予定なんだか教えてくれると助かるんだが」
唯人の問いかけに、それもそうねといった具合で、レモンティーの四分の一を再びストローで吸い上げると、ふうっと息を吐いた。
「結構前に、ネット通販だからショッピングなんて行かないという話をしたのを覚えているかい?」
「覚えてる」
「だがな、ウィンドウショッピングに興味が湧いたので今回はそれをしにショッピングモールに向かうことにする」
唯人は、アイスコーヒーをいつの間にかすっかり飲み干していた。氷だけのコップからコーヒーを吸い上げようとずずっと音を立てたことに気が付いた。
「あの人ごみに行くのか? 夏休み初めの、しかも土曜日にそんなところに向かうって言うのは、人混みに酔いに行くのか?」
「そうだ。人がいっぱいなのは知っているが、あえて向かおうじゃないか。人がたくさんということは、自動的に私たちも目立たなくなるということだろう? そうすれば、店員に話しかけられずに済む」
唯人は半眼で、
「単純に店員と話すのが嫌なだけじゃないか。確かに服屋の店員は時間があればあるだけ話しかけてくるし、着たくもないようなものを勧めるし、返事をしなければ試着室に案内して着せられるし。碌なことではないのは分かるが、それだけの理由で混んでる時間に行くのか?」
「まあ、後は見るだけで買わないのが最初から決まっている場所では話しかけられる頻度が減って、多少の罪悪感も覚える必要がなくなるからというのもある」
「いや、別にお前がそれでいいならいいんだが」
どうせ見て回った挙句に、荷物持ちをさせられるんだろうなとは思っている。仲のいい幼馴染に女子が二人もいれば荷物持ちをさせられた回数は計り知れないし、片方が服装に頓着しなくても片方が非常に頓着するので、待ち時間、荷物の量、行く回数は非常に多く、着せ替え人形にされる春香も含め、四人で振り回されることが多いものだと唯人は思う。
それにしても遊園地に行ったときにはショッピングのことを否定的に言っていた気がしなくもないがと思った。
「服とかアクセサリーに興味があるのか?」
唯人は尋ねると、
「そりゃあ、人並みには興味がある。なんて言ったって女の子だからね」
相変わらずの表情で言う梨乃に、
「そういう言葉は、ウインクしながらかわいく微笑んで、いたずらっぽく言うのが鉄則だからな」
何度目か分からないやり取りに、
「そうか、確かにウィンクは必須だな。エロゲのデートイベントの立ち絵でもウィンクしてる率が高い上に、振り返りアングルが多いからな。」
無表情でこれでどうかと言わんばかりに完璧なウィンクを決める。
「あのな、何度も言うけどエロゲ基準にするな。それと、まあ、今回の場合は正しい。ただし現実の女の子はしないだろうな。それをやって見せた点は評価してやってもいいが、その表情は何とかならんのか。可愛く微笑めと教えただろう?」
アルカイックスマイルを浮かべる梨乃がもう一度ウィンクするが、
「あのな、完璧な笑みというか、口元の微笑は最近出来ている気がするが、目元が笑っていない。怖いからやめたほうがいい。まあ、お前は美人だから今の表情の肖像画は売れそうだが」
梨乃は両手を頬に当てて、
「美人だなんて、照れてしまうな」
そういうが、唯人は、
「もうやめてしまえ。照れた表情も見せないで口角ちょっとだけ上げて言われても心境が分からんわ!」
またしても何度も繰り返したやり取りに、唯人は少しだけ安心感を覚えながらも、最初の頃よりとっつきやすいというか、話していて楽しい人間になっていそうだと思った。二人はそれぞれ代金を払うと扉をくぐって外に出た。
外は入った時と変わらず、むしろ少しばかり温度が上がったような気がするが、それくらい暑かった。人通りは変わらず、ただ、一本表に出ると増えた気がした。海にでも行くのか、浮き輪やゴーグルやらが見え隠れする透明なバックを背負った子供や、どこに出かけるともしれないバックパックをパンパンにした父親らしき子供連れ、友達と歓談する高校生。
夏真っ盛りだった。
ショッピングモールは、駅の近くにあった。地上十階建てで、地下には駐車場がある。さほど広くもない土地のためか、上に積み上げる形になっていた。
唯人と梨乃は、先ほどの場所から徒歩で移動して、その場所にたどり着いていた。店自体は、一時間は前から開店しているため入り口で客が待っていたり、店員が並んで挨拶していたりといったことはなかった。自動ドアをくぐると、先ほどの喫茶店よりも低い温度で空調が使用されていて、少し肌寒く感じられる。汗が引けばちょうどいい温度になるのだろうな、と唯人は確信した。
「着いたな」
唯人の呼びかけに、
「着いた」
短く梨乃は答える。
「それで、どこを見たいんだ? 文房具屋か、それとも服屋か?」
「私的には、まず二階から五階の服屋とアクセサリーのお店を見てから、六階の雑貨屋と文房具屋を見て、九階と十階にあるレストランのどこかでご飯を食べたいと思っているんだけれどな」
「それでいいんじゃないか? 昼ごはんさえ食べられれば付き合うから」
その言葉に鷹揚に頷いた梨乃は、先に立って歩き始めた。入口の近くにはエスカレーターが存在しており、それに乗って二階へと進む。二階には、服飾ブランドの専門店が並んでいた。
梨乃は本当に見ているだけらしく、時々唯人にあれが綺麗だとかこれが素敵だというだけで特に手に取ることもなく淡々と進んで行った。
三階を見終わるころにはすでに昼時で、一度最上階に上り昼食をとることにする。
「何を食べたいんだ?」
唯人の問いかけに、
「ラーメン」
と答えると、その暖簾をくぐって入店していった。
「ラーメンっておいしいよね」
梨乃は木製の机に向かって、お冷を両手で包み込んで言った。
「そうだな。ラーメンって三分でも食べられるし、お店の本格的なものも楽しめるから、手軽に食べられる一人暮らしの味方だよな」
唯人はしばしばカップ麺を食べることを示唆した。
「私は健康的じゃないから食べることはないけれど、確かにそうでしょうね」
その答えに、
「そう言えば、料理をごちそうしてくれる話はどうなったんだ? この前家に行ったときは熱で無理だったけど、そのうち楽しみにしてる」
唯人は告げて、
「そうね、機会があれば作ってあげるわ。機会があればだけど」
「それ、絶対にその機会が来ないことを暗に示しているとかそういうことじゃないよな?」
「それはどうだか」
しばらくしてラーメンが卓に届くとしばしすすった。伸びてまずくなる前に、着たらすぐに食べるが信条の唯人は、ものの数分で食べつくした。それから、自分でも意外なほど空腹を感じていたんだと満たされた腹をさすった。
梨乃も残り少しを食べ終えて会計を済ませると、四階に戻った。四階には大して心に刺さるものがなかったらしく、すぐに五階に上った。
「ここのアクセサリーショップ、見てみることにする」
「どうぞごゆっくり」
ひたすら相槌と追随だけを今日の役目としてきたので、特に何を言うでもなく単純にそう告げた。どうせあまり何も買わないのだろうな、と思っていると、唯人は綺麗な貝殻のイヤリングを見つけて、その白い色から、梨乃によく似合うのだろうなと思い、声をかけた。
「これとか似合うんじゃないか? 肌も白いからイヤリングも白で」
少し考えると、
「あなたがそう思うのなら似合うのかもね。じゃあ、これを買おう」
会計にもっていくのを止めて、唯人が購入すると耳につけるように示した。
「よく似合ってるじゃないか」
そう告げる唯人に、
「これくらい自分で買うのに」
「ここは、喜んで『ありがとう、大好き』くらい言う場面だろうに?」
「ありがとう、大好き」
「棒読み真顔をまずはやめい」
口角を最大限引き上げて―とは言っても若干だが―、それで、もう一度同じセリフを繰り返すと、今度は両手でむにっと頬を持ち上げて目じりを下に引っ張った。
「それじゃあ、無理があるだろうが。まあ、言ってみただけだから特に気にする必要はないけどな。別に反応が欲しくて買ったんじゃなくて、単純に買いたくて買っただけだから」
「つけたかったの?」
「自分にじゃないわ! お前につけたかっただけだ」
唯人を指差しながら言う梨乃に反論すると、さっさと歩きだした。
「あとはもう一階上だけか?」
そう問うと、
「あとは上の階と、帰りぎわに買おうと思ってた下の階の商品だけだ」
「そうですか」
唯人はそれに付き従って、階を上がった。上の階、つまり六階の文房具売り場と雑貨売り場は階全体に広がっており、広大だった。天井からは、種別の札が場所を示すように下げられており、一目見ただけでも種類の多さが分かった。
「私、シャーペンの芯とボールペンが欲しかったんだ」
「俺は、のりを見てくる」
二人はしばし分かれて行動することにする。唯人は巨大な売り場をさまよって、目的のものを手に入れると、エスカレーターの付近にはすでに商品を買ったらしい梨乃が見えた。
「お待たせ」
「待った。三分くらい」
「いや、いつもと逆のパターンをやらなくてよろしい。別に待った時間にも入らんだろ、三分なんて」
「五分でも同じことがいえると思うのだけれど」
「確かにな」
エスカレーターを下り、三階に到達すると、そのうちの一店舗にすたすたと入って行った。梨乃の後についてはいると、下着屋だった。どぎまぎする唯人をしり目に、手招きをすると、
「どっちが好み?」
聞いてきた。
「どっちでもいいし、俺に聞くなよ。困るだろ? それに前はこういうところは困るだろうからとか言ってなかったか?」
「察するに黒が好みかしら? そんな顔してるもの」
「いや、ピンクだな」
思わず答えてから、
「自分の好きなの買えばいいじゃないか」
慌てて返した。梨乃は紫のほうを会計してから、外に出る。それを追って唯人は外に出た。
唯人と梨乃はショッピングモールを出る。再び暑い世界に踏み出すと、梨乃は日傘をさした。強い日差しの中を唯人はこっそりと日蔭側に回って、傘の恩恵を受けていた。
「これからの予定は? 今日はこれで解散か?」
唯人は、額の汗をハンカチで拭いながら聞いた。このあたりは、少し高めの建物が多く、地面もアスファルトやコンクリートで塗り固められているから、ヒートアイランド現象でも起こっているのだろう。異常な暑さに結論を出すと、日傘の中をのぞいた。
「これから行きたい場所があるんだけど、いいかな?」
最初から今日一日は振り回されると覚悟していた唯人は、
「別にどこだっていいよ。どうせこの時間からできることも行ける場所も限られてるだろうし」
さすがに周辺で済むだろうと思った唯人は迷いなく、少し投げやりに言った。
「私も行ったことがなくてさ。別に人が大勢いる場所でもないから、あんまり見られることはないと思うよ」
二人が先ほど注目を集めていたことは、見ないふりをしていても感じていたらしい。気遣うそぶりを見せると中心部から少し離れるようにして歩いて行った。少し歩くと、中心部からは外れた場所に来ていた。人通りは少なく、しかし皆無ではないといった感じの場所だった。
「ここなんだけど」
そう言って梨乃が指さしたのは、一つの建物だった。一見すると普通だが、入り口には宿泊や休憩の文字があり、ラブホテルであることが分かった。
「こんなところに入るのか? ラブホテルだぞ? そもそも俺たちはそんなことする仲でもないだろうに」
唯人は疑うような目で見た。
「知ってるわよ、ラブホテルくらい。セックスする場所でしょ? 私、エロゲで見たことあるし」
そう得意げに断言する。
「お前は俺とセックスしたいのか?」
「どうだろうね。とりあえず中が気になるから入ってみたいの」
「とりあえず、こんな明るい時間に入る高校生はいないだろ」
唯人は言う。
「それに、ラブホテルって高校生は使えないんじゃ?」
「そこは心配無用よ。無人カウンターのところだし、第一今どきの中学生でも使うらしいよ。私って、人と話すことあまりないじゃない? でも、クラスの人の会話はよく聞いてるの。先々週もクラスの女子が彼氏と入った話とかしてたし、援助交際でおっさんと寝た話も聞くし」
「それはそれでどうなんだ? 進学校を自称するなら生徒も勉強するべきだよな。まあ、男女交際も認められてるからそういうのもいるだろうけど」
「とりあえず中に入るから」
「ちょっと、待て。本当に入るのか?」
梨乃は迷いなく、
「ええ、入るって言ってるじゃないか。とりあえず人もいなさそうだし、早いとこ入るよ」
食い下がる唯人を無視して、さっさと中に入る。仕方なくそのあとに続くと、梨乃はさっそく部屋を選んでいた。そして、
「こっち」
早くも決めたらしくさっさと部屋へと向かっていった。
「ラブホテルって、意外と綺麗なのね。新しいからかな。ここってどれも同じ部屋の形で設備らしくて、結構普段遣いするにはもってこいだってネットに書いてあった。たいていは部屋のグレードがあるみたいだけど、下から二番目あたりがコスパいいって聞くね」
「へえ、それは知らんかった。そして、俺初めて入ったんだけど、お前って入ったことあるのか?」
振り返ると、
「ゲームでだったら何回もあるけど、実際入るのは初めてだな」
指定の部屋に入ると、自動精算機が音声を発した。それに驚きながらも奥に進むと、案外普通のビジネスホテルのようで驚いた。ただ、天井にはプロジェクターがあり、カラオケの設備もある。お得感のある部屋だった。
「ベッドがキングサイズくらいある以外は普通だな。というか、ビジネスホテルにないようなものもあるな」
「そうね、これはお得かもしれない。また、ここに来て映画なんかを見るのもいいかもしれないな」
「いや、お前の家のテレビは十分大きいだろ」
そんなやり取りをしていると、梨乃は荷物を置いて、
「じゃあ、私はお風呂に入るから、お先」
風呂に入っていった。風呂には中が見える機能などはなく、ただの一般家庭のように洗面所から入るようだった。手持無沙汰になった唯人は、
「あいつ、何考えてるんだか」
そう思うと、ベッドに飛び込んだ。家のベッドでは到底できない、巨大なものだからこその感触に楽しくなってきて繰り返し、その後テレビをつけた。毎度のようにくだらないワイドショーを見ていると、家のテレビよりも映るチャンネル数が多いことに気が付く。
「ほんとにここ、お得な場所かもしれない。テレビも映るし、別にセックスのために来てない人もいるかもしれないな」
一人ごちた。テレビをぼうっと見ていると風呂からバスローブ姿の梨乃が出てきて、
「次どうぞ」
そう言った。
「中見たかったんじゃないのか?」
そう聞く唯人に、
「せっかくお金払うんだから、使えるものは使わないと損よ。風呂場広かったから、入ってきなさい。その間に、私は髪を乾かすから」
「はいはい」
本当に何を考えているんだか。いつも通りの無表情からは、今は何も読み取ることができなかった。しょうがない、と風呂場へ向かうと、梨乃の言う通り風呂場は広かった。
「ラブホテルだから二人とか三人とか一緒に入れるようになってるんだな」
服を脱ぐと中に入る。別に湯は張られていない。シャワーで体を流して、頭と体を洗う。先ほどまでの気持ち悪さがすっと引いていく。浴室から出ると不快感はなかった。梨乃と同じようにバスローブを羽織ると、帰るまではサラサラの服を着ていたいと部屋に戻った。
「早かったのね」
梨乃は髪を櫛で梳きながら言った。
「シャワーだけだったから。お前こそ風呂は溜めなかったんだな」
「あなたは私の残り湯で何をするつもりだったの? 期待した? エロゲでは飲むことが多いよね。美少女のゆで汁」
「言い方が悪いな、おい。ゆでられてないから、だし汁じゃないか? まあ、それはいいとしてドライヤー貸してくれ。髪乾かさないと風邪ひくから」
「クーラーの温度は上げておいたけど?」
「確かに最初は寒かったな」
そんなこんな話しながら髪を乾かす。唯人は、あとはテレビでも見て帰るか、と思いベッドに寝転ぶと、急に梨乃が馬乗りになった。
「なんのつもりだ?」
表情を険しくして唯人は眼を見た。
「抱いてほしい」
表情は一切不変で、どこか遠くを見ているような眼をしていた。
「もう一度聞く。何のつもりだ?」
先ほどよりも強い語気で再度訊ねた。
「抱いてほしいと言ったんだ。つまり、セックスだな。私とセックスしろと言っている」
「最初からこのつもりだったのか?」
「そうだな。なんとなく抱かれたくなった。ではだめだろうな」
そういうとバスローブを脱ぎ去った。先ほどの下着店で購入した、ピンクの下着を身に着けていた。
「先ほど聞いた好みに合わせえたが、ダメか?」
唯人は、下着など目には入っていなかった。梨乃は唯人のバスローブを脱がせにかかると、はだけさせた。自分の下着に手をかけて、それを自らの手ではぎ取ってしまうと、梨乃は唯人の手を取り自分の胸に押し当てた。
「意外と大きかったんだな」
「感想はそれだけかい?」
唯人は感触を堪能するでもなく、双丘を揉みしだくでもなく、ただ身体を見ていた。
「この傷、どうしたんだ」
体中の細かい傷跡を見る。胸から手を離すと、腰あたりに刻まれた少し大きめの傷跡をなぞった。
「こんな身体じゃあ、抱く気にもなれないか?」
珍しく、唯人が見るのは二回目だったが、前回の憎しみとは違った歪め方をした表情をじっと見た。
「いや、別にそういうわけじゃない。でも、最初からする気なんてなかったし、それよりも衝撃を受けてる。なんでこんなに傷だらけなんだ? 誰にされたんだ?」
そう訊ねると、梨乃は昏い目をしながら話し始めた。
「これをしたのは、家族だよ」
衝撃を受けた、と同時に、やっぱりか、という感情も湧く。以前、梨乃の家で家族写真を見ていた時の表情を思い出したのだ。
「私は、さっき行ったショッピングモールの経営をしている会社社長の娘だよ」
先ほどの買い物はどんな気持ちで行っていたのかを考える。
「と言っても、実の娘じゃなくてね。母の浮気相手との間の子なんだ。だから、父は私を恨んでいるし、母も生んだことを後悔しているんだ。それで、昔家にいたころは、毎日のように鞭で叩かれていたんだよ。だから私は家を出て、二度とかかわらない代わりに、いなかったことにしていいから、大学を卒業するまでは金を出してくれるように頼んだんだ。家を出る前に、遺産相続権放棄の書類と、それを妹に譲る旨を認めてね」
なおも裸のままの梨乃に、唯人は体を起こすとバスローブを肩にかけた。
「妹は、父と母の間に生まれた、いわば正当な子供で、二人から願われて生まれてきた。もちろん、私は妹を見たことがあるけれど、なでてやることも遊んでやることもしたことがない。
両親には、妹に近づかないことを厳命されていたからね」
空調の音だけが低くうなり、唯人は再びベッドに体を横たえた。
「妹は私とは違ってかわいがられたよ。なんでも与えられた。お菓子でも、ゲームでも、それこそ愛でもね。私には何もなかった。そして、自由すら与えられなかった。人とかかわる自由も、外を出歩く自由も、何もね。さっき言ったみたい可愛とは絶縁しようとしたんだけど、その自由すら与えられなかったんだよ。遺産放棄は承認されても絶縁を認めてくれることはなかったんだよ。お前には将来、利用価値のある人形として、どこかの愛人にするから、それまでは自由すらも与えないって」
むごい話だ。これが小さなころからなら、感情が出ないのも仕方がないのかもしれない。唯人はそう思った。
「それで、この傷なんだけど、これはすぐに消える程度で、痕が残ることがない程度で与えられた傷なんだよ。でもこの腰の傷は違う。両親から可愛がられた妹は、どんどんと傲慢になって、虐げられる私をいじめることに躍起になったときにつけられたんだ。私は、自分で言うのもなんだけれど頭がよくて運動もできた。だれかの愛人候補にすると言われた小学生の時から、一応勉強はしろと言われて、簡単にできるようになってしまったんだ。小学生の時には、大学入試は日本の大学なら満点に近い点数を取れるようになった。そして、妹はそれに嫉妬したんだろうね。自分のあった頭の出来が悪いのは自分のせいなのに。自分からはかかわってはならなかったけれど、私を虐待する単に嗜虐的な笑みをもって私に近づいた妹をだれも止めなかったんだ。私は、そのころには冷めきってしまっていて、されるまま、泣くこともわめくことも、許しを請こともなかった。だから、余計に腹が立ったのかもしれないね」
独白はゆっくりと行われていた。その目はいまだに唯人を見てはいなかった。
「それに、私はアルビノなんだ。だから、普通の人と見た目が違う。だから、両親も気味悪がっていた。そのことを知っていたんだよ、当時の私は。それで、学校でも友人なんていなかった。かかわりを禁じられていたから。教室で一人、本を読んでいることが多かったよ。それで学校でもいじめられたけど、反応がない私に飽きて一週間で無視してくれたのはうれしかったな」
自虐的に嗤う。
「何もかもが詰まらなかった。誰もかもがおろかに見えた。見た目がよくて頭がよくて運動ができるのに、だれにもかかわろうとしない。私は退屈な人形だったんだ。高校二年になってからは、地元を離れて、違う土地に来た。金だけは出してくれた。無関心だった、私がいようといまいと。そもそも私が勉強を始めたのは、家族として認められたいという承認欲求があったからなんだ。それすらも、認められなかったけれど。テストで満点を取ろうが、かけっこで一位を取ろうが、無意味だった。関心なんて、生まれた瞬間から持ってもらえなかったんだよ」
唯人には、なんとなく理解できた。母さんが死んでからの父さんは変で、ただ認めてほしかったけれど、父親は何も言ってはくれなかった。それでも、梨乃のように虐げられたわけではない。ただ、他人のような関係性になっただけだった。家を共にしても、接触はほとんどなくて、それでも幼馴染がいた。自分には話しかけくれる人間が、相談できる人間がいた。それが梨乃にはなかった。人との接触が許されなかったのならどうしようもないのかもしれない。
「私は、転校してから、なぜ生きているんだと聞いていだろう? あれは、私はこんな思いをして、転校して、家族から距離をとって、人を信用してなくて、それでもただ生かされていて……。私に告白してきたり、話しかけてきたり、はたまた人気者だったり……。どうして、幸せに生きているのか、何を目的に生きているのか。それを知りたかったんだよ。別に変人と噂されてもよかった。答えてもらえるなら、それでよかった。自分の生きる意味を明確に持っている人間がいて、もしくは持っていないあいまいな考えの人間がいて、それでよかったんだ。
でも、だれもはっきりとは答えなかった。あなたとは違って」
ここで、視線を引き戻して唯人を見た。
「それで、あなたと恋人ごっこがしたかったの。なんだか、ちゃんと答えただけでも自分がいることが言ってもらえていて、何とか存在していられる気が初めてして。だから、抱いてほしいの。あなたに、私を。セックスして処女を失って、それを父に報告して。それで何かしら反応してくれるなら、それでいいの。愛人にすると言っただろうが、と鞭うたれるだけでもいいの。それで、家族になれるなら」
梨乃は初めて涙を見せていた。唯人は梨乃の肩を押して、強引に押し倒した。
「それは間違ってる。間違ってるよ、お前は。家族なんかじゃない。気持ちの悪い何かだ。お前が満足しようが、何をしようが、勝手だ。でもな、それは決して家族のコミュニケーションでも何でもない」
「空虚ななにもない人形の私は、どうしようもないの。これくらいしか考えつかないの。別にあなたのことを嫌いか好きかもわからないし、胸の中がぐちゃぐちゃで引き裂かれてしまいそうで。空虚な人形を抱くのは嫌か? 家族になりたいって、人形が思ったらだめか? 存在自体が罪だっていうのか。消えてしまったほうがいいって、その考えが正しいっていうのか? 教えてくれよ、あなたは分かるの?」
号泣していた。何もかもを押し流して、封じ込めていた感情を開放して、表情がくずれて、泣いていた。懇願するように、
「ねえ、なんで生きてるの……」
唯人は、その唇を奪った。むさぼるように、舌を口腔内にねじ込んで絡めて、頭をつかんだ。驚いたように、梨乃は表情を変えて、離れようとした。それでも唯人は、梨乃の力ない両腕を片手でつかんで、片手では頭を固定して、あたたかな唇を、舌を、離さないでいた。数分とも数十分とも思える長いキスをした後、
「別に俺はお前のことは嫌いじゃなくなった。最初こそ面倒そうなのに目をつけられたって思っていたけれど、それでもそのころから意外なほどに嫌でもなかった」
「そう」
梨乃はぽつりと零した。
「俺が、今からお前を抱く。 だから、嫌なようなら今すぐ俺を押しのけてベッドから降りろ」
唯人は逃がすつもりなどなかった。全身で押さえつけていた。
「痛い。最初から逃がすつもりないじゃない。いいよ抱いて。私でよければ抱いて。いや、私を抱いて。今なら感情も何もかも開放して、ただただ、されるがままになると思う。私の初めてを奪って。それで……」
上気した頬となまめかしい菫色の目線に、唯人は先ほどのバスローブをはぎ取って、自分も全裸になった。それから、
「俺も初めてなんだ。だから、まあ、そういうことで」
「今更、照れるなよ。恥ずかしくなるじゃないか」
壁の時計を見ると時刻はまだ、五時だった。唯人は梨乃の身体をむさぼりつくした。
激しい腰の痛みとともに目が覚めたのは、朝の六時半だった。昨日のことは後悔していなかった。唯人は隣で眠る梨乃を見てから、ベッドからはい出した。洗面所に向かうと歯を磨いて、顔を洗った。昨日着てきた服は、汗が乾いてべたつきはなかったが、早く帰って洗濯したいと思った。スマートフォンの通知には、香織からのメール通知が表示されており、
「今日は帰る、心配かけてすまなかった」
そう書いた。そうこうしているうちに、梨乃が起きてきて、洗面所に並んだ。すでに機能の感情はなくなっており、前からの無表情に戻っている気もしたが、完全にそうでもなく、若干の照れと戸惑いの入り混じった表情が見え隠れしていた。
「おはよう。あなたは朝早いのね」
「そうでもない。昨日のことで三十分も遅く起きた。あとは腰が痛い」
「それは、自業自得でしょ。私の悲鳴も無視して動き続けるから」
昨日の様子を思い出して唯人は少しはにかみながらも、
「お前ってあんな声出たんだな。激しい言葉の後に、あのままマグロかと思いきやしっかり自分でも動いてたのな」
梨乃は唯人の足を踏んだ。
「別に好きでもない人と初めてして、嫌じゃなかったのか? こんな人形としてさ」
梨乃の言葉に、
「知ってるか? 恋愛のABCって」
唯人は聞いた。
「確か、Aはキス、Bはペッティング、Cはセックスだろう?」
「その続きでDEFZもあって、妊娠、結婚、家族、最後だってさ」
最近は、HIJKっていうのもあるらしいぞ」
「なにそれ、初めて聞いた」
首をかしげる梨乃に、
「Hは文字通りセックスをする、Iは愛が生まれる、Jはジュニアができて、Kで結婚するらしい。だから、もしかしたら昨日のことで愛が生まれるかもしれないって思ったんだよ。形だけの恋人から本当になれるかもなって」
「私と結婚するの? そうね、それもいいかもしれない。でもね……」
空白があった。
「でもね、さようなら。今日でこの関係は終わりよ。あなたの邪魔ばかりしていたし、こんな空虚な人形なんて放っておいたほうがいいわ。それに、私自身、あなたが好きかなんて分からない。あなたもそうでしょ? 昨日は私の口車に乗せられて、雰囲気に流されてしたこだってことにしてよ」
「どうして?」
唯人は問うと、
「だって、私ではあなたに釣り合わない。何もしないのに、何でもできる。人の数倍努力するあなたと、何の努力もなしに結果だけ取って、努力を踏みにじる私はふさわしくないでしょ? 何もしない私があなたのそばにいることはふさわしくないから……」
唯人はここで梨乃がすでに服を着ていることに気が付いた。
「だから、さようならだよ。もう連絡しない。願わくば、私がちゃんと人間になれたら、その時はまた話してほしい。あと、ホテル代は払ったから。それじゃあね、さよなら」
洗面所から出ていく彼女に触れることはできなかった。気が付いたようにその背中を追いかけて、部屋のドアを押し開けようとした梨乃に声をかけた。
「何かしてみろよ」
振り返らなかった。
「何かして、それから人間になって話しかけろよ。待ってるから」
不思議と待っていると口にしていた。別に何でもない、ただの元恋人への言葉ではなく、ただの知り合いに向けた言葉だった。
「応援してる」
頼れ、などとは言えなかった。すでに自分はフラれているのだから。それでも声をかけて、結局梨乃は振り返らずに扉が閉まった。
唯人は家に帰ると、扉の前で香織を見つけた。今は特に話したくない。自分の中で感情の渦と激しい炎と、それから少しの悲しさを鎮めるのに集中したい。
そう思っていても、昨日の夜に心配して連絡をくれた人間を放っておくことなんてできないし、昨日帰らなかった理由をきちんと説明するべきだと思った。
香織は、唯人に何があったのかは聞かなかったし、最初唯人は目が合っただけで何も話そうと思わなかったが、心配そうな姿を見てそう思ったのだ。
「とりあえず、上がって」
唯人は玄関開けると中に入り、振り返らずに香織に告げた。
「うん」
それ以上のことは口に出さなかった。父親が昨日帰ってきた形跡がないのを見て、安心してから、どうして父親が帰ってきていないのに安心したのだろうか、今までは何も感じていなかったのに、もうただの血縁者であるだけの他人だと思いきっていたのに。
唯人の思考は整理がつかないまま、魚群のように脳内を走り回った。香織がリビングに入ったのを確認して、エアコンの電源を入れ、冷蔵庫からオレンジジュースを取り出した。ガラスのコップに注ぐと、食卓の上に載せた。自分の分も注いだ唯人はひとまず一息に飲み干した。
余韻に浸るでもなく、ただただ最後の一滴まで飲み干そうとしたのでもなく、それでもコップを上に持ち上げて顔を上げたままでいた。椅子に座って、オレンジジュースをこくりとのどを鳴らして飲んだ香織は、何か言いたげな顔をしてそれでも何も言わずに言葉を待っていた。
「あのさ、俺……」
躊躇しながらも言う。
「昨日、梨乃とセックスした」
「そっか」
特に驚きもなく香織はまたジュースを飲んだ。
「それで、別れた」
「そっか」
今度の返事には若干の軽蔑と、憐憫と、それから同情が混ざっていた気がした。
「別に俺からフッたわけじゃないんだ。フラれたんだよ。別に俺もあいつも真剣に恋人だったわけじゃないし、最初から見せかけの恋人だってことは分かっていたはずだったんだ。それでもフラれたのはつらいものだな」
「ゆい君、今、ひどい顔してるよ」
「涙がにじんでいるか? それとも泣きそうな顔をしているか?」
訊いた唯人に、
「あの時と……、ゆい君のお母さんが亡くなって、お父さんが家を空けがちになって、その初めのほうの顔と同じ顔してる」
「そんな顔か?」
「ゆい君は取り繕うのがうまいから、多分学校の子たちは誰も気づかないと思うよ。でもね、私の眼はごまかせないよ。何年一緒にいると思ってるの? 多分、亮太と春香と浩志も分かると思うよ。付き合いが一番長い、私だけじゃなくて、三人にも分かるくらいの顔をしてる」
「そっか」
それ以上の言葉を唯人は持ち合わせていなかった。それが以外の答えもすべてひっくるめてそれで、そっか、と答えた。
「何も訊かないんだな」
静かに言うと、
「別に気にならないわけじゃないけど、言いたくなさそうな顔してるし、ましてやそれを無理に聞き出さなきゃってものじゃないから。ゆい君が話したくなったら話してくれていいよ。それまで待ってるから」
「そうだな。どうやって話したもんかな」
それは長い時間の始まりでもあったし、同時に心を整理するための時間でもあった。口外しない、とわざわざ口に出して約束してから唯人の話を聞き始めた香織に感謝品しながら、話し始めた。出会いから、別れまでの道筋を。
ゆっくりと話し始めてからかなりの時間が過ぎた。昼食には即席麺を食べながら話した。その途中でぽろぽろと涙がこぼれた。
そして昼の三時、冷蔵庫のアイスを出してから、はっきりと告げられた。
「自分で自覚してないだけで、はっきりと理解できてないだけで、ゆい君は刑部さんのこと好きだったんだね。自覚すればよかった。昨日、何もしなければよかったなんて、どうしようもないことをぐちぐち考えるのはやめたほうがいい。時間の無駄なだけよ。その状況で振られたのならどうしようもないんじゃない。その詳しい、秘密の内容とか過去とか、それに関しては話してくれなかったから知らないし自分から聞く気もないよ。ただね、自分を責めないほうがいい。落ち度はなかったと考えて、それで生きてるほうが楽だよ。明確な理由なんてなかったんじゃない。もしくは、別れの時の言葉がその通りの意味じゃなかったのかもしれない。だからこそ、分かろうとするのはいいけど完全に理解して、それで自分を責めようとするなんて、意味がない。そもそも、ゆい君は刑部さんのこと何も知らないじゃない。本当の姿を見たこともない、つらい過去を直接見たこともないのに、それを分かって悲しんで、それを忘れさせられなかった自分を責めるなんて傲慢なことこの上ないよ」
その言葉にはっとして、自分がいかに傲慢だったのかに気が付く。無駄に悩んでも意味はないし、そんなことで梨乃に何かしたいわけでもなかったのだ。ただ、彼女が話しかけてくれるのを待つべきなのだと気が付いた。
「ありがと、話聞いてくれて」
香織は、
「今度クレープのおごりでチャラにしてあげる」
そう言って帰っていった。それから唯人は、中途半端に残っている夏休みの宿題を仕上げてしまおうと決意すると、自室へと戻っていった。
第二節
「これでお願いします」
浩志は弁護士にそう言っていた。春香とのことがあって吹っ切れたのだ。自分を大切に思ってくれる人がいる。それならばわざわざ大切に思ってもくれない人たちと関わる必要なんてないのではないか。
絶縁状を送り付けるために文面を考えてもらっていたのだ。保証人などは春香の両親がしてくれることになっていた。そもそも高校生でそんなものを必要とすることはしないつもりだった。学費も食費も光熱費も今まで自分で出していたのだからさして変わりはないだろう。
「本当によろしいのですか? 絶縁状を出しても法的な根拠は一切ないのですから無駄になる可能性が高いですが」
「先生。これは僕が僕の気持に整理をつけるためにすることです。絶縁して二度とかかわりたくないと意思を示せれば十分なのですよ。僕は今まで文面に残さなくてもそういう風に生きてきました。今回はその決定的な書類を内容証明郵便で送ることが大切なんだと考えています」
「そうですか。この文面なら脅迫にも当たらないでしょうし、考えも伝わると思います」
「ありがとうございます」
浩志は事務所を出ると郵便局へ向かい内容証明郵便で書類を送った。
それから家に帰ると春香が待っていた。
「ちゃんと出せたー?」
その疑問に、
「ちゃんと書面は出したよ。僕はもうかかわりを持ちたくないって。親権を持っているからどうなるか分からないけどさ。気持ちの整理はできたよ。ありがと」
「うん、お疲れー」
その声色には若干の喜色が浮かんでいた。
「そう言えば、ようやく完成したわけだけどさ、この前のゲーム」
「そうだねー。結構わがまま言っちゃったからー。でも完成して良かったー」
「ホームページに昨日、ダウンロード用のリンクを張っておいたから見てくれる人もいると思うんだけど」
「見てもらえるといいねー」
今までの作品も評価してもらえていて、素人の趣味作品にしてはうまい具合だと思っているが、それでも浩志は願っていた。酷評されても良い。でも、少しでも気に入ってくれる人がいればいいなと。
「それで新作を作りたいんだけど?」
浩志は春香に言っていた。
「新作は、何人かが青春を送る中で出会ったかけがえのないものを守るみたいなテーマで作りたいなって」
「それって、何か意味あるの? 例えば私たちのこととか」
問う春香に、
「春香が伝えてくれた気持ちを大事にしたいって気持ちも入ってるけど、それも全部ひっくるめていろいろしたいなって」
「そういえば前に書いた、唯人たちのデート妄想イラストがあるからそれも使えたりして?」
「あと音楽も入れたいね。だからやってくれるかどうか分からないけど香織に頼んでみたいなって。一応はもともとピアノ弾いてた天才なんだから」
「それがいいかもね。最近沈んでる気がするから別のことを考えてもらうっていう意味でも」
浩志も春香も香織と亮太は何かあったんじゃないかと思っていた。感づいていた。しかし、口には出さない。それは本人が解決すべきものだと考えているから。
「それじゃ、連絡するね。……もしもし、僕だけど」
スマートフォンに話しかけた。
第三節
ピアノの前に座って一心不乱に鍵盤を叩く。香織は浩志に先日頼まれたゲーム音楽を制作していた。自分は弾くことはできるが作ることなんてできない。そんなことはしたことがない。そういったにもかかわらず、無理でも良いから作ってみてくれと言われた。趣味で作っているだけだから完成しなくても問題はないと。
グランドピアノで月光を弾くのが最近の香織がしてきたことだった。同じ箇所を何度も何度も繰り返す。それで何となく亮太とできないことを紛らわせてきた。今回の作曲では無性に集中できている。
今は曲のイメージを固めていた。春を感じさせる軽やかな曲を、と言われており鍵盤を叩いて悩んでいた。どれが正しいのか分からない。それは弾き方ひとつで変わるピアノ曲と同じ試行錯誤の仕方だった。
「違う、違う、違う」
イメージが固まらない。自分で自分にイライラをぶつける。髪をぐしゃぐしゃと乱した。
「少し休憩しようかな」
ピアノがある自宅の防音室から出るとキッチンへ向かい水を飲む。冷水が身体に染みた。
「亮太、聞いてる?」
香織は亮太に訊いた。
「聞いてるよ。俺は全然音楽分からないんだが、それで良いのか?」
疑問を呈する顔には真剣さからか眉間に皺が浮かんでいた。
「別に浩志と春香の趣味作品だから素人でも良いと思うの。いや、別に適当で良いというわけじゃなくて、素人が聞いて気持ち良いというか、イメージが浮かぶ曲が最良だと思うの」
「そっか、それなら続けようか」
亮太は、壁際の椅子に再び目を閉じて背中を預けた。
「別にそんなに身構えなくて良いってば」
香織は関係性の変化を、自分の亮太に対する感情が変化しているのを感じた。
今までは一緒にいるだけでセックスをしたくなった。好きだろうけど性欲の解消がもっとも大きな感情になっていた。
今は違った。ただ隣にいて欲しい。自分の欲望を抑えられる。音楽に集中すると、ただ楽しむ音楽をするとストレスを感じていてもそれは心地よい。むしろ楽曲のブラッシュアップでそれは解消される。
鍵盤を叩く。これで、前に感じていた愛する感情ではなく、欲望優先になってしまっているのではないかとい疑問が解消できた気がした。
「じゃあ、二枚目の左下を弾くから感想をお願いね」
すでに楽曲は完成していた。数日前に書いては消し、作っては壊しを繰り返した楽曲は一応の完成を見ていた。そして耳に気持ち良いか、それを追及していた。
流れるように指が鍵盤を滑る。素早く上昇したかと思えば下降する。感情の波は渦巻き、時に優しい音が耳をなでる。
弾き終わるとペダルから足を上げて椅子から降りる。
「どうだった?」
「そうだな。俺は良いと思うけど?」
「こことかどうだった?」
鼻歌を歌いメロディーを教える。
「別にそこは大丈夫だと思うけど。どっちかっていうとこっちのほうが気になるけど。なんていうんだろうちょっと楽しくないっていうか」
「楽しくないって。そっか。もう一回考えてみるね」
抽象的な意見だが香織は考えてみることにした。それにしても楽しくないというのはどういうことだろうか。疑問を抱えながらも、
「今日はここまで大丈夫。また今度よろしく」
「了解。また協力するよ」
香織は亮太を玄関から送り出すとふっと笑った。
第四節
夏休みにも関わらず、補習という名目で授業範囲が進むというめちゃくちゃな学校は多分ここだけではないだろう。そんなことをするくらいならば、最初から夏休みなどという名目を作らずに、本当の休みの期間だけにその名前を付ければいいのに、などと学校に対する苦情を心の中で思いながら、唯人は行われている授業を聞いていた。
これに加えて、夏休みという名目なのだから宿題を、などというふざけたことをぬかして、大量の課題を出してくるあたり、夏休みでも何でもないじゃあないか、と一人心の中で文句を言った。
とはいえ、こういうことを見込んで入学してきているのだから、高校と義務教育課程を同一視してはいけないし、勉強のために入ったのだからそれは義務であり、普段から自分で勉強している唯人にとっては、いわば小学校の漢字ドリルや計算ドリルと同じ、作業と化していた。
「宿題が進まない」
隣の席で、授業中にもかかわらず内職している生徒を見ると、これがバレたら後で呼び出されて怒られるに決まっているのに、どうして前のほうの席でするのかと疑問を抱いていた。
そうこうしているうちに、授業終了のチャイムが鳴り、本日の補習という名の授業の終了を告げていた。
「お疲れさん」
亮太は、すでに荷物をまとめていたらしく、チャイムが鳴ってすぐに唯人の席の前に立っていた。
「ようやく終わったな」
唯人の言葉に、
「本当にようやくだな。大体、なんで午前だけ授業ってどういう了見なんだろうな。それなら明日の分とか先に先に午後まで詰めてくれれば、何もない日が多くなるだろうにどうやら学校は俺たちに嫌がらせをしたいらしいな」
「同意見だ。無駄な時間だよな。何が補習だ、ふざけるな」
こっそりと吐き捨てると、教室にはほとんど生徒は残っていなかった。大体この時期は、運動部は夏の大会のために練習しているし、文化部は夏休み明けの学校祭に向けて作業をしているし、帰宅部なんていうものはそもそも速攻帰っている。暑い教室に残りたがるものなどめったなことではいなかった。
「とりあえず帰ろうか。唯人も今日、暇だろ? これから、香織の家で課題するんだけど、報酬は高いアイスで雇われないか?」
夏休みに入って二週間ほどたって、唯人はとっくに課題をすべて終えていた。今まで同様、残りでは勉強を続けている。どうしても勉強を続けなければならなかった。今やめてしまえば全てが水泡と帰すからだ。受験の合格者と不合格者の差は、毎日二十分ほどの勉強時間の差らしい。だいぶと有利に進めているつもりの唯人だが、ここで油断しては推薦入学という選択肢をつぶしかねないと思った。
ついでに言えば、梨乃と行ったラブホテルだって、見られていれば推薦への道が絶たれていたかもしれないことを考えると、少し軽はずみではあったかと思う。
「まあいいよ。横で勉強してるから分からないことがあったら教えてやるよ。その代わり、高いアイスクリームのちょっと大きめのを忘れるなよ」
「ちょっと大きめのって条件つけるんだな。まあ、了解したよ先生。とりあえず分からなそうなところを優先して聞くことにする。ほら、今の化学とか数学って複雑じゃん? 理系だからだろうけどさ」
「励み給え」
唯人は荷物をまとめて立ち上がり玄関に向けて歩き出した。今日も視線を受けていて、鬱陶しいことには変わりないが、そもそも梨乃と別れたことで余計に注目されている。
「気にすんなよ。人の噂も何とやらって言うし」
「そうだな。気にしないでおこう。ただ、あいつと別れて一番厄介なのは、今はフリーなら私にもチャンスはあるのではなんて考える馬鹿がいるくらいだな」
「そりゃあ考えるさ。フリーならワンチャンスって。刑部のほうも結構告白されてふってるらしいぞ。容赦なくな。心を折られているらしい。お前は優しく断るからしつこくいけば何とかなるかもって連中が増えていくんだよ。いっそ、『貴様らには興味がないからに度と話しかけるな、鬱陶しいんだよごみカス』くらい言ったらどうだ? マゾっ気があるやつなら喜びそうだけどな。綺麗な顔でののしられて」
「そんなこと言って教師からの印象が悪くなったらどうするんだ?」
「一般で受けても受かりそうだけどな」
「それとこれとは別なんだよ。前にも言ったことがあるだろ? みんなが勉強している中で、遊びまわりたいって。だからこそ頑張るんだよ。早いとこな」
「そうですか。勉強ができる奴は違いますね」
「馬鹿にしてるのかおちょくってるのかどっちだ?」
「それって、どっちも似たような意味じゃないか?」
馬鹿話をしながら帰路についた。相変わらず、夏は暑いし蝉はうるさい。この音を聞くだけで腹が立つのも仕方ないだろう。騒音規制法なんてものは蝉には適用されないし、どうしようもない。
「とりあえず一回帰るから。先に行ってて」
亮太とは玄関先で別れて、いったん家に帰る。どうやら父親は帰ってきていないようだ。
短時間なのにクーラーをつけるのもためらわれて、荷物の準備をしてからシャワーを浴びて着替える。スマートフォンを見ると昼食は準備済みの旨が入っていた。
鍵をかけて家から出る。すぐに隣の家に向かうとすでに準備が整っていた。手を洗う。食卓にはカレーが準備されていて、香織も亮太も春香も浩志もいて、だからこそ、自分は一人じゃなかったんだなと思い、席に座る。
「それじゃあ、いただきます」
声を合わせて言うと、カレーを頬張った。梨乃と自分との差はほんの少しでしかなかったのだろう。それでも、ほんの少しの差が機械的な人形か、感情的な人間かの決定的な差を分けたのだろう。どうしてもここで感謝しなければならないと思った唯人は、
「みんな、ありがと」
ぽつりと言った。
「はいはい」
「どうしたんだ、急に」
「どういたしましてー」
「なんかあったのか?」
「なんでもない」
唯人は、もう一口カレーを頬張った。