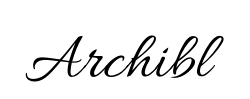第一節
夏休みも終わり、学校祭が近づいてきて、それでもその前に夏季休暇明けの課題テストがあって、校内もそわそわした落ち着きのない雰囲気が満ち満ちている中、唯人はクラスも出し物の裏方として手伝いつつ、テストに向けての勉強をしていた。
本当は執事喫茶だとか劇だとか、唯人に何かしらの役割が割り当てられそうになっていたのだが、忙しいとか練習時間が取れないとか、いろいろな理由をつけて裏方に徹していた。何かの役割が割り当てられてしまえば練習だとか、衣装合わせだとかでなんだかんだ時間がとられることに間違いはなかった。
「よく全部回避できたな」
亮太が隣で金槌を片手に言った。
「人聞きが悪いことを言うなよ。仕方なく、時間がないから仕方なくできなかっただけだ。それを回避しただなんて、とんでもない」
「そうですか、そうですか」
面白がるような言い方で顔を崩しながら言った。
「それでも裏方としては真剣にやらせてもらってるよ」
「目の前に参考書が広げられてなければ、少しは言うことも信じたんだが?」
「時間の有効活用といってほしいね。何はともあれ、学校祭前の準備期間にテストがあるから油断してられないじゃないか?」
「俺は、今回も十五位前後でいいよ。また、一位狙うのか?」
亮太は木の板に釘を打ちつけながら訊いた。
「そりゃそうだろ。奪還せねばならないからな、栄光の座を。まあ、一位のほうが二位よりもいいだろ? でも、ニュースとかでスポーツの競技会を紹介するときって、順位じゃなくて話題をとれそうな人を選ぶから、一位の選手が全く触れられもしないという可哀想なことになっているのもよく見るわけだが」
「確かに、一位のやつを紹介してやれよ、四位の有名な選手じゃなくてっていつも思ってるけどな」
「視聴率が全てなんだろうさ」
「そりゃ、それで金稼いでるからな」
夢も希望をない知名度こそ全てというメディアの闇を少し話したところで、
「よし、できた」
看板の基礎部分ができた。あとは表面に絵とか店名とか書いて支柱を廊下の壁に括り付けるだけだ。
「今日の作業はこれくらいにしておこうか。あとはセンスある人の指示を待とう」
「そうだな。やたらと張り切っていたクラス委員長が仕切りたそうだしな。それにお前のことをライバル視してるな。テストはずっと三位で刑部が来てから四位に繰り下がりだったしな。さっきの話じゃないけど、四位でも注目すらされないからな。可哀想に」
そう言って話していると、ちょうど委員長が部屋に戻ってきた。
「なにさぼってるの? 仕事は終わったの?」
「ちょうど終わって、委員長に見せようと思ってたんだよ。どう?」
亮太が言うと、
「まあまあね。あとはとりあえず支柱を水色にでも塗ってちょうだい。看板は美術部の子に頼むから」
「分かりました。委員長も忙しいでしょうけど頑張ってくださいね」
「お気遣いどうも」
肩を怒らせて他のグループの元に向かう委員長を見送ってから、
「お前、挑発しすぎだろう。顔が悔しそうだったぞ」
「別に俺は挑発なんかしてないぞ。単純に応援していただけだ」
「よく言う」
教室では小物を作っているクラスメイトがいるだけだった。家庭科教室では時間制でミシンの使用時間が決まっている。ちょうどこのクラスに割り当てられた時間だった。
「もうすぐ今日の時間も終わりだし、適当に時間つぶそうぜ。ペンキ探しに行くふりしてさ」
「それがいいかもしれないな」
二人は教室を出て、倉庫のほうへ向かった。
「ようやく下校時間だな。帰るか」
「そうだな」
玄関にいた香織が合流していた。そもそも春香と浩志は来なかったらしい。そう聞くと、
「授業ないのに来るメリットってないよな。締め切りがぁ、とか言ってたし余裕ないんだな」
「最初に宿題終わらせないからよ。結果として宿題と仕事の締め切りがかぶってデスマーチってわけ」
香織は呆れたように笑うと、
「帰りに公園でも寄ってかない? ジュース飲もうよ」
「帰ってからでもいいだろ?」
「外で飲むのも格別なのです」
三人で公園に入った。自販機にはさすがにホットの飲み物はなく、アイスばかりだった。炭酸飲料を買うと、近くの木陰になっているベンチに座り、
「コンビニでアイスも買って来ればよかった」
発していた。
「確かに、ジュースとアイスという組み合わせは最高だけどね、カロリーがすごいことになるんじゃないの?」
「香織は重たくなってないから大丈夫だ。見た目も変化してないし体重の変化をもたらすような体形変化はしてないと思うから」
「亮太、少し黙ろうか」
怖い顔で言われて、目を逸らし、ジュースをあおった亮太は、吹けもしない口笛を鳴らそうとしていた。
「それで、ゆい君。今回はやけに気合入ってるじゃない? いつもは余裕しゃくしゃくで、普段通りのペースを保ってる感じだけど、今回はめちゃくちゃ勉強してるから」
その言葉に、
「今回こそは一位を取るために一点を上げるための勉強をしてるんだ。満点でないと一位はないからな」
「ああ、刑部さんの満点伝説は続いてるもんね。普通のテストはもちろん、小テストも課題問題もすべて満点らしいじゃない。模試も満点だったみたいだし。あんな風になれたらなって思うけど、それじゃあ面白くないよね」
唯人は、
「話してないから知らないだろうけど、あんなふうになりたいなんて思うな。あいつ自身、あんなふうになりたくてなったわけじゃないから、すごい悩んでるんだから。俺がフラれたのもそれが一因でもある」
「そっかぁ、そこのところはぼかしてしか聞いてないから知らないけどそうなんだね」
先ほどまで口笛を吹こうとしていた亮太は、
「その話、俺知らないんだけど」
むくれたように言った。
「だって、話してないからな。香織に話聞いてもらってたんだけど、詳細は話してないし、他のやつにも話してない。聞きたければ、本人に聞いてくれ。多分話さないだろうがな」
「そっか、話す気ないんなら聞いても意味ないわな」
あっさりと納得して亮太はジュースを再び含んだ。
「話す時が来たらちゃんと話すから、お前にも春香と浩志にも」
「それならよし」
無言で炭酸を飲み干すとごみ箱に投げ入れ、かばんを持って立ちあがった。
「それじゃ、帰ろうか」
唯人の言葉に二人は笑って立ち上がると並んで歩き始めた。
第二節
もうすぐ文化祭だ。亮太は暑さを感じながら香織の家に向かっていた。今日は映画を見るから来て欲しいと言われたのだ。他の人は声を掛けたけど来られないと言われていた。
二人きりだなんて別に珍しくもない。友人として映画を見るだけだ。それなのになんだかドキドキしていた。
「いらっしゃい」
インターフォンを鳴らすとすぐに迎え入れられた。
「外は地獄だな」
汗をハンカチで拭きながら言った。
「リビングは冷えてるから。あとタオル持ってくるね」
リビングは確かに冷えていた。タオルで汗を拭っていると香織はブルーレイディスクを再生機にセットしていた。
「今日は何を見るんだ?」
「コメディー映画だよ」
「コメディーって珍しいな」
いつもはホラーとかラブストーリーを見ることが多い。
「なんとなく見たかったからさ。借りてきたの」
にこやかに笑う香織の笑顔が眩しく感じられた。
コメディー映画を見終わるとお昼を回っていた。軽食を食べながら鑑賞をしたので昼食は済んでいる。そこでディスクを取り出した香織が急に話しかけた。
「あのね、亮太。話があるの」
亮太は何を言われるのかと身構えた。
「復縁してくれない?」
自分もしたいと思っていた。それでも自分はまた依存してしまう。それでもいいのだろうかと考えた。どう答えるのが正しいのだろうか。
「どうして今?」
「ゆい君にはバレちゃってた。それでね、依存してようが何だろうが、きっと気持ちは本当だと思うから復縁してもいいんじゃないかって」
「バレてたのか。いや、バレてるんだろうなって思ってたけど」
「そうなんだ。実は最初から隠すのは無理だろうって、私も思ってた」
笑う。
「俺が香織に依存してるのはわかってるし、これからもそうかもしれない。それでも良ければもう一回やり直そうか」
「私も、多少は抑えられるようになったよ。それで普通に亮太のことが好きなんだろうなって思ったの」
「じゃあ、俺と付き合ってくれますか?」
亮太は告白した。答えはわかっている。それでも自分から、香織が納得したのなら自分から言いたいと思っていた。
「私が先に言うと思ったのに。でも、喜んで」
優しく抱擁を交わした。
「それで、久しぶりだからね……?」
「そうだな。香織。ちゃんと恋人に戻ったから」
二人で香織の部屋へと向かいベッドに倒れこんだ。
第三節
距離が縮まった気がした。二人の肩は触れ合っていた。
「新作だけど、卒業までを期間にゆっくり作っていこうと思うんだけど?」
浩志は春香にそう話した。
「良いと思うー。かおちゃんの音楽は完成したみたいだよー」
「そうだね。かなり出来は良かったよね。さすが天才って言うか。亮太にも協力してもらったみたいだし」
「あとでお礼言っとかないとねー」
「うん」
浩志と春香は笑いあった。浩志は卒業まではこの距離感が続くのだろうなと思う。それで、卒業まで好きでいたら。以前に言われたことを思い出した。
今までずっと好きだったんだ。卒業までの一年半くらい短いものだ。そう思いながら固めた構想を話した。